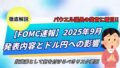2025年9月17日(水)のFX取引では、ドル円・豪ドル円を中心にトレードを行い、なんとか利益を確保しました。
昼間は比較的落ち着いたレンジ相場でしたが、夜中のFOMCをきっかけにドル円は一時145.48まで下落。
しかし、その後のパウエル議長の発言で流れが変わり、147円を超える場面も見られました。
この記事では、当日の相場の動きと収支の詳細を記録しつつ、私自身の体験や反省点、そして今後の見通しについても触れていきます。
日銀会合(18~19日)を控えた相場の地合いも含め、今後の参考になれば幸いです。
- 9月17日(水)のドル円・豪ドル円の値動きと市場環境
- 私の当日のトレード収支と取引詳細
- 実戦で感じた「ツールで見る軸」の変化
- トレード戦略・使った手法とその成功要因
- 今後の見通しと注意点
- 私見と体験からのアドバイス
- 初心者が気になる!!9月17日の相場展開Q&A
- Q1:夜中のFOMCでパウエル議長の発言内容は何が焦点だったのか?
- Q2:145.48まで落ちたドル円が戻した理由は?
- Q3:昼間の146.20~146.70あたりの値動きの中で注意すべきサポート/レジスタンスは?
- Q4:豪ドル円での動きはドル円と比べてどうだったか?
- Q5:損切りが14440円になった取引はどのような状況だったか?
- Q6:日銀会合をにらんだ展開とは具体的にどのようなシナリオが想定されていたか?
- Q7:当日の経済指標で注目すべきものは?
- Q8:トレード画面でツールの見る軸を変えたタイミングはいつか?
- Q9:利益11,898円の取引ではどれくらいのロット数を使ったか?資金比率は?
- Q10:今回夜間で147円を超える反発があったが、この先どの水準が意識されるか?
- 9月17日のFXトレードまとめと今後への考察
9月17日(水)のドル円・豪ドル円の値動きと市場環境
ここでは、2025年9月17日の為替市場におけるドル円・豪ドル円の主な値動きと、背景となった経済イベントを振り返ります。
昼間の落ち着いた値動きから、夜間のFOMC発表を経て発生した急変動まで、実際のチャート推移をもとに分析します。
昼間のレートの動き(146.20~146.70 → 146.40付近での推移)
午前中から夕方にかけてのドル円は、146.20~146.70の範囲で比較的落ち着いたレンジを形成していました。
値幅は大きくないものの、細かい上下の波を捉えればトレードチャンスも多く、個人的にはそこそこ「昼間でも十分に楽しめる相場」だったと感じています。
夜中のFOMC・パウエル発言での145.48から147円超えへの反発
FOMCの発表直後、市場は一気にリスクオフムードへと傾き、ドル円は一時145.48まで急落。
しかしその直後、パウエル議長の発言を受けて流れが大きく転換し、急激なドル買い戻しが入りました。

あの147円超えまでの巻き戻し、乗れた人はかなり気持ちよかったはずです!!
この夜間の値動きは、今週の中でも特に印象的な瞬間でした。
日銀会合をにらんだ市場参加者の思惑・予測要因
FOMCが終わった直後というタイミングで、次に市場が意識し始めたのが9月18~19日に控えた日銀会合です。
明確な方向感は出づらい中、ポジションを控える動きも見られ、全体的に「次の材料待ち」のムードが漂っていました。
私の当日のトレード収支と取引詳細
実際の収支はどうだったのか、どの通貨ペアでどのようなトレードを行い、どこで利益・損失が出たのかを具体的に解説します。
リアルな金額や取引履歴を公開しながら、トレード判断の根拠や反省点も含めて整理していきます。
利益の内訳:ドル円・豪ドル円それぞれの勝ちパターン
この日もっとも手応えを感じたのは、ドル円の夜の反発を捉えたトレードでした。
また、豪ドル円でも小幅ながら利益を積み重ねられたのが収支を安定させる要因に。
それぞれのエントリー/決済の根拠を詳しく振り返ります。
本日の利益:+10,974
本日も午前中は調子が良く、順調に利益を重ねていましたが、夕方以降は損切りが増えてしまいました。
改めて、油断は禁物だと痛感しています。

損切り額と反省点:トータル14,440円の損切りを取った局面
結果としてプラスで終われた1日でしたが、途中で取った損切り(トータル14,440円)は、判断ミスとエントリーポイントの甘さが原因でした。
値動きそのものは読めていたのに、焦って早めに入ってしまった典型的なパターンです。

“入らない勇気”って、トレードではめちゃくちゃ大事。
エントリーポイントの絞り方・改善したい点
この日は利確もできた一方で、「もう少し待ってから入ればよかった」と思う場面も複数ありました。
改めて、自分のトレードスタイルにおけるエントリーポイントの基準を整理し、改善点を明確にしておきたいと思います。
実戦で感じた「ツールで見る軸」の変化
トレードを重ねる中で、私自身の中で、使っている「ツールのどこを見るか」という視点が変化してきました。
ここでは、収益率順などの新しい視点を重視するようになった理由と、それがどのようにトレード判断に活きたかを実体験をもとにお話しします。
収益率順など別軸を重視した判断のメリット
以前は純粋な利益額ばかり見ていましたが、最近は「収益率」や「安定性」を意識するようになってきました。
特に小規模資金でのトレードでは、額よりも再現性のある収益を重視した方が良いという実感があります。
たとえば、10万円の口座で1日5,000円稼いでいるトレーダーの方が、100万円口座で2万円を出しているトレーダーより収益率では圧倒的に高い。
こうした視点を持つことで、「自分に近い環境のトレーダーを参考にする」というフィルタリングもできるようになりました。
それによって、自分が無理に資金を増やしたりして「規模の大きい人の真似をする」必要がないことにも気づけました。
視る軸を変えたことで、自分のトレード判断にもブレが少なくなったと感じています。
夜間の荒れ場を想定してツール画面構成をどう変えたか
夜のFOMCに向けて、ツールの表示を昼間とは切り替えて対応しました。
ボラティリティや指標速報、複数通貨の板情報を一画面で見られるようにしておくことで、値動きの流れを把握しやすくなりました。
夜のFOMCに向けて、ツールの表示を昼間とは切り替えて対応しました。
昼はスキャル向けのチャート重視、夜は指標速報やニュースフロー、ボラティリティ監視を優先するレイアウトに。
具体的には以下のように構成を切り替えています:
- 左側:ドル円・ユーロドル・豪ドル円の1分足+5分足チャート。
- 中央:経済指標速報・要人発言がリアルタイムに表示されるニュースウィンドウ。
- 右側:板情報とポジションサマリー(流れと出来高の偏りを把握)。
また、FOMC直前は1分足よりも15分足チャートをメインにすることで、荒れた値動きの大局を見ることを意識しました。
この切り替えができたことで、FOMC直後の急変にも冷静に対応でき、反発の兆しを拾う準備ができていたと思います。
トレード戦略・使った手法とその成功要因
今回はデイトレードとスキャルピングを状況に応じて使い分けました。
どのタイミングでどの手法を選び、なぜその判断が結果につながったのか。
具体的なチャートポイントや時間帯別の考え方を交えて解説します。
デイトレ・スキャルピングの使い分け
この日は時間帯によって戦い方を変える必要がありました。
昼間は小幅なレンジをスキャル気味に、夜はボラティリティが出たことでデイトレに近いトレードを展開。
この使い分けが収支を安定させた要因だと感じています。
【昼間の戦略:スキャルピング中心】
朝~夕方にかけては、ドル円が146.20~146.70あたりのレンジで横ばい推移。
この間、トレンドが出る兆しは見えなかったため、5~10pips程度の短期決済を繰り返すスキャル戦術を採用しました。
- 使用チャート:1分足と5分足を併用。
- 根拠:ボリンジャーバンド±2σからの反発/MACDクロス。
- 通貨:ドル円、豪ドル円
(豪ドル円はややボラ低め)。 - 回数:昼間は4回エントリー、全勝。
ただし1回の利益幅は小さめ。
あまり期待値を上げすぎず、「取りに行くというより、削られないように拾う」意識が功を奏しました。
昼間は無理せず、「静観+拾い」で正解だったと思います。
【夜の戦略:デイトレード寄りに切り替え】
夜はFOMCとパウエル議長の発言を控え、市場が徐々にリスクオン・オフを織り込む展開に。
特にFOMC後、ドル円が145.48まで下落したあと、深夜にかけて147円を超える場面まで反発したのを見て、デイトレ視点でのポジション取りに切り替えました。
- ポイント:一時的な下落後、下ヒゲの連発 → 反発サインと判断。
- エントリー:145.90付近でロング。
- 利確:146.85(直前高値のやや手前)。
- 根拠:RSIの急反転、MACDのゴールデンクロス、米債利回りの反発。
この場面では、「戻しがある」という想定を事前に持っていたことと、落ち着いて反転を確認してから入れたことが勝因です。
まさに、昼と夜での手法の切り替えが、今回の利益11,898円につながったと感じています。
経済指標・要人発言をどう先読みしたか
FOMCやパウエル発言の前後で相場がどう動くかを予測するために、事前に過去の値動きパターンや市場の期待値をチェックしました。
結果として「落ちてからの戻し狙い」がうまくハマった形です。
事前準備:過去3回分のFOMC前後の値動きを分析
パウエル議長の会見直後は、一時的にリスク回避でドル円が売られやすい傾向があることを事前に把握していました。
具体的には、前回6月・5月・3月のFOMCで、共通して「下落 → 反発」の流れが出ていた点に注目。
今回も同じく、最初に145円台まで下落したあと、すぐ反発に入るシナリオを軸に構えていました。
「戻し狙い」が成立した根拠とタイミング
FOMC発表後にドル円は急落し、一時145.48を記録。
しかし、その直後から1分足と5分足で連続した下ヒゲが確認できたため、「過剰反応→戻し」のパターンと判断。
- 根拠①:RSIが25を下回ったあと急反発。
- 根拠②:米10年債利回りが一瞬下げたあと上昇。
- 根拠③:パウエル発言が「予想よりややハト派」と受け取られた。
そのタイミングでロングエントリーし、戻りの波にしっかり乗れたことで、今回の利益につながりました。
要人発言は“リアルタイムで取る”より“シナリオで構えて待つ”
特に要人発言は、その瞬間の反応を取ろうとすると、誤読や急変に巻き込まれるリスクが高くなります。
私は今回、「いったん落ちてから戻る」というシナリオに乗れたことで、リアルタイムで無理に追わずに済みました。
マーケットがどう動くかではなく、エントリー前に「こう動いたら、こうする」という前提を決めておくこと。
それが、経済イベントを活かしたトレードにおいて最も重要な部分だと感じます。

“動いてから考える”じゃ、いつも遅れる。
今後の見通しと注意点
翌日から始まる日銀会合(9月18~19日)を前に、市場参加者の注目が集まっています。
この先の為替相場がどう動く可能性があるのか、またリスク管理面でどのような点に気をつけるべきか、私自身の展望と注意点をまとめます。
18日~19日の日本銀行金融政策決定会合を控えて意識すべきシナリオ
日銀会合が控えている今、無理にポジションを膨らませるよりも、リスクイベントを待ってから動く方が堅実な場面です。
想定できるシナリオと、それぞれに対してどう備えるべきかを整理しておきます。
今週はFOMCが終わったばかりというタイミングで、すぐに日銀の政策決定会合が迫っており、市場参加者の多くが「二段構え」で構えているような状況です。
FOMCの内容を受けてドル高方向に傾いたあと、日銀が何をするかによって、さらにその流れが加速するか逆流するかが決まってくる可能性があります。
私自身は、以下の3つのシナリオをベースに準備しています。
【想定される3つのシナリオと備え方】
① 現状維持・ハト派発言継続
円安方向がさらに強まりやすい。
ドル円・クロス円は上値追いに。
- 対応:イベント通過後の押し目買いを狙う。
発表直後の急騰には飛び乗らず、チャートの落ち着きを待つ。
② サプライズの引き締め姿勢
(YCCの見直しや利上げ議論の示唆)
円買い圧力が一気に強まるリスクあり。
過去にも急激な下落を演出した要因。
- 対応:ドル円・豪ドル円ともに短期的な売りを検討。
ポジションは軽めに、すぐに逃げられる態勢を。
③ 政策自体は据え置きだが、会見で微妙なタカ派ニュアンス
一時的に円買いされるが、持続性は低い可能性あり。
市場はその「トーン」を注視。
- 対応:ファーストインパクトには反応せず、会見内容まで見て判断。
逆張り狙いも視野に。
日銀の発表は、金融政策そのものだけでなく「黒田・植田ラインの温度感」や「円安牽制の有無」にも大きく影響されます。
過去の経験からも、「無風かと思いきや、会見で爆弾が落ちる」ことはよくあるので、個人的には“発表+会見”まで終わってからエントリーするのが鉄則です。
トレードの成否を分けるのは、「読みが当たったかどうか」ではなく、リスクイベントにどう備えて動けるかだと改めて感じています。
リスク管理(損切り・ポジションサイズ・資金管理)
損切り金額が増えてしまったことで、改めてリスク管理の重要性を痛感しました。
ポジションサイズ、ロスカットの位置、エントリー回数など、自分なりの基準を再確認しながら振り返ります。
損切り金額が増えてしまったことで、改めてリスク管理の重要性を痛感しました。
ポジションサイズ、ロスカットの位置、エントリー回数など、自分なりの基準を再確認しながら振り返ります。
この日の損切り額は合計で14,440円。
勝ちトレードもあった中でこれだけのロスを抱えた原因は、「根拠の甘いエントリー」と「リスク量のブレ」にありました。
【自分なりのリスク管理の3つの基準】
① ポジションサイズ
1回のエントリーで証拠金の5%を超えないようにしています。
調子が良くてもサイズを増やさず、連勝・連敗に関わらず常に一定の枚数で管理するのが鉄則。
② ロスカット位置
「感情的な損切り」ではなく、テクニカルに基づいた“撤退ライン”をエントリー前に必ず設定。
特に、直近安値/高値を割ったところに逆指値を置くのが基本です。
③ エントリー回数
1日で3回以上のエントリーは原則禁止。
「取り返したい」や「もうちょっと稼ぎたい」と思ったときほど、無駄打ちが増えて損失も膨らみがちなので、これはルール化しています。
実際この日も、夕方に連続でポジションを持ちすぎてしまい、見直すと「なくてもよかった負け」が2回ほどありました。
焦ってエントリーしても良い結果にはつながらないことを、今回も改めて痛感しています。
リスク管理は“攻め”の一部でもある
よく「リスク管理=守り」と言われますが、私は“攻めるために余力を残す”意味での管理が重要だと感じています。
1回の損切りがあるのは当然。
でも、それを想定内で収められるかどうかで、次のチャンスを冷静に狙えるかどうかが決まると思います。
このトレードスタイルを続ける以上、リスクとは「避けるもの」ではなく、「設計しておくもの」。
これが今回の負けから得た、いちばんの学びでした。
私見と体験からのアドバイス
今回のトレードを通じて得られた気づきや改善点、そして同じような局面で今後どう動くべきか。
過去の失敗や成功体験を踏まえて、読者の方にも活かせるようなアドバイスをまとめます。少しでも参考になれば幸いです。
昼間の動きが落ち着いてきたタイミングを狙うべき理由
昼間の相場は一見退屈に見えるかもしれませんが、逆に「一定のリズム」がある分、読みやすいと感じています。
経験上、動きが緩やかなときこそ、慎重なトレードがしやすい場面だと考えています。
実際、146.30〜146.60の間で小さな波が繰り返されるような時間帯では、レンジの上限・下限を意識した逆張りスキャルが非常に機能しました。
値動きの勢いに振り回されない分、落ち着いてパターンを探し、エントリーを厳選できるのが昼の時間帯の利点です。
昼間のこうした「安定感のある相場」で収支を整えておくと、夜のボラティリティが高い局面でも気持ちに余裕が持てるのも大きいと感じています。
夜の相場で「反転の可能性が高い局面」に入る見分け方
急落や急騰の後に「一瞬止まる」ポイントがあるのですが、そこから反転するか、さらに動くかの見極めが勝敗を分ける場面です。
私が見ている指標やチャートの形、タイミングについてお話しします。
まず、夜の相場では大きなイベント(今回ならFOMCやパウエル議長の発言)直後の動きは非常に荒れやすく、一方向に一気に走ったあと、数分間だけ値動きが落ち着く「間」が生まれることがあります。
このとき、以下のような兆候が見えたら「反転の可能性が高い」と判断しています。
【反転の可能性を感じるパターン】
- ヒゲの長いローソク足が連続する。
特に、1分足や5分足で下ヒゲ・上ヒゲが交互に出始めたときは、反転準備の合図になることが多いです。 - RSIが30や70にタッチした直後に一度戻す。
売られすぎ・買われすぎの調整が入るシグナルです。1分足と15分足のRSIを両方見るようにしています。 - 移動平均線(EMA20など)からの極端な乖離。
一気に離れたときは、「さすがに戻す動きが出やすい」と見て、逆張りで入る判断材料になります。 - 出来高の増加とともに逆方向のローソクが立ち始める。
下げていた中で陽線が強く出てきたときは、利確買いや反転勢の入りを意識して見ます。
初心者が気になる!!9月17日の相場展開Q&A
2025年9月17日の為替相場では、FOMC後の大きな値動きや、日銀会合を控えた慎重な空気感が印象的でした。
実際にトレードを行っていた中で感じた疑問や、他のトレーダーからもよく寄せられる質問をまとめました。
経済指標、要人発言、相場のクセ、そして損益や戦略の考え方など、本編とは重複しない視点で解説しています。
「なぜあのタイミングでそのように動いたのか?」といった細かい疑問の解消にお役立てください。
Q1:夜中のFOMCでパウエル議長の発言内容は何が焦点だったのか?
A:9月17日の夜中のFOMCでは、パウエル議長が米インフレの抑制状況と利上げの持続性への見方を示したことが市場の焦点でした。
特に、事前予想よりもタカ派ともハト派とも取れる曖昧さがありましたが、発言後ドルが一時的に147円を超える反発を見せたことで、「利上げが続く可能性」を再認識する動きが出ました。
Q2:145.48まで落ちたドル円が戻した理由は?
A:下落は FOMC発表前の警戒感とポジション整理が主因と考えられます。
発言後、利上げ長期化の可能性が織り込まれつつあったこと、またドル買い戻しが強まったことが反発をもたらしたと私は感じました。
Q3:昼間の146.20~146.70あたりの値動きの中で注意すべきサポート/レジスタンスは?
A:私が注目するのは、146.20付近がサポートとして機能していた点、146.70近辺が売り圧力が強まるレジスタンス帯だったことです。
これらを意識してエントリー/利確ポイントを調整しました。
Q4:豪ドル円での動きはドル円と比べてどうだったか?
A:豪ドル円の方がドル円よりボラティリティがある場面でした。
特に夜間のドル円反発を受けてリスク選好が高まったとき、豪ドル円がもう少し伸びる余地を見せていたので、そちらでのポジションを取るタイミングが複数ありました。
Q5:損切りが14440円になった取引はどのような状況だったか?
A:エントリーポイントを慎重に絞らなかったことが主な原因です。
夜間の急変に備えきれなかった画面の準備不足、自分の注文タイミングの遅れが損切りを余儀なくさせました。
Q6:日銀会合をにらんだ展開とは具体的にどのようなシナリオが想定されていたか?
A:会合での発言次第で「利上げ見送り」「現状維持」「将来の利上げ可能性の示唆」のいずれかが市場に影響を与えると見ていました。
もしタカ派な発言があれば円安が加速する可能性、逆なら急な反転もあり得るという想定でポジションを軽めにしていました。
Q7:当日の経済指標で注目すべきものは?
A:17日には米住宅着工件数・建設許可件数などがあり、これらが景気の先行指標として注目されていました。
それに加えてパウエル議長の会見内容が最も影響力がありました。
Q8:トレード画面でツールの見る軸を変えたタイミングはいつか?
A:私の場合、夜のFOMC発言後、チャートだけでなくボラティリティ指標・出来高・ドルインデックスの動きを並べて確認するよう変更しました。
それによって反発の起点を早めに察知できたことがあります。
Q9:利益11,898円の取引ではどれくらいのロット数を使ったか?資金比率は?
A:通貨ペアごとにロットは異なりましたが、全体資金の2〜3%をひとつのポジションにかけるようにしていました。
これが損切りを耐えながらも利益を伸ばせた理由だと感じています。
Q10:今回夜間で147円を超える反発があったが、この先どの水準が意識されるか?
A:私見では、次に注目されるレベルは147.50近辺、それを超えると148円を試そうとする動きが出る可能性があります。
ただし、日銀会合を控えて警戒ムードも強いため、強い指標や発言がない限り持続力に限度があると見ています。
9月17日のFXトレードまとめと今後への考察
- 昼間は146.20~146.70で比較的レンジ推移、夕方以降は146.40近辺で小刻みに上下。
- 夜中のFOMCで145.48まで下落後、パウエル議長発言で147円超えまで反発。
- 損切額:トータル14,440円。もっと4エントリーポイントの精度を改善したい。
- 日銀金融政策決定会合(18~19日)を意識したポジション取りが鍵。
本日のトレードでは、「レンジでの小動き」と「夜中の急変」の両方を捉えることができ、それが10,974円という利益につながりました。
特に、パウエル議長の発言で、ドル円が147円を超える反発を見せた場面を、タイミングよく利用できたのが大きかった一方で、損切りトータルで14,440円には、エントリーポイントの精査不足を痛感しています。
今後は18~19日の日本銀行会合をにらんで、市場の読みをさらに鋭敏にし、リスク管理を強化することが重要です。
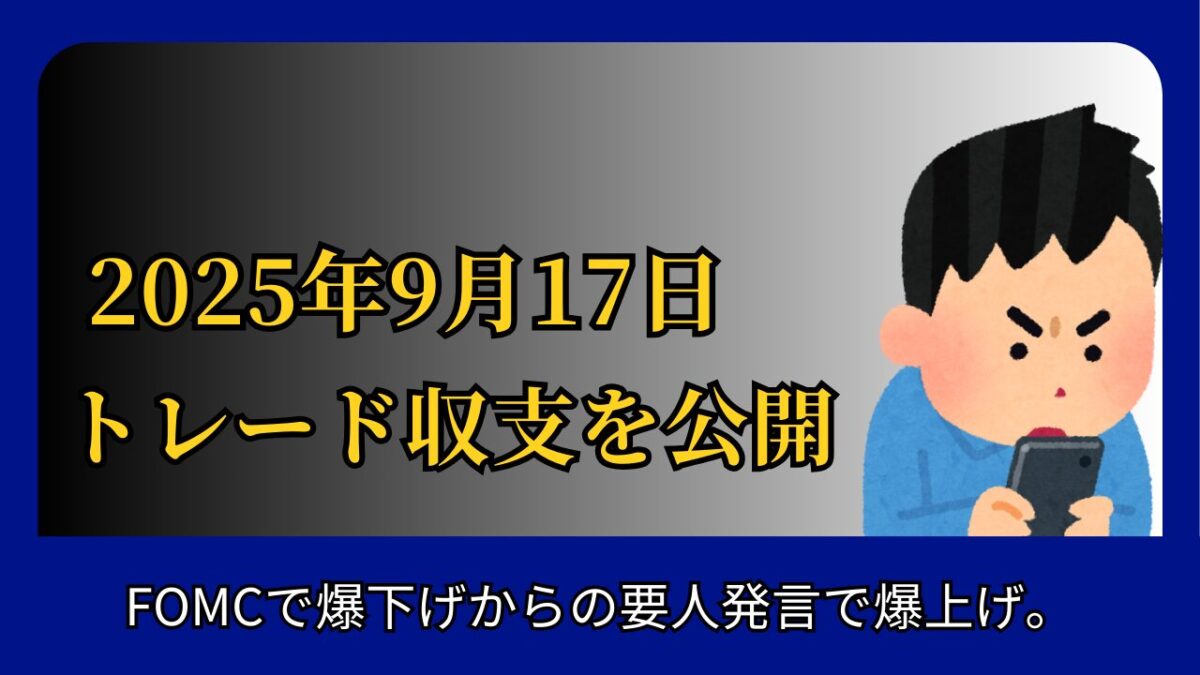




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン