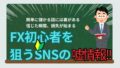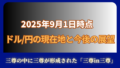今週(2025年9月第1週)は、私のように経済指標を軸に相場を見るトレーダーにとって見逃せない一週間です。
米国雇用統計、ISM、中国のPMI、ユーロ圏のインフレ指標など、市場を大きく動かす可能性のある★3つ以上の重要指標だけを厳選し、読み解いていきます。
私自身の経験も交えながら、為替相場やポジション戦略への影響を掘り下げます。
2025年9月第1週の注目【経済指標】スケジュール
今週(2025年9月1日〜9月5日)は、各国から発表される重要な経済指標が目白押しです。
特に、★3つ以上の高インパクト指標に絞って日ごとのスケジュールをまとめました。
実際に私がFXに活用している「見るべき指標」も含まれているので、ぜひ参考にしていただければと思います。
9月1日(月)中国:財新製造業PMI/アメリカ:ネーションワイド住宅価格指数/ユーロ圏失業率
10:45 中国:財新製造業PMI ★★★
中国の財新製造業PMIは、製造業の経済活動を示す指標であり、50を超えると拡大、50未満では縮小を示します。
市場では、PMIが50.0を超えると良好な経済状況が示唆されるため、重要な指標とされています。
前回の発表で49.5だったため、今回は安定した結果が期待されていますが、米中経済の動向によって市場反応は変わる可能性があります。
15:00 アメリカ:ネーションワイド住宅価格指数 ★★★
ネーションワイド住宅価格指数は、アメリカの住宅市場の健全性を示す重要な指標です。
前回は住宅価格の上昇を示しており、今回はそのトレンドが続くかどうかが注目されます。
特に金利の影響を受けやすいので、金利動向に敏感な市場では影響が大きいです。
18:00 ユーロ圏失業率 ★★★
ユーロ圏の失業率は、欧州経済の健全性を反映する重要な指標です。
直近の発表で失業率は安定的に推移しており、今回も大きな変化はないと予想されていますが、失業率の低下は消費者支出の増加を意味し、経済成長の期待を高めます。
市場は小幅な改善を予測しています。
9月2日(火)ユーロ圏消費者物価指数(CPI)/アメリカ:製造業PMI/米ISM製造業景気指数
18:00 ユーロ圏消費者物価指数(CPI)★★★
ユーロ圏のCPIはインフレの動向を示す最も重要な指標で、ECB(欧州中央銀行)の政策決定にも大きく影響します。
直近のデータではインフレがやや鈍化していたため、今後のインフレ期待に対する市場の反応が注目されます。
CPIの上昇が続けば、利上げの可能性が高まるため、ユーロへの影響が大きくなります。
22:45 アメリカ:製造業PMI ★★★★
製造業PMIは、アメリカの製造業活動を示す重要な指標です。
市場予測では、前回よりも若干の改善が期待されています。
製造業の拡大は、景気回復の兆しとして重要視されるため、ポジティブなデータが出れば、ドルへの買い圧力が強くなるでしょう。
23:00 米ISM製造業景気指数 ★★★★★
ISM製造業景気指数は、アメリカの製造業の景気を示す指標であり、特に50を超えている場合は拡大、50未満は縮小を意味します。
前回のデータでは拡大を示す結果が出ており、今回もこの傾向が続くかが焦点です。
特に製造業の回復がドルに与える影響が注目されます。
9月3日(水)アメリカ:JOLTS求人件数/耐久財受注
23:00 アメリカ:JOLTS求人件数 ★★★★
JOLTS(求人労働力調査)求人件数は、労働市場の健康を測る重要な指標で、特に景気拡大の際には注目されます。
前回は労働市場が依然として強いことを示すデータが出ており、今回はそのトレンドが続くかを見極めることが重要です。
企業の求人活動が活発ならば、経済回復の証として強いドルが期待されます。
23:00 アメリカ:耐久財受注 ★★★★
耐久財受注は、製造業の需要状況を示す指標で、特に設備投資の動向を示唆します。
直近では堅調な耐久財の受注があり、景気回復の兆しとして注目されています。
耐久財受注の増加は企業の設備投資拡大を意味し、経済の強さを示すため、ポジティブなデータが出れば市場も好感するでしょう。
9月4日(木)アメリカ:ADP雇用者数/貿易収支/ISM非製造業景気指数
21:45 アメリカ:ADP雇用者数 ★★★★
ADP雇用者数は、民間部門の雇用者数を示す指標で、米国の雇用市場の健全性を予測する材料となります。
前回は雇用の増加が予測以上に強かったため、今回はそのトレンドが続くのかに注目が集まります。
ADPの雇用者数が強ければ、米国経済の回復が確認され、ドル高を促進する可能性があります。
22:45 アメリカ:貿易収支 ★★★★
アメリカの貿易収支は、輸出と輸入の差を示す指標で、特に赤字が続く場合にはドルにネガティブな影響を与えます。
前回の発表では赤字が拡大したため、今回も赤字が続くと予想されています。
貿易収支の悪化はドル安要因となるため、注視する必要があります。
23:00 アメリカ:ISM非製造業景気指数 ★★★★★
ISM非製造業景気指数は、米国のサービス業を中心に、景気の回復具合を示します。
前回は好調な結果が出ており、今回はその強さが続くかが焦点です。
サービス業の回復は、経済全体にとって重要な要素であり、指数が強ければ、ドルへのポジティブな影響が見込まれます。
9月5日(金)アメリカ:非農業部門雇用者数/失業率
21:30 アメリカ:非農業部門雇用者数 ★★★★★
米国の非農業部門雇用者数は、以前発表された結果が予想を上回る増加となりましたが、その後、修正後に減少したことがありました。
この修正結果は、労働市場の回復に対する懸念を引き起こし、予想以上に雇用の伸びが鈍化していることが示唆されました。
修正後の結果は、ドル安の圧力を強める要因となり、米国経済の回復に対する市場の期待がやや後退しました。
失業率も同様に、改善しているものの、完全な回復には時間がかかるとの見方が広がりました。
したがって、今後の指標発表では、前回の結果の修正に基づき、雇用増加が鈍化する可能性も視野に入れつつ、ドルの動向を注視する必要があります。
21:30 アメリカ:失業率 ★★★★★
失業率は経済の健全性を示す重要な指標であり、低いほど経済が好調であると解釈されます。
前回の発表では、失業率が低下したことがポジティブに受け取られましたが、その後、修正が入って若干の上昇を見せる結果となりました。
もし今回、失業率が予想より上昇するようであれば、米国経済の弱さがより明確に浮き彫りになり、ドル安を引き起こす可能性があります。
逆に、失業率が低下し、さらに好転すれば、米国経済の強さを裏付ける結果となり、ドル高のサポート要因となるでしょう。
実際に、失業率が低下した場合、米国経済の回復力が強く示されることになり、特に消費支出の増加が期待されます。これが、ドルにとってポジティブな要因となります。
逆に、失業率が悪化するようなら、ドルの弱さを予想するべきです。
指標ごとの前回比較と私見
指標の意味だけでなく、「前回との違い」や「市場の反応傾向」を抑えることで、今後の値動きをより正確に読めるようになります。
ここでは、私自身のトレード経験を踏まえて、過去の数値と比較しながら、指標ごとの見通しや注意点を私見ベースで解説します。
中国財新製造業PMI:前回などとの違い、個人的感想
中国の財新製造業PMIは、製造業の景気を示す重要な指標ですが、直近の発表では若干の鈍化が見られ、50.0を超えるかどうかが焦点です。
前回の結果は49.5で、安定した製造業の成長を示唆していました。
しかし、世界的な経済不確実性や米中関係の影響を受ける可能性があり、今回の数値にどのような影響を与えるかが注目されます。
個人的には、世界的な供給網の混乱や、特に半導体などの重要部品の供給問題が引き続き影響する可能性が高いと見ています。
このPMIの数値が安定していれば、短期的な中国経済の健全性を示し、他の新興国市場にも良い影響を与えるかもしれません。
逆に下回れば、再度経済の減速懸念が市場に広がり、リスク回避の動きが強まる可能性も考えられます。
米ISM指数・JOLTS・耐久財受注:前回比と私の見立て・経験に基づく分析
米ISM製造業景気指数は、アメリカの製造業の健康度を示す重要な指標であり、前回の発表では50を超えたことで、製造業の拡大が続いていることを示唆しました。
今回も好調な数字が出る可能性が高いと考えていますが、製造業のコスト上昇やサプライチェーンの問題が影響を与える可能性があり、改善幅は限定的かもしれません。
JOLTS求人件数も労働市場の健康を示す指標で、前回の発表では求人件数が予想よりも強かったことが印象的でした。
私自身の経験として、求人件数が高い水準を維持すると、消費者支出や企業投資の継続を期待できますが、同時に労働市場の人手不足が景気回復を制約する要因にもなり得ます。
耐久財受注は、設備投資の動向を反映するため、非常に注目しています。
前回は予想以上の強い数字が出ましたが、現在の経済環境では企業が慎重な姿勢を取る可能性もあり、やや弱含みの結果が予想されます。
私としては、データが強ければ、アメリカ経済が引き続き成長しているという証拠として、ドル高を支える要因になると見ています。
ADP雇用統計と非農業部門雇用者数/失業率:市場との違い、筆者の展望
ADP雇用統計は、通常の雇用統計の前に発表されるデータで、米国の民間部門の雇用状況を示します。
前回のADPデータでは、予想を上回る強い雇用増加がありました。
私自身、ADPが強いデータを示した場合、非農業部門雇用者数がその後の発表でも強い結果となる傾向があると感じています。
しかし、ADPと実際の非農業部門雇用者数の間には時折差が出るため、安易に楽観するのは危険です。
非農業部門雇用者数は、労働市場の健康を示す最も重要な指標であり、前回も予想以上の強い結果が出ました。
今回も好調な結果が出る可能性が高いと予測していますが、過去に私が経験したように、雇用の増加が一時的なものではないかという懸念もあります。
失業率は、低ければ低いほど経済の健全性を示します。
失業率が低下すれば消費の増加が見込まれ、経済成長を後押ししますが、過去に失業率が低すぎると、労働市場の過熱やインフレ圧力が強まるリスクもあります。
個人的には、失業率がさらに低下し、景気回復が続くシナリオを予想していますが、同時にインフレ懸念も高まり、金融政策への影響が気になるところです。
ユーロ圏CPIと失業率:インフレと雇用情勢、個人視点からの捉え方
ユーロ圏CPI(消費者物価指数)は、インフレの動向を示す指標として重要です。
前回、ユーロ圏のインフレは予想よりも高く、ECB(欧州中央銀行)の政策に影響を与える結果となりました。
私としては、インフレの上昇が続くことで、ECBが早期に利上げを実施する可能性が高いと見ていますが、エネルギー価格や供給不足の影響が続く限り、インフレは高止まりするでしょう。
そのため、今後のインフレ指標には特に注目しています。
ユーロ圏の失業率は、直近の発表で安定的な低水準を維持しており、労働市場は順調に回復しています。
個人的には、失業率が低ければ消費者の購買力も高まり、経済成長を支える要因となるため、今後の指標でも引き続き安定した失業率が続くと予測しています。
失業率の低下は、インフレや利上げの懸念とともに、消費支出の増加や投資家心理にポジティブな影響を与えると見ています。
今週の為替動向と見通し
経済指標が市場に与える影響を見る上で、通貨ペアの直近の動きと、その背景を理解することが重要です。
ここでは、先週のドル・円・ユーロの値動きを振り返りつつ、今週の指標発表を受けた為替の動き方を予測していきます。実際に私が注目している通貨ペアも取り上げています。
先週からの米ドル・ユーロ・円の推移
先週の為替市場では、米ドルは安定した強さを維持しました。
特に、米国の経済指標が予想を上回る結果となり、市場では米ドル買いの動きが続きました。
米ドルは引き続き注目されていますが、ドル円は150円付近の水準ではなく、実際には146円台半ばから148円台後半を推移していました。
これは、前週の指標発表後に一時的に強含みましたが、他の通貨に対してドルの上昇ペースが若干緩やかになったためです。
ユーロは、ユーロ圏のインフレ指標が予想を上回る結果となり、ユーロ高を支える要因となりましたが、依然としてECBの政策が金融緩和的であることから、ユーロの上昇には限界がありました。
ユーロは一時的に1.75ドル付近まで上昇しましたが、経済成長の鈍化懸念や低金利政策が続く中で、徐々に弱含みました。
ユーロ円は、先週は172台半ばで推移しましたが、最終的には172円割れまで下落しました。
日本円は、米ドルの強さや相対的な低金利政策が影響し、円安が続きました。
米国の利上げ観測が強まり、ドル円は147円台を中心に推移しました。
円は引き続き弱含み、特に米国金利差が為替に強く影響を与えている状況です。
各国指標が為替に与える短期影響の予想(私見含む)
米国経済指標は引き続き為替市場に大きな影響を与えると予測します。
特に、ISM製造業景気指数や非農業部門雇用者数は、米ドルの動向に直結します。
もし、これらの指標が強い結果を示すと、米ドルの強さが一段と強まり、ドル円が更に上昇する可能性が高いです。
特に、雇用者数の増加が予想を上回れば、米国経済の回復力が確認され、ドル高をサポートします。
ユーロ圏のCPIや失業率も重要な指標です。
ユーロ圏のインフレが高いままで推移すれば、ECBの利上げ観測が強まる可能性があり、ユーロの支援材料となります。
ただし、ユーロ圏経済の成長鈍化懸念もあり、ユーロ高には慎重な見方をしています。
特に、失業率が改善しても、全体的な経済成長が乏しい場合、ユーロは上昇を続けにくいでしょう。
日本円に関しては、米国の金利差が引き続き円安圧力をかける要因となります。
特に、米国の利上げが加速する場合、円安が進行し、ドル円は一段と強くなる可能性が高いと見ています。
円は、低金利政策を維持する限り、米ドルやユーロに対して弱い位置に留まるでしょう。
今後の為替変動要因(米利下げ・ECB政策・中国PMI)
米利下げの可能性が市場で囁かれる場合、米ドルは大きく影響を受けるでしょう。
もし、米国が利下げに踏み切れば、米ドルは一時的に下落する可能性があります。
特に、米利下げは投資家のリスク選好を高め、米国経済が悪化しているというサインとして受け取られれば、ドル売りが加速する可能性もあります。
しかし、現時点では利下げの可能性は低く、米ドルには上昇基調が続くと予想しています。
ECBの金融政策も重要な影響を及ぼします。
ECBがインフレを抑えるために利上げに踏み切る場合、ユーロ高が進みます。
逆に、引き続き緩和的な政策を維持する場合、ユーロは弱含みとなり、ドル高の動きに押される可能性があります。
私見としては、今後数ヶ月の間でECBが早期に利上げに踏み切ることは難しいと考えており、そのためユーロは引き続き弱い位置にあると見ています。
中国PMIが経済の指標として注目されます。
中国経済の減速がPMIを通じて示されると、リスク回避の動きが強まり、ドルや円が買われる展開が予想されます。
特に、中国の製造業の減速が予想を下回れば、世界経済の不安定性が高まり、円は一時的に安全資産として買われることが予想されます。
逆に、中国経済が安定を見せれば、リスクオンの動きが強まり、円安が進むでしょう。
今週のポジション戦略
「どこでエントリーするか」や「どこでリスクを回避するか」という判断は、トレードにおいて常に重要な課題です。
ここでは、デイトレードと中長期視点の両方から、今週の経済指標を受けてどのようなポジションを取るべきかを具体的に考えていきます。
また、私の過去の成功例や失敗談をもとに、実践的で有効な戦略をご紹介します。
デイトレーダー向け:短期的注目ポイントと私のトレード経験
デイトレードでは、短期的な経済指標や市場の動きに敏感に反応することが求められます。
特に、米国の非農業部門雇用者数や製造業PMI、CPIなどの重要指標が発表されるタイミングでは、短期間で大きな値動きが起こりやすいです。
私自身もデイトレーダーとして経験してきた中で、注目すべきポイントは、指標発表前後のボラティリティと市場の過剰反応です。
例えば、失業率の発表直後に大きな価格変動が起きることがありますが、その動きを見極めて早期にエントリー・エグジットすることが利益に繋がります。
また、ポジションサイズの管理が非常に重要です。
私も過去に、急激な価格変動に巻き込まれて大きな損失を出した経験があります。
これを防ぐために、指標発表前に ストップロス を設定しておくことが基本です。
中長期投資家向け:指標で左右されにくい構え方
中長期投資家にとって、短期的な経済指標の影響を過剰に気にすることは、焦りや過剰反応を引き起こす可能性があります。
確かに、失業率やGDP成長率などの指標は重要ですが、長期的な視点で見れば、日々の変動は一時的なものであり、基本的には企業のファンダメンタルズや業界全体のトレンドに注目することが重要です。
私の経験上、定期的なリバランスが中長期投資には欠かせません。
例えば、景気後退が予測される場合、リスク資産を減らし、金利上昇に対応するために債券や金に分散投資するなど、ポートフォリオを市場の動向に合わせて調整することが利益を生みます。
また、企業の成長性や市場シェアの拡大に注目することで、長期的に良いパフォーマンスを得ることが可能です。
短期的な経済指標に一喜一憂せず、自分の投資哲学に基づいて堅実に運用することが重要です。
リスク管理の重要性と私の実体験から学んだ教訓
リスク管理は、どんなトレーダーや投資家にとっても最も重要な要素です。
私も初心者の頃は、ポジションサイズの過信から大きな損失を出した経験があります。
特に、過度なレバレッジや指標発表直後の過剰ポジションが原因で、大きな失敗をしてしまいました。
リスク管理で最も大切なのは、自己資金の何%をリスクにさらすかを事前に決めることです。
私の場合、1回のトレードで最大1〜2%のリスクを取るようにしています。
このルールを守ることで、仮に連続して損失が発生しても、総資産への影響を最小限に抑えられます。
また、トレードの前に必ずストップロスを設定することも重要です。
特に、ニュースや経済指標が発表される前後では、予想外の価格変動が起きることが多いため、事前に計画的なリスク管理を行うことが成功への鍵です。
最後に、精神的な安定もリスク管理の一環です。
過去に、損失を取り戻そうと焦ってエントリーした結果、大きな損失を出したこともあります。
その経験から、冷静に市場を分析し、焦らずにルールを守ることが最も重要だと感じています。
今週の注目指標と気をつけるべきポイント
今週の指標はどれも重要ですが、特に注視すべき「相場が大きく動く可能性が高い指標」がいくつかあります。
ここでは、★4~★5つに該当するハイインパクト指標を中心に、その特徴や注意点、私がトレード前に意識しているリスク管理のコツなども含めて詳しく解説します。
特に重要な指標ランキング★★★/★★★★/★★★★★の解説
経済指標はその重要度によって、市場に与える影響が大きく異なります。
ここでは、★★★、★★★★、★★★★★のランク別に、各指標が市場に与える影響について解説します。
★★★(重要度:中程度)
このランクに分類される指標は、市場の短期的な動きに影響を与えることがありますが、長期的なトレンドにはあまり大きな影響を与えません。
例えば、財新製造業PMIやユーロ圏失業率などが該当します。
これらは市場のセンチメントに一時的な影響を与えることが多いですが、長期的な成長性や政策の方向性には直接的な影響を与えることは少ないです。
★★★★(重要度:高)
このランクは、市場の短期的なボラティリティを引き起こす可能性が高い指標です。
たとえば、ISM製造業景気指数やユーロ圏消費者物価指数(CPI)などが該当します。
これらはインフレ動向や製造業の景気感を反映し、中央銀行の政策変更のシグナルとしても解釈されます。
特に、CPIやPMIは為替相場や株式市場に即座に反映されるため、注意深く見守る必要があります。
★★★★★(重要度:非常に高い)
このランクに分類される指標は、市場に与える影響が非常に大きいです。
代表的なものとしては、米国の非農業部門雇用者数(NFP)や米国失業率、ISM非製造業景気指数などがあります。
これらの指標は、中央銀行の政策決定や経済全体の健康状態を反映するため、市場はこれに大きく反応します。
特にNFPは、米国経済の強さや弱さを示す最も重要な指標の一つとして、ドルの動きに直結します。
結果に振り回されないための心構え(私の失敗談や教訓など)
経済指標の結果が発表されるたびに、私も以前は感情的にトレードをしてしまうことがありました。
特に重要な指標が発表される瞬間、その結果に大きく反応してしまい、その後の市場の動きを冷静に見守ることができなかった経験があります。
例えば、ある時、米国の雇用統計が予想以上に強い結果だったため、米ドルが急騰しました。
その瞬間、「これは絶好のチャンスだ」と感じてポジションを取ったのですが、その後修正が入ってドルが反落しました。結果的に大きな損失を抱えました。
私の教訓として、どんなに重要な経済指標であっても、その結果だけに振り回されないことが大切です。市場の反応は短期的には予測不可能なことが多く、冷静に状況を分析した上で行動することが重要です。
私が実践しているのは、指標発表後の動きを見極めることです。
指標が発表された直後に取引を始めるのではなく、数分から数十分後に市場がどのように反応しているかを見てから、ポジションを取るようにしています。
これにより、過剰な反応を避けることができ、損失を最小限に抑えることができました。
さらに、指標の結果が悪くても、必ずしもそのまま市場が一方向に動き続けるわけではありません。
リスク管理を徹底し、ポジションサイズを調整することで、指標発表後に不利な状況に陥ることを避けることができます。
よくある質問:2025年9月第1週の経済指標について
この記事の内容に関するよくある質問のコーナーです。
9月第1週に発表される重要な経済指標に関する疑問を解消し、トレードや投資戦略に役立つ情報を提供します。
具体的な指標の詳細や、相場への影響についても触れていますので、ぜひご参考にしてください。
Q1:ISM製造業景気指数(米国)とは何ですか?
A: 米国の製造業の景況感を示す代表的な指数で、50を上回ると好調、下回ると縮小を示します。経済の先行きを図る重要データです。
Q2:JOLTS求人件数はなぜ注目されるのですか?
A: 労働需給のひとつの指標で、過熱した労働市場や不均衡を読み解くことに使われます。
Q3:非農業部門雇用者数とADP雇用者数の違いは?
A: 非農業部門雇用者数は政府統計、ADPは民間企業の集計であり、前者が正式な雇用統計として注目されます。
Q4:ユーロ圏CPIが為替に与える影響は?
A: インフレ抑止の観点からECBの政策を左右し、ユーロの価値を動かす可能性があります。
Q5:財新製造業PMIと公式PMIの違いは?
A: 財新は中国の民間調査機関が発表するPMIで、より早く市場に影響しやすい「フラッシュ指標」です。
Q6:為替予想に有効な指標は?
A: 雇用統計、CPI、PMIなどが特に影響力が大きいです。
直近の私の感覚では”非農業部門雇用者数”が特に反応が強かったです。
Q7:ポジションを持ちすぎないコツは?
A: 指標発表前は手仕舞いする、発表結果を確認して再エントリーするなどの戦略が安全です。
私も痛い目に遭いました(笑)。
Q8:ISM非製造業と製造業、どちらが重要?
A: 米経済はサービス業が大半なので、ISM非製造業はより注目度が高い傾向です。
Q9:耐久財受注が経済に与える意味は?
A: 生産財への需要指標で、製造業の先行きや景気トレンドを示唆します。
Q10:失業率が低下すると何が起きる?
A: 消費の上昇や賃金上昇圧力につながり、場合によっては利上げ期待が高まります。
まとめ:2025年9月第1週の経済指標とその影響
- 9月第1週は、米国、ユーロ圏、中国の重要な経済指標が発表されます。
- ★3以上の指標に絞り、各指標の予測と市場への影響を分析しました。
- 特に米国の雇用統計やISM指数がドルに大きな影響を与える可能性があります。
- トレード戦略は、指標発表後の反応を見て、リスク管理をしっかり行うことが重要です。
- 今週の注目指標はISM製造業景気指数、非農業部門雇用者数、ユーロ圏失業率です。
9月第1週は、労働市場や購買担当者指数、インフレ動向という異なる角度から経済の全体像を探る重要な1週間となります。
米国の雇用統計、ISM製造業/非製造業の景況感、中国の製造業指標、ユーロ圏の物価と雇用など、多様な側面が浮かび上がります。
こうした指標の結果を踏まえ、私はこれまでの経験から「市場の反応が先行する慣性にも注意」「指標当日はポジションを小さくする」などの心構えが有効だと感じています。
この記事では、前回との比較を丁寧に行いながら、私的な視点や体験談を加えることで、単なる情報提供にとどまらない深みのある構成を目指しています。
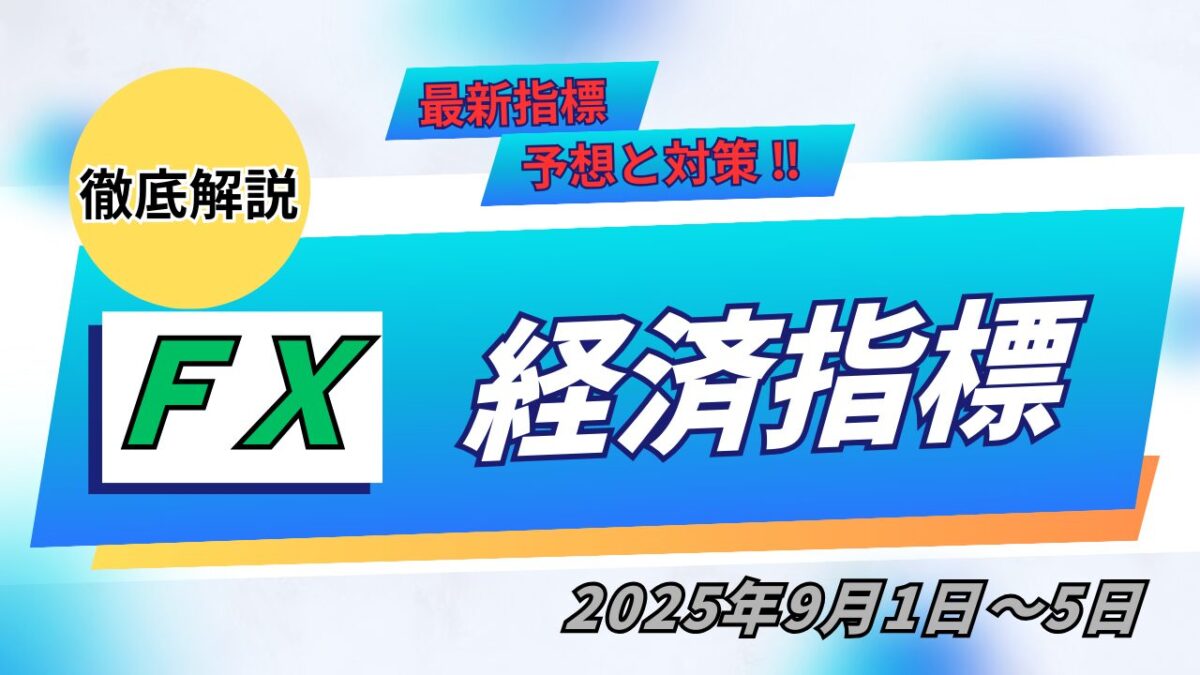




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン