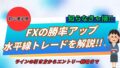2025年9月15日(月)〜9月19日(金)の1週間は、重要な経済指標が集中しています。
小売売上高、消費者物価指数(CPI)、複数の政策金利発表など、マーケットに大きな影響を与えかねないイベントが目白押しです。
私自身、この週は毎朝チャートを開く前に「今日は何があるか」を確認するほど慎重にポジションを取ります。
特に、FRBや英中銀、日銀の金利動向が焦点となるだけに、為替相場のボラティリティも高まりやすいでしょう。
この記事では、今週発表予定の主要な経済指標の整理、先月との比較、そして通貨ごとの見通しやポジション取りの注意点について、私の視点も交えて詳しく解説します。
今週発表の注目指標一覧【9/15〜9/19】
2025年9月第3週は、マーケットの動きを左右するビッグイベントが連日続く1週間になります。
毎日のように重要指標が発表され、通貨ペアによってはスプレッドが広がる場面も増えるでしょう。
私も週の初めには、全体のスケジュールをざっと把握しておくようにしています。
これだけ多くの指標が並ぶと、事前準備の有無が明暗を分けます。
ここでは、日ごとの指標を簡潔に整理していきます。
トレードする通貨が含まれている日には、特に注目をしましょう。
9/15(月)発表の主な指標 ― 小売売上高・鉱工業生産指数・ニューヨーク連銀製造業景気指数など
週明け早々、中国の小売売上高と鉱工業生産指数が発表されます。
この2つは中国景気の「実需」と「製造面」の動向を示すため、豪ドルやNZドル、そして原油市場にも波及しやすい印象です。
また、21:30には米国のニューヨーク連銀製造業景気指数も予定されています。
景気感応度の高い指標のため、サプライズには注意が必要です。
私自身、月曜はあまり大きなポジションを持たないようにしていますが、中国指標の結果によってはアジア時間で意外と動くこともあるため、朝イチのチェックは欠かせません。
9/16(火) ― ILO失業率/失業率/失業保険申請件数、ZEW景況感指数、ユーロ圏関連、生産・設備稼働率など
火曜日は1日中、指標ラッシュです。
欧州ではILO失業率やZEW景況感指数、そしてユーロ圏の鉱工業生産指数が並び、ユーロ関連通貨ペアが特に注目されます。
そして、米国では小売売上高、CPI、鉱工業生産指数、設備稼働率などインフレと消費の両方に関わるビッグ指標が連発します。

この指標で私はポジションを縮める。
失業率やCPIの結果がブレやすいこともあり、こうした日は事前にポジションを軽くして、発表後に方向を確認してから入るようにしています。
特にCPIは、FRBの政策判断に直結するため要注意です。
9/17(水)以降の政策金利とCPI ― FRB政策金利・消費者物価指数(CPI)、英中銀政策金利など
週後半は政策金利ウィーク。
まず水曜深夜にはFRB(米連邦準備制度)の金利発表と声明があり、市場はそのトーンに神経を尖らせています。
特に「年内に追加利下げはあるのか?」という点が焦点になりそうです。

🔍 今週の目玉
FRBの金利据え置きが予想されているものの、インフレの粘着性を示す発言が出れば、ドル高トレンドが再燃するリスクも。
声明文の中の「一言」で市場が大きく動く場面が過去にもありました。
木曜の英中銀(BOE)、金曜の日本銀行の政策金利発表も重要です。
最近は特に、発表よりもそのあとの総裁会見や声明文のニュアンスに注目が集まっています。
先月の数値からの振り返りと比較分析
先週の指標も大事ですが、今週のトレード戦略を組み立てるには「先月の結果」をしっかり振り返ることが欠かせません。
「先月が強かったのか弱かったのか?」それによって、今回のマーケットの反応は大きく変わるからです。
私自身、数年前の失敗で「前回の内容を見ずにポジションを取ってしまい痛い目を見た」ことがあり、それ以来は必ず直近のデータを確認しています。
ここでは、小売売上高・失業率・CPIなどを中心に、前回との比較や、市場がどう反応してきたかを見ていきます。
先月の小売売上高・鉱工業生産の動き ― トレンドと先行きのヒント
先月の米国小売売上高は「堅調」だった一方で、鉱工業生産はやや鈍化していた印象です。
このように、消費が伸びても生産活動に波があると、景気全体の力強さに疑問符がつく場面がありました。
以前、小売売上高の発表で「予想よりかなり悪い数字」が出たことがありました。
そのとき、私はロングポジションを持っていて、マーケットが一気に逆方向に動き、大きく削られた苦い経験があります。
今週も、数字の強弱に過剰反応する可能性を想定してポジションを管理する予定です。
失業率・失業保険申請件数の先月比 ― 労働市場の「強さ/弱さ」
労働市場の数字は「インフレ抑制」や「利下げの根拠」に直結するため、注目度は常に高いです。
先月は失業率が若干上昇傾向だったことで、FRBのトーンもやや慎重になった印象がありました。
個人的には、失業率が上がったとしても「労働参加率の上昇によるものか」を見極めたいところです。
この点を見誤ると、市場の反応も大きく変わるため、慎重に数字の背景を分析したいと思っています。
物価(CPIなど)・設備稼働率などインフレとキャパシティの状況
インフレ関連指標は、先月の結果もかなり「強め」でした。
特にコアCPIがしぶとく高止まりしていたため、FRBの政策見通しにもブレーキがかかっていました。

⚠️ ここが落とし穴かもしれない!?
市場は「そろそろインフレは落ち着くだろう」と見ているかもしれませんが、予想以上にCPIが強かった場合はドル高が再加速する可能性もあります。
安易な「織り込み済み」は危険です。
設備稼働率についても、80%を超える水準が維持されているかどうかがポイント。
リソースがフル稼働に近づくと、インフレ圧力が再び強まりやすくなります。
今週は大きい指標が目白押し、各通貨どう推移するか?
今週のように重要指標が集中している時、最も注目すべきは「各通貨ペアがどう反応するか」です。
米ドル、ユーロ、円、そして英ポンドまで、政策金利や物価データの発表に対する感応度が高くなることが予想されます。
実際、こうした週では、指標発表の前に仕掛けるか、発表後に追いかけるかの判断が重要になります。
どちらを選ぶかでリスクの取り方が大きく変わるため、自分のスタイルに合わせた戦略が求められます。
ここでは、主要通貨の見通しをそれぞれ整理しつつ、私が特に注目している通貨ペアも紹介します。
ドル円・ユーロドルなど主要通貨ペアの反応見込み
今週はFRBの政策金利発表とCPIが控えているため、ドルを中心に主要通貨ペアは荒れやすい週になると見ています。
特にドル円は、米金利に対する市場の反応が強く出やすく、日銀の政策金利も重なることで方向感が出にくい=フェイクブレイクに注意です。
ユーロドルはユーロ圏の景況感指標とCPIに対して、やや鈍感になってきた印象ですが、米側の動きに引っ張られやすい状況は続きそうです。
私は今週のドル円は、あえて「値幅取り」ではなく、「方向を見てから参加」を意識しています。
ユーロ圏・英国など政策金利発表を控えたリスクと機会
英中銀(BOE)の金利決定は、今回も「据え置きか、最後の利上げか」の分岐点として注目されています。
市場は既に「利下げへの地ならし」と見ていますが、サプライズが起きやすいタイミングでもあります。
ユーロ圏については政策金利よりもZEWや鉱工業生産など“マクロデータ”のほうが影響を持つ場面が増えています。
そのため、ユーロは「一時的な上下」よりもじわじわとした中期のトレンド形成に向かう可能性がありそうです。
BOEに関しては、以前「据え置きでも声明がタカ派」だったことでポンドが急上昇した経験があるため、文言とトーンにも警戒しています。
新興国通貨や商品通貨への影響
指標発表が先進国中心でも、実は新興国通貨や資源国通貨(豪ドル、NZドル、カナダドルなど)への波及も無視できません。
たとえば、中国の小売・生産データは豪ドルに直結しやすいですし、米国のCPIやFRBのスタンスが変われば、新興国からの資金流出/流入に直結します。
私の感覚ですが、こうした通貨は「急激な資金の流れ」によって“つられ下げ/上げ”が発生することがあるため、トレードする際はレバレッジを控えめにします。
また、原油や金属価格にも影響が出る週なので、コモディティ通貨を扱う人はWチェックを忘れずに。
今週のポジション取りの注意点と戦略
多くのトレーダーが悩むのが「この状況でどうポジションを取ればいいのか?」という点。
特に今週のようにCPIや政策金利といった相場の転換点となりやすい指標が続く週は、リスク管理の重要性が一気に高まります。
私も過去に、FRBのサプライズ発表で完全に逆を突かれたことがあり、以来「指標前のポジションは軽く・早めに利確」を基本とするようになりました。
ここでは、ポジション構築・調整の際に気をつけるべきポイントを、相場の特徴とあわせて紹介します。
政策金利発表前後のポジション調整のタイミング
政策金利の発表タイミングでは、直前にポジションを持っているか、発表後にエントリーするかで大きな差が出ることがあります。
私自身のルールでは、「発表前は小ロット or ノーポジ。発表後の動きを見てから入る」を基本にしています。
サプライズ時の急変動に巻き込まれると、リスクだけでなく心の乱れも生じやすいですから。
特に今週のFRBや英中銀は、発表内容よりも声明文や会見のトーンが注目されており、“2段階での動き”になる可能性もあります。
CPI・買い物売上(小売売上高)に対するマーケットの期待とのギャップに注意
米国のCPIと小売売上高は、「すでに織り込まれている」という空気が出やすい指標ですが、結果が予想を上回ると市場の反応は極端になります。
特にCPIは、コアや住居費など細かい構成要素にも注目されるため、「ヘッドラインは良くても詳細で売られる」といった場面も。
かつてCPIが予想よりわずかに強く出た場面で、想定以上にドルが急伸して驚いた経験がありました。
それ以来、こうした“期待と現実のズレ”に敏感になりました。
リスク管理 ― ボラティリティが高まりやすい指標発表時のストップロス/ヘッジ戦略
今週のようにビッグイベントが集中しているときほど、ストップロスの設定とヘッジ戦略は必須です。
特に「一瞬で大きく動く指標」の前には、指標後のリバウンドも含めたストーリーを描いておく必要があります。
私がよくやるのは、事前にチャートの「一番荒れそうなレンジ」を見積もって、そこを超えたら自動撤退する設定をすること。
また、複数通貨で逆相関ポジションを組んでおくことで、一方向に飛ばされた時のダメージを和らげるという工夫もしています。
私見をシンプルにお伝えします
最後に、今週の展望を私なりの視点でまとめておきたいと思います。
マーケット全体を見渡してみると、今週は「政策金利・物価動向・労働市場」の3つがキーワードになりそうです。
個人的には、FRBと英中銀の金利判断が最も影響力を持つと考えており、その発表次第でドル円・ポンド円は一段と動く可能性があります。
ここでは、いくつかの「もしこうなったら」というシナリオ別の相場反応も含め、今後のトレードに活かせる視点をお伝えします。
私が注目している指標とその理由
今週、個人的に最も注目しているのはFRB政策金利とその声明文です。
利上げは行われないとの見方が大勢ですが、「あと何回利下げがあり得るのか?」という点に焦点が移っています。
パウエル議長の発言がハト派すぎると株高・ドル安、タカ派的だとドル高が加速しやすいです。
また、米小売売上高も気になっています。
消費動向が弱含めば、「利下げ近し」と見られる可能性も。
自分の中では、これらの指標が2025年末の市場全体のセンチメントに影響する起点になると感じています。
もしこうなったらこう動く(シナリオ分析)
こうした指標ラッシュの週は、「予想が外れたときの反応」を先に考えておくことが重要です。
たとえば:
- CPIが強く出たら
→ ドル買い、株売り、長期金利上昇の流れ。 - 英中銀が予想外の利上げ
→ ポンド急伸、ユーロポンド急落。 - FRBがタカ派姿勢維持
→ ドル円が145〜146を試す可能性。
私は毎回、ベースシナリオ/強気シナリオ/弱気シナリオの3つを書き出して、感情に振り回されないように準備します。
「どう動くか分からない」ではなく、「こうなったらこう動く」を事前に整理しておくことで、落ち着いた判断ができるようになります。
今後数週間へのインプリケーション
今週の指標結果は、「ただの1週間のデータ」ではなく、今後の金融政策の道筋を照らすシグナルになります。
特にFRBやBOEが利下げ方向に傾きつつあるなか、今回のCPIや雇用統計の結果が強い場合、マーケットは再び「利下げは遠のいた」と織り込む可能性があります。
私としては、今週の動きが「年内のトレンド変化点」になる可能性もあると見ており、短期の値動きだけでなく、数週間〜数ヶ月先を見据えた戦略構築を意識しています。
初心者も安心!2025年9月第3週の経済指標FAQ
経済指標が多い週は、特に「どの指標を見ればいいの?」「発表前後はどう動けば?」など、疑問や不安を持つ方が多いです。
ここでは、今週のようなビッグイベントが集中する相場でよく寄せられる質問に、できるだけ分かりやすく答えていきます。
「指標そのものよりも、その“意味合い”をどう読むか?」という視点で、初心者にも経験者にも役立つ内容にまとめました。
Q1:米国とユーロ圏のZEW景況感指数は何を示す指標ですか?
A:ZEWとは「欧州の機関投資家の景況感調査」の略で、経済の先行き期待を数値化したもの。企業投資や資産運用の見通しに敏感なため、発表後は金融市場(特にユーロ圏の債・株・為替)で反応が出やすいです。
Q2:ILO失業率と公式失業率の違いは何でしょう?
A:ILO失業率は国際労働機関の基準で失業を算出するもので、失業者の定義・調査の方法が異なります。
公式失業率と比べて若干違った労働市場の実態が見えることがあります。
Q3:政策金利発表で声明文が重要な理由は何ですか?
A:金利そのもの以外に、中央銀行の未来見通し(インフレの見方、景気見通し、利下げ/利上げの可能性など)が声明文に込められています。
それがマーケットへ「サプライズ」を与えることが多いため、投資家は文言を細かくチェックします。
Q4:鉱工業生産指数の上昇/下降は為替にどう影響するか?
A:生産指数が上昇すればその国の製造業が活発という見方となり、通貨が買われやすくなります。
逆に低調だと輸出見通しや国内需要の弱さを警戒され、通貨安圧力になることがあります。
Q5:設備稼働率とは何で、どのような意味がありますか?
A:設備稼働率は稼働可能な設備に対し、どれだけ使われているかを示す指標。
高い設備稼働率は資源の逼迫やインフレ圧力を示す可能性がある一方、余力があれば成長余地があるという見方もできます。
Q6:日銀政策金利発表前には何を注目すべきか?
A:金融政策だけでなく、為替・物価・経済成長の見通し発表、また総裁の会見があればその内容。
加えて、他国の政策金利との比較で円の位置付けが変わることがあります。
Q7:マーケット予想と実際の数値が乖離したときに起きることは?
A:乖離が大きければ、価格が一気に跳ねたり、逆に大きな反落が起きたりします。
サプライズ(予想を上回るか下回るか)によって市場心理が揺れ、ボラティリティが拡大することが多いです。
Q8:先月のCPI・小売売上高の動向は今週の予想にどの程度影響するか?
A:過去のデータは市場予想のベースになるため大きな影響があります。
もし先月が予想外に強かった/弱かったために市場が「織り込んでいる」可能性があるので、それを覆すような今週のデータは特に注目です。
Q9:為替トレーダーが「指標発表前後」に避けるべき行動は?
A:過度なレバレッジ、ポジションサイズの過大、ストップロスを設定していないことなどが危険。
指標直前にポジションを取るのはリスク高いため、建てていても一部を手仕舞うなどの調整が有効です。
Q10:指標が予想通りであれば「無風」かというと…?
A:いいえ。
市場は「予想とのギャップ」だけでなく、将来見通しのヒントを探しています。
影響は限定的になることもありますが、文脈(政策や他指標との兼ね合い)によっては振れ幅が出ることがあります。
2025年9月第3週の経済指標まとめと今後のポイント
- 9/15~9/19 は「今週は大きい指標が目白押し」であり、小売売上高、鉱工業生産、CPI、政策金利など発表が集中する。
- 先月の数値(小売・失業率・物価)を振り返ることで、今週の予想の土台が見える。
- 各通貨・為替ペアは政策金利発表やCPI等で大きく動く可能性あり、特にドル・ユーロ・円。
- ポジション取りには慎重さが必要:発表前後の動き、ストップロス/ヘッジ、過剰レバレッジを避ける。
- 自分としては、政策金利とCPIの発表を重視し、それらの結果次第でポジションのリスクを縮小または転換する可能性が高い。
2025年9月15日〜19日の1週間は、CPI、政策金利、小売売上高など相場を大きく揺らす指標が連発する“勝負週”です。
特にドル円やポンド円など、金利や物価に敏感な通貨ペアは、わずかな文言の違いや結果のズレで急変動が起きやすい環境にあります。
私自身、こういう週は「予測よりも反応」、「期待よりも現実」を重視してトレードするよう心がけています。
ポジションを取るのではなく、「動きが出てから乗る」柔軟さも必要でしょう。
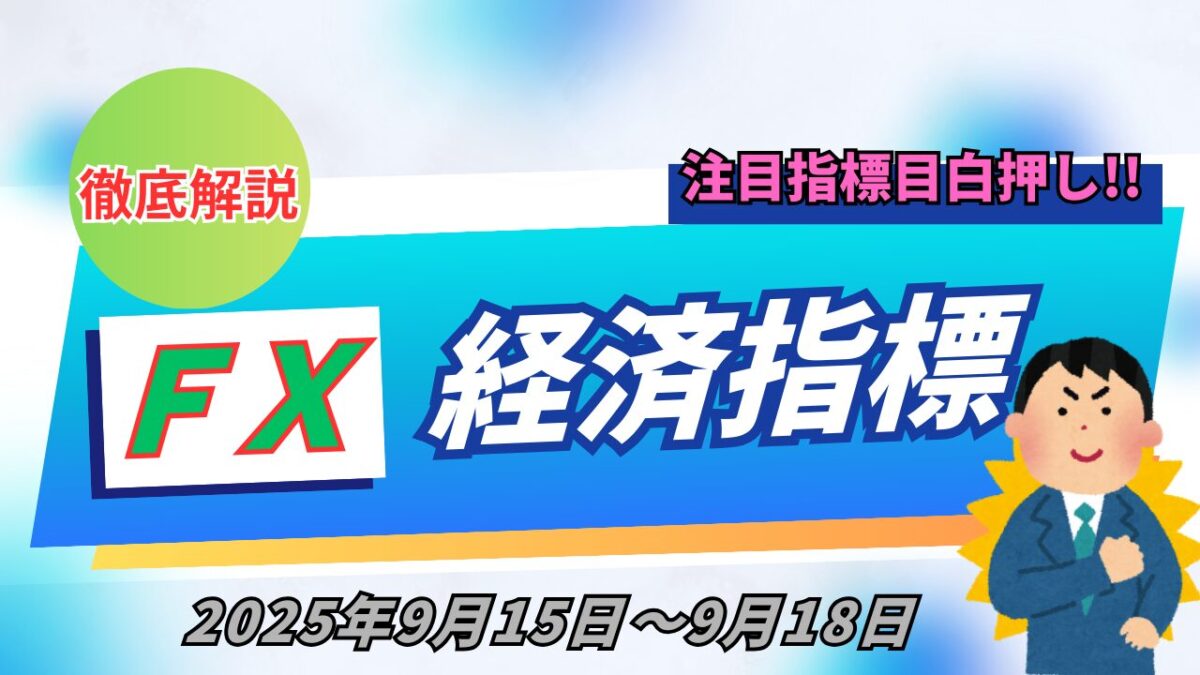




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン