2025年9月第4週(9月22日〜26日)は、主要国で星3つ以上の高インパクト経済指標が集中する注目の一週間です。
米国ではPCE価格指数や耐久財受注、欧州ではIFO景況感指数やPMI、日本や中国でも政策や物価に関連する重要データが発表予定となっており、市場の変動要因が複数重なっています。
特に今週は、「前回の結果が市場に与えた影響」を念頭に置いたうえで、今回の指標数値がどのような市場反応を引き起こすかを事前にイメージすることが重要だと感じています。
この記事では、これら星3つ以上の経済指標に特化し、スケジュール・注目ポイント・市場の見通しを整理します。
実際に私が過去の相場で注目してきた経験や、各国の金融政策との関連も交えながら、2025年9月第4週の経済イベントを多角的に解説していきます。
9月第4週の星3つ以上の重要経済指標:発表スケジュール
2025年9月第4週は、各国から発表される経済指標の中でも「市場にインパクトを与える可能性が高い星3つ以上」のデータが連日続く、極めて注目度の高い一週間です。
ここでは、曜日ごとのスケジュールを整理しながら、それぞれの指標がなぜ重要視されているのか、どの時間帯に市場が動きやすいのかといった視点でチェックしていきます。
月曜の注目:中国最優遇貸出金利発表の意味
中国の「最優遇貸出金利」は、銀行が企業などに貸し出す際の優遇金利のことで、金融政策のスタンスを反映する有力な指標です。
前回、この指標が発表された際には、市場参加者が予想外の利下げ方向性を示したと解釈して中国株・人民元が反応した記憶があります。
今回も、中国政府が景気刺激をどこまで図るかのシグナルとして注目されます。
前回の発表から見て、今回も政策サポートを強めたいという意図があるならば、この貸出金利が据え置きまたはわずかな引き下げとなる可能性が高いと考えています。
他方、もし予想以上に引き上げられたり引き締め色が強い解釈をされると、内需関連株や不動産セクターにネガティブな影響が出るでしょう。
私見ですが、中国政府は国際的な供給網や輸出の環境が厳しくなってきている中で、国内景気を支えるための政策緩和的な対応を優先する可能性が高いとみています。
したがって、この指標は「据え置きか引下げ予想」が短期的には市場が望むシナリオだと思います。

“据え置き=安心材料”って思っている投資家、多そうです。
火曜:PMI(製造業・サービス業・コンポジット)と経常収支が市場にもたらす変動リスク
火曜に発表される製造業PMI、サービス業PMI、コンポジットPMIという購買担当者指数群は、景気の牽引セクターである製造とサービス業の現状と先行きがどう見られているかを示すため、市場にとって非常に感度が高い指標です。
また、同日に発表される経常収支も外需・通貨フローに直結するため、為替市場などで波紋を呼ぶことがあります。
前回のPMI発表では、製造業の部分が予想を上回った/下回った(実際のデータによって変化しますが)ことで、株式市場の景気敏感セクター・輸出関連株に先行して影響が出ました。
今回も同様に、特に製造業PMIの上振れがあれば、ドル/通貨ヘッジを行っている企業やサプライチェーンが利益を見込める可能性があります。
一方で、サービス業が弱含むと消費関連や内需型株がネガティブに反応するでしょう。
私自身の見方では、現状のグローバルな物流コスト・人手不足などのボトルネック要因が少なくとも部分的には改善されてきており、製造業PMIは前回よりもわずかに良い数字が出る可能性があると期待しています。
ただしサービス業はコスト圧力が残るため、上振れは限定的かもしれません。
水曜〜金曜:IFO景況感指数/新築住宅/GDP/耐久財受注/PCE価格指数など指標ラッシュ
水曜以降には、IFO景況感指数、新築住宅販売件数など住宅セクター、木曜のGDP・耐久財受注、中古住宅販売、そして金曜のPCE価格指数とコアPCE価格指数といった、金融政策・消費・物価圧力の核心を突く指標が立て続けに発表されます。
これらは相互に関連性が強く、一つの指標が予想と異なれば他に波及する連鎖反応が起きる可能性が高いので、特に注意が必要です。
前回のIFO景況感指数では、企業の期待感が弱くなった点が注目され、それがユーロ/株式市場に不安感を呼びました。
今度の発表で期待部分が予想を上回るか、あるいは現状判断が改善するかどうかが見どころです。
PCE価格指数については、米国でのインフレの持続性を測る上で最も重視される指標であり、政策金利を運営する FRB のスタンスに直結します。
私見としては、この期間にサプライズが起きる可能性が最も高いのは PCE価格指数と、IFO景況感指数だと思っています。
特に PCE が予想よりもインフレ寄りであれば、市場は金利上昇の可能性を織り込む方向へ動くでしょう。
一方で新築/中古住宅販売が弱めであれば、住宅関連セクターや建材・資材コストが利回りや住宅ローンコストで影響を受けやすくなると感じます。
前回の結果から見た今回の指標予想と市場反応の焦点
過去の発表データが市場にどう影響を与えたのかを把握することは、今回の相場予測において非常に有効です。
ここでは、特に前回の発表時に市場がどのように反応したかを振り返りながら、「今回の発表で市場がどこに注目しているのか」「想定外の数値が出た場合、どのような反応が起きそうか」といった点を分析していきます。
私自身も、過去に意外な値動きを見た指標は特に気をつけてモニタリングしています。
前回のPMI・PCE・GDPなどで市場が驚いた/影響を受けた点
前回の発表で特に市場がサプライズと判断したのは、PMI の “予想との乖離” と PCE/GDP の成長トレンドが予想より強かった/弱かったという点です。
例えば、製造業PMIが予想より上振れすると、輸出産業・重工業系株が先行して買われることが多く、逆もまた然りでした。
これまでの経験から、「予想からの乖離」が小さく見えても、雇用・コスト・価格関連指標が同時に強い/弱いことが確認されれば、政策金利見通しが修正されることが多いです。
前回の GDP 発表では、成長率が予想をわずかに上回るかどうかが、FRB/ECB の次の利上げタイミングに影響を与えた記憶があります。
私見ですが、市場は「予想と実際の差異」を単独ではなく複数指標の組み合わせで読み取る傾向があります。
したがって、今回も単に PCE が強くても、耐久財受注・雇用・消費の他データとの整合性が取れるかが重要です。
今回“星3つ以上”の指標で予想レンジ/サプライズ要因になるところ
今回の中でサプライズになりやすい指標として考えているのは製造業PMI、PCE指数、耐久財受注あたりです。
予想レンジは、アナリストコンセンサスで直近の流れを踏まえると、「多少強め」「やや弱め」が混在しており、予想より上振れたら市場に安心感を与える可能性がありますが、逆に下振れだとセンチメントが急速に冷えるリスクがあります。
また、住宅販売系の指標(新築/中古)や経常収支などは、インフラ・消費・貿易環境など複数の要因との関連があり、これらも予想外の動きになったときに注目されるでしょう。
特に金利・為替コスト・建築資材価格など外部コストが最近変わっているので、それらが指標結果に反映されるかどうかが“サプライズ可能性”のカギです。

住宅関連って“後出し感”あるけど意外と効くよね?
私見として、「予想を上回るサプライズ」が起きるシナリオとしては、製造業PMIが予想より強く出る+住宅販売が回復基調を示すという組み合わせです。
逆にサプライズがネガティブな方向なら、内需・消費関連株・住宅株での調整が早く起こると見ます。
私見:どの指標でサプライズが起きやすいか、どの市場セクターが敏感か
私が注目している指標は、PCE価格指数および製造業PMIです。
特に PCE は FRB のインフレ判断に直結するため、その結果が予想を上回るかどうかで金利先高感が強まる可能性があるからです。
製造業PMIについては、現在のグローバルなサプライチェーンや輸出環境が幾分改善してきており、その改善が数字として現れる可能性が高いと思っています。
セクターで敏感に反応するのは、輸出関連株(機械、自動車、電子部品等)、住宅建設・不動産セクター、および金融セクターです。
利回り上昇が起きれば銀行株が恩恵を受ける可能性がありますし、為替でドル/ユーロ/人民元の動きが大きいと輸出型企業の競争力に影響します。
また、リスク管理の観点から、予想に対する強いサプライズが起きた場合、ポジション調整を素早くすることを考えています。
過去、強めに出たPMIで翌日急反発があったことなどを経験していますので、そのような動きを警戒しています。
米国・欧州・アジアの政策・市場へのインプリケーション
経済指標の影響は一過性の値動きだけにとどまりません。
特に星3つ以上の指標は、各国の金融政策判断やマーケットセンチメントの転換点にもなり得るため、発表内容が中央銀行や投資家にどのように解釈されるかが重要です。
ここでは、米国・欧州・アジアそれぞれの地域別に、今週の指標が政策金利見通し、為替動向、株式・債券市場にどのような形で影響を及ぼし得るのかを読み解いていきます。
私自身もトレード戦略を立てるうえで、各国のスタンスの違いを意識しています。
米国:PCE指数/耐久財受注/中古住宅販売などから読み取れる利上げ・金利見通し
米国については、PCE価格指数およびコアPCEがインフレの基調を示す最重要指標であるのは言うまでもありません。
耐久財受注と中古住宅販売は、設備投資および消費者の購買意欲・住宅ローン金利の影響を間接的に浮き彫りにします。
前回の PCE では物価上昇圧力がある程度示されたため、FRB が金利をどう見せるか、市場がどのように織り込むかが焦点になります。
もし PCE の結果がインフレ加速を示唆するものなら、長期金利の上昇、ドル高、株式では成長株よりもバリュー株寄りの動きが出る可能性があります。

住宅関連が崩れると、意外と小売・家電・資材にも波及します。
耐久財受注/中古住宅販売が弱めなら、消費サイクルや住宅景気が停滞しているとの懸念が強まり、景気敏感セクターにリスクが出てくるでしょう。
私見としては、今回の PCE は前回よりもインフレの伸びが鈍化する方向が市場には期待されていて、もしこの期待が裏切られると大きな調整が来ると思っています。
逆に、耐久財/住宅の指標がポジティブサプライズなら「景気の底打ち」が意識され、リスクオンの動きが強まる場面がありそうです。
欧州:IFO景況感・サービス業/製造業PMIがECBスタンスやユーロ為替に与える影響
欧州では、IFO景況感指数・製造業・サービス業PMIは政策当局の期待・不安を反映する指標です。
IFOはドイツ企業の先行き期待・現況判断をまとめたもので、ユーロ圏全体の景況感先行指標として重みがあります。
製造業・サービス業PMIが芳しくあれば、ECB が利上げスタンスを維持または引き締め基調を示す根拠になる可能性が高いです。
また、ユーロが対ドル・他通貨でどう動くかは、これら指標に市場がどう反応するか次第になります。
予想よりも強い指標ならユーロ買い・金利差拡大期待になり、弱いならユーロ下落や安全資産回帰の動きが起きやすくなります。
私見として、IFO 景況感については、市場の織り込み水準を超える形での、“期待の裏切り”が最も市場を動かすシナリオだと思っています。
とりわけ“企業の将来見通し”部分が悪化していたら、ユーロ圏内の景況感回復期待が後退し、ユーロ及び欧州株に売り圧がかかる可能性があります。
/中国・スイス・日本などアジア・小国:貸出金利・中央銀行政策金利と国内景況感
中国の最優遇貸出金利やスイスの政策金利発表は、それぞれその国の金融政策の方向性をあらわすだけでなく、資本フロー・為替市場に即時的な反応を引き起こすことがあります。
日本についても、物価・輸入コスト・消費者マインドの動きが、日銀スタンスや企業収益に直結するので、これらが“期待”をどこまで上回るか/下回るかが重要です。
前回の政策金利発表で緩和姿勢が示された国では、今週の発表を「変更あり/追加措置あり」のサインと捉えるトレーダーが多いはずです。
スイス中銀の動きが予想よりタカ派/ハト派であれば、スイスフランだけでなく周辺国通貨にも波及する可能性があります。
私見としては、アジア圏では中国の貸出金利が今週最も注目される指標だとみています。
理由は、政策余地のある部分が他国よりも比較的大きく、中国政府が成長維持を重視しており、市場にもその意図を見せたいという意図があるのではないかと考えています。
2025年9月第4週の経済指標に関するよくある質問とその答え
経済指標をチェックする中で、「これはどういう意味?」「なぜ市場に影響するの?」と感じたことはないでしょうか。
ここでは、本文では触れきれなかった基礎的だけれど意外と重要な疑問点について、簡潔かつ実践的に解説します。
特に、PMIやPCE、IFO景況感指数などの専門用語、政策金利との関係性、指標の読み方といった部分は、投資経験にかかわらず共通して気になるポイントだと思います。
私自身も投資を始めた当初は、指標の意味や市場への影響がよく分からず、戸惑った経験があります。
「これから本格的に指標分析を始めたい」「今週の動きをしっかり押さえておきたい」という方に向けて、ぜひ参考にしていただければと思います。
Q1: PMI(製造業・サービス業・コンポジット)って何が違うの?
A:製造業PMIはモノづくり業界の活動を、サービス業PMIはサービス業の活動を、コンポジットPMIは両者を合成した総合指標です。
製造業が強いのにサービスが弱いなら景気の構造的な偏りがあることを示唆する。
Q2:“最優遇貸出金利”とは何か?なぜ注目されるのか?
A:中国などで銀行が特定企業や業界に対して有利な貸出条件を提供する金利。
これが変わると政策の方向性(景気刺激か抑制か)や銀行貸出の増減が示されるので、国内経済に影響。
Q3:経常収支の発表が為替に与える影響は?
A:経常収支が黒字であればその国の通貨への外需の支えが強いと市場は捉えることが多く、為替が強まる可能性がある。
逆に赤字なら弱含む要因になる。
Q4:IFO景況感指数ってどのように計算されるの?
A:ドイツIFO研究所が企業調査を行い、企業の現在状況・将来期待などを数字にまとめたもの。
ドイツ国内だけでなく、欧州経済やサプライチェーンの状況を示す指標として注目される。
Q5:耐久財受注が景気判断で重要な理由は?
A: 耐久財は製造業の投資や大きな設備投資が多いため、企業が将来を見込んで購入しているということ。
受注が増えれば景気が先行的に良くなる可能性がある。
Q6:PCE価格指数とコアPCE価格指数はどう違うのか?
A:PCE価格指数は消費者が購入するモノ・サービス全体の価格変動を示す。
コアPCEは食料とエネルギー価格を除いたもので、変動が激しい部分を除いてインフレの基調を見やすくする。
Q7:中古住宅販売と新築住宅販売、どちらが住宅市場の変動をより早く反映する?
A:新築住宅販売は供給側の動きが強く、住宅開発・建築の意欲を反映するので将来のトレンドを先取りしやすい。
中古は既存住宅の取引であるため、現在の需要・条件の影響を受けやすい。
Q8:政策金利発表のタイミングで注意するべきことは?
A:発表内容だけでなく、声明文・見通し・中央銀行の発言(記者会見など)が重要。
特に政策金利据え置きでも「将来の利上げ可能性を否定しない」等の文言があれば市場が動く。
Q9:指標発表で予想が上振れ/下振れしたとき、市場はどのような動きをするか?
A:上振れならリスクオンの動きになることが多く、株高・債券利回り上昇・通貨強化が考えられる。
下振れならその逆。
ただし「サプライズがすでに織り込まれているかどうか」で反応の大きさが変わる。
Q10:“星3つ以上”という重要度はどのように判断されているの?
A:経済カレンダーや市場情報サイトでのインパクト評価。
「High Impact」「Major」「★★★」「★★★★」「★★★★★」などで表示される。
指標の過去の市場反応・政策との関連性・発表国の経済規模などで重要度が決まる。
2025年9月第4週の市場見通しまとめと注目点のおさらい
- 今週は火曜以降、製造業・サービス業・コンポジットPMI、IFO景況感指数、新築住宅・中古住宅販売件数、PCE価格指数など、星3つ以上の指標が続くため、市場の変動リスクが高い。
- 前回の指標で予想を上回った/下回ったもの(例:PMI類、PCEなど)のパターンが今回も参考になる。
特にインフレ関連指標でのサプライズが利益機会にも損失リスクにもなりうる。 - 米国のPCE価格指数/耐久財受注などに注目。
これらが強めに出れば、利上げ観測や債券利回り上昇、ドル高方向に圧力がかかる可能性あり。 - 欧州はIFO景況感指数やPMI関連で景気先行きの信頼感/不安材料のどちらが表面化するかが鍵。
ユーロ圏・ドイツ経済への見方が市場を左右する。 - 中国の貸出金利やスイスの政策金利など、アジアおよびその他地域の金融政策も見逃せない—国内外の金利差が資本流入・為替に影響すると思われる。
9月第4週は、星3つ以上の高インパクト経済指標が集中し、市場にとって試金石のような1週間になるでしょう。
特に火曜のPMIラッシュと金曜のPCE価格指数は、世界的なインフレと金融政策の方向性を占う上で極めて重要です。
前回の指標で予想を下回る/回るパターンを経験してきた私から見て、今回もサプライズの発生の可能性を甘く見ることはできません。
もしPCEや耐久財受注などで強めの数値が出れば、米国ドルおよび金利市場に向けたポジションを早めに調整する価値があります。
一方、欧州や中国での弱めの指標が続けば、リスクオフの動きや安全資産へのシフトが起きる可能性があります。
読者として自分が注目するのは、その「前回の結果とのずれ」がどこで起きるかです。
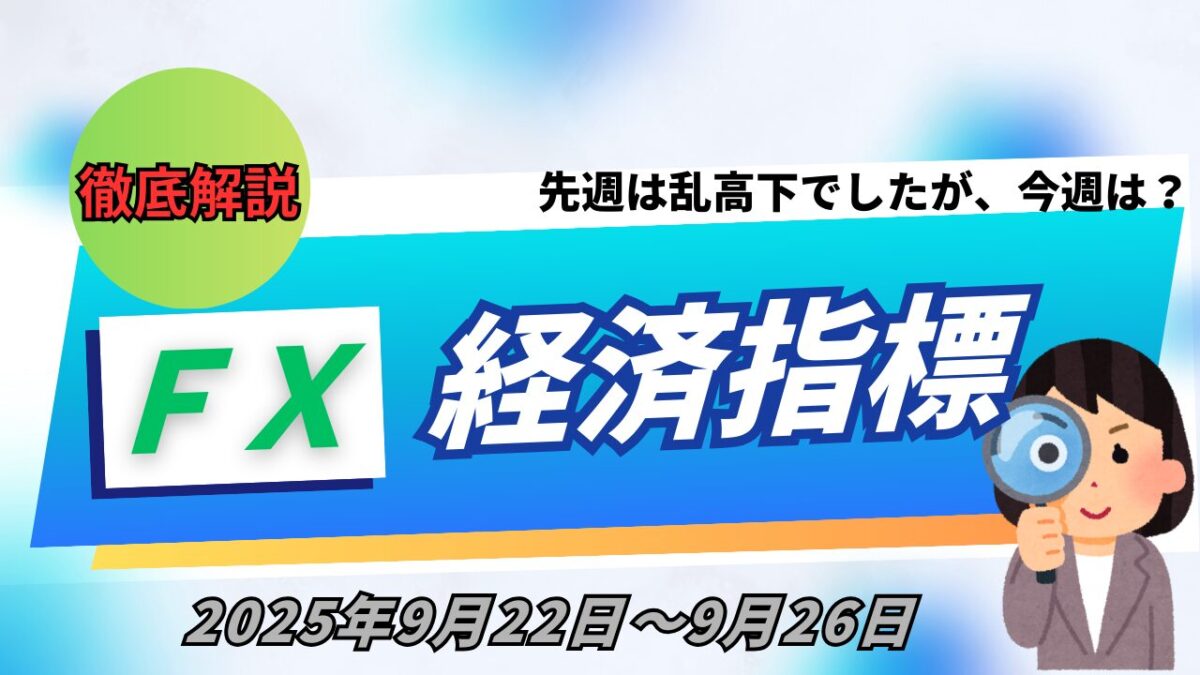




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン

