2025年9月18日(木)の深夜、注目されていたFOMC(米連邦公開市場委員会)の声明が発表されました。
市場の関心は、政策金利の据え置きか、あるいは今後の利下げ開始時期に移っていましたが、今回の内容は一部の予想とは異なる形となり、為替市場、とくにドル円相場に大きなインパクトを与えました。
実際にドル円は発表直後から急上昇し、短時間で約1円近い値動きとなる局面もあり、私自身、逆張りで何度か損切りを余儀なくされるなど、改めてFOMC発表の難しさを痛感させられました。
深夜2時、画面越しに1円幅が秒速で動くのを見て、正直「これは手が付けられない」と冷や汗をかきました。
この記事では、2025年9月FOMCの要点をわかりやすく整理し、ドル円相場への影響をチャートの動きやファンダメンタルズの視点から分析。
また、私自身のトレード経験や戦略も交えて、今後の為替見通しと対応策について考察していきます。
FOMC 2025年9月18日の発表の要点|ついに「利下げ」の扉が開いた
今回のFOMCでは、政策金利の水準に加え、FRBが今後どのような金利スタンスを取っていくかという点に注目が集まりました。
事前には「年内に利下げがあるのでは」という見方もありましたが、実際の声明やドットチャートではどのような方向性が示されたのでしょうか。
ここでは、公式発表の要点を整理し、マーケットの予想とのギャップに焦点を当てていきます。

「噂で買って事実で売る」……そんな相場の格言が頭をよぎるような、期待と不安が入り混じった発表でしたね。
政策金利の決定内容と市場予想との比較
今回のFOMCでは、政策金利が 4.00〜4.25% のレンジに引き下げられました。
これは、2025年内で最初の利下げであり、市場の多くが予想していた通りの動きでした。
市場は直前まで、「利下げは回避されるか据え置きになるか」が議論されており、インフレのしぶとさや労働市場の強さを理由に据え置き説を唱えるアナリストも少なくありませんでした。
しかし、声明の中で「雇用の伸び鈍化」や「インフレ率が依然として高止まりしている」という言及があり、FRBがリスク管理のために慎重ながらも緩和の方向へ舵を切る必要があると判断したことがわかります。
私見としては、この決定は想定内ではありましたが、「利下げ幅」よりも「今後どれだけ継続的に利下げができるか」が鍵になると思っています。
今回の発表では “年内あと1〜2回の利下げ” が見込まれており、市場価格にもそれが織り込まれていたように感じました。
私自身、チャートを見ながら「この利下げでドル円がどこまで下がるか」がポイントだと思っていたので、発表直後の反応を見て少し驚いた部分もありました。
利下げ=ドル安という単純な図式にならないのが、FOMCトレードの本当に恐ろしく、かつ面白いところです。

今回の利下げは、2025年に入ってから初めての動きですね。
利下げサイクル入りの第一歩です!!
利下げ/据え置き/利上げの見通しとFRBメンバーのスタンス
ドットチャート(Summary of Economic Projections:SEP)では、多くのFOMCメンバーが、2025年末にかけてさらに利下げを2回程度見込んでいることが示されました。
この点で、「利下げゼロ」を想定していた市場参加者とのギャップがあり、この見通しがドル円にとっては下押し圧力を生む材料となったようです。
FRB内部にも見方の差があり、インフレ抑制を重視するハト派的なメンバーと、経済や雇用データの弱さを見て早期の緩和を支持するハト傾向の強いメンバーとで意見が分かれているようです。
私自身、過去数回のFOMCで、このような内部の意見差が“声明文のトーン”や“パウエル議長の会見での発言”に微妙に反映され、それが市場の反応を左右してきたと感じています。
今回も、声明以外の会見での発言が今後の利下げ見通しに影響を与えるだろうと考えます。

メンバー内の不一致(ドットの散らばり)を見ると、FRB自身も「手探り状態」なのが透けて見えますね。
ドットチャート(Dot Plot)の最新見通しとインフレ・雇用データとの関係
SEPで示されたドットチャートによれば、2025年末時点での政策金利の中央値予想は約 3.60〜3.75% 程度と見られており、これまでの見通しからやや利下げ幅が限定的であるとの声もあります。
インフレ率(とくにPCEコアインフレ)や雇用統計が今後も上振れする可能性があるため、FRBは慎重さを保ちながらの利下げを想定しているようです。
労働市場のデータでは、雇用の伸びが鈍化しており、失業率もわずかですが上昇傾向にあります。
これが利下げを支持する材料ですが、同時にインフレ率が2%目標を超えて高止まりしていることが、利下げに慎重になる要因です。
私の場合、直近の雇用データを見て「これならもう少し利下げを見込んでいた」部分がありましたが、声明文の見方やドットチャートの予想を見ると、FRBもそのあたりを折り込んでいたようです。

「景気後退はさせない、でもインフレも許さない」という、針の穴を通すような舵取りが求められています。
ドル円相場の反応分析|乱高下の嵐を振り返る
FOMCの発表を受けて、為替市場は大きく反応しました。
特にドル円は、政策金利やドットチャートの内容に連動する形で、上下に大きな値幅を伴う動きが見られました。
私自身、発表直後の値動きに対応しきれず、一部ポジションを損切りする場面もあり、改めてボラティリティの高さを実感しています。
ここでは、ドル円のチャート反応を具体的に振り返りながら、その背景にある市場心理や金利差の影響を分析していきます。

あの瞬間の5分足チャートは、まさに「ナイアガラ」の後の「ロケット」のような、心臓に悪い動きでした。
発表直後のドル円の値動きとチャートポイント(サポート・レジスタンスを含む)
FOMC発表直後、ドル円は急下降し、発表前にサポートとして意識されていた146.20付近を明確に下抜ける動きが見られました。
この割り込みによって一時的に売りが加速しましたが、その後はショートカバーや押し目買いが入り、反発する展開となりました。
私もこの辺りで“逆張りロング”を試みましたが、勢いに押されて損切りを余儀なくされた経験があります。
その後、ドル円は148円台中盤まで上昇し、その過程で重要なサポートライン(直近安値や50時間移動平均線など)をテストしました。
テクニカル的には、148.00付近が心理的節目/サポート転換の可能性があるポイントだったと感じています。
もしここを割るような動きが出れば、短期的な調整局面が来るかもしれません。

サポートラインが「一瞬でレジスタンスに変わる」恐怖。
FOMC発表時はテクニカルが紙屑になることもあります。
金利差(日米金利差)が為替に与える影響
今回のFOMCで米国の政策金利が引き下げられたとはいえ、依然として日本との金利差は大きく残っています。
日本は長年低金利政策が続いており、金利差拡大がドル買い/円売りを支える要因になりやすい環境にあります。
過去にも何度か経験しましたが、私のトレード経験でも、「金利差が拡大しているとき」にドル円の上げが強くなりやすく、少しの悪材料でも押し戻されにくい場面がありました。
今回も同様に、利下げを受けたにもかかわらず、ドル円がけっして急落しなかったのは、日米金利差が一定のサポートとなっていたからだと考えています。

日米金利差が“下値の支え”になっているわけですね。
これがある限り、ドル円が下がりづらいのも納得です。
市場心理と投資家センチメントの変化(リスク回避 vs リスクオン)
FOMCの発表を受けて、市場のセンチメント(投資家心理)は「リスク回避」から「リスクオン」へと一時的に傾いたように見えました。
特に利下げが明確に示されたことで、「景気減速懸念はあるが、FRBはソフトランディングを狙っている」という安心感が出たのでしょう。
その結果、株式市場は上昇、米国債利回りはやや低下、ドルは一時買われたものの、全体としては「落ち着いた反応」に留まりました。
私自身、こうした“安心感による買い”は一過性で終わるケースが多いと感じているため、あまり過信せず、むしろ急激な反転リスクに備えるようにしています。
例えば、今回のようなFOMC後のタイミングでは、「リスクオン相場かどうか」はドル円の方向性を見極める重要なポイントになります。
地政学リスクや突発的な経済指標にも注意が必要です。

「楽観」が広まった時こそ、大口が売りを浴びせてくる……そんな警戒感を常に持つようにしています。
経済指標・FRB発言から見る中長期の影響
短期的な値動きとは別に、中長期で見た場合、FOMCで示された見通しは今後のドル円相場にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
インフレ率や雇用統計、PCEコアなどの経済指標と、FRB関係者の発言トーンを照らし合わせながら、マーケットが何を織り込もうとしているのかを整理します。
私自身、これまでの経験から「発表内容そのもの」よりも「その後のデータや発言の積み重ね」が為替の流れを決めていくと感じています。
インフレ率、雇用統計、PCEコアなどの主要指標とのリンク
FOMCの方針は、基本的にインフレと雇用の2軸に支えられています。
今回の会合では、PCEコアインフレが依然として高水準で推移していることが懸念材料とされつつも、雇用の鈍化が利下げの根拠として強調されていました。
とくに「PCEコア」はFRBがもっとも重視しているインフレ指標で、ここが2%に向かって安定的に下がらない限り、積極的な利下げは難しいと考えられます。
私自身、雇用統計やPCEをもとに相場の方向性を考えるスタンスを取っていますが、今回は「インフレが粘着的なので、すぐの大幅利下げはないだろう」と警戒していました。
市場全体もこのあたりを慎重に見ている印象でした。

結局、私たちは「パウエル議長のカンペ」の続きを、日々の指標から読み解くしかないんですよね。
今後の利下げ/利上げ見通しとその可能性(年内・来年以降)
現時点では、2025年中にあと1回〜2回の利下げが見込まれている状況です。
ただし、その前提には「インフレが確実に沈静化している」ことと、「景気の悪化が明確でないこと」が必要です。
ドットチャートを見る限り、FRB内でも慎重派とハト派の間で意見が割れており、来年以降の政策方針はデータ次第で大きく変動する余地があります。
私は、「市場が“利下げを織り込みすぎた”ときこそ危ない」と感じており、今回のように発表直後に買われても、後から反動が来るケースを何度も見てきました。
むしろ、見通しが不透明なときほど、トレンド転換のヒントをチャートやセンチメントから探ることが重要です。
投資家として気を付けるべきリスク要因(景気後退可能性、財政政策、地政学リスク等)
金利政策だけでは相場は語れません。投資家が見逃してはならないのが「その他のマクロ要因」です。
たとえばアメリカ経済が予想以上に早く減速する場合、景気後退入りが現実味を帯び、ドル売り材料となる可能性があります。
また、財政赤字の拡大や米中摩擦、地政学リスク(中東・台湾問題など)も無視できません。
過去にも、FRBが利下げを進めている最中に突発的な悪材料が出て、相場が大きく逆方向に動いたことがあります。
私はいつも「ファンダメンタルズは大局を動かすが、テクニカルは短期判断の基準」と考えています。
FOMC後の相場はとにかく不安定なので、ニュースや指標発表のスケジュールも含め、広い視点で相場を見ることが重要です。

大きな方向性はファンダで見て、細かいタイミングはテクニカル。
これが一番しっくりきます。
私見とトレード戦略|痛い損切りから学んだこと
今回のFOMCを受けた値動きの中で、私がどのような判断をしてどのような結果になったのか、リアルなトレードの記録をもとに振り返ります。
また、今後のドル円の戦略について、自分なりの見通しとエントリーポイント、リスク管理の考え方をまとめていきます。
FOMCは毎回マーケットに強い影響を与えますが、冷静な分析と柔軟な対応力が求められると改めて感じさせられました。

「自分の予想」に固執した瞬間に、相場は牙を剥いてくる。
そんな当たり前の怖さを再認識した夜でした。
私のポジション経験と損切り/利確の判断ポイント
今回のFOMCでは、私自身もエントリーと損切りを繰り返す展開となりました。
発表前は静かな値動きが続いていましたが、発表直後には急激な下落があり、この下落はショートでしっかりと取ることができました。
しかし、その後の145.50付近から147付近までの急反発に対しては、逆張りのショートで狙ったものの、いくつかのエントリーが損切りにかかってしまいました。
こういう時に感じるのは、「方向感が定まらない状況での逆張りは本当に危険だ」ということです。
FOMC後は一時的に動意づくため、テクニカル指標が機能しにくいこともあります。
一方、利確できたのは、明確なサポートラインでの反発を見極めてからの短期ロングでした。
損切りを恐れずにポジションを切り替える勇気と、柔軟な対応力が結果的に収支を支えました。

利確の喜びよりも、損切りの判断を1秒でも早くできた自分を、今回は褒めてあげたいと思います。
リスク管理(資金管理、ストップロスの設定、逆張り・順張りの戦略)
FOMCのような重要イベント時は、相場が一方向に大きく動くこともあるため、普段以上にリスク管理が重要になります。
私はこうした局面では、ポジションサイズを通常の半分以下に抑えたり、ストップロスの位置を事前に明確に決めておくことを徹底しています。
特にトレンドが出やすいタイミングでは、逆張りよりも流れに乗った順張りを意識したほうが、結果的に勝率は高くなると感じています。
急な値動きに振り回されないためにも、自分の中でのルールと冷静な判断を保つことが欠かせません。
今後のドル円予想レンジとエントリーポイント・チャート上の注目ライン
現時点でのドル円の予想レンジは、147.50〜148.80 付近と見ています。
ただし、この範囲は今後の経済指標や地政学的リスク次第で容易にブレイクされる可能性があります。
チャート的には、148.30付近に短期の上値抵抗があり、それを上抜けると149円台回復の可能性も出てきます。
逆に147.30〜147.00にはサポート帯があるため、このゾーンを割ってくるようなら短期調整が進むと見ています。
私は、FOMC後に一方向に張るのではなく、「反応を見てからエントリーする」戦略を取っています。
エントリーポイントとしては、重要な水平ラインと移動平均線(特に4時間足ベース)を重視しており、それが私のトレードスタイルに最もフィットしています。

水平線+4時間足MA。
これが今の自分の鉄板です。
2025年9月FOMCと為替相場に関するFAQ
FOMCやドル円相場に関するニュースや分析記事を読む中で、読者の方からよくいただく質問や疑問点があります。
ここでは、2025年9月18日のFOMC発表に関連しつつも、本文では触れきれなかった内容や、初心者の方が特につまずきやすいポイントについて、Q&A形式でわかりやすくお答えしていきます。
トレードに活かせる知識や基礎的な理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてください。
Q1:FOMCとは何か?
A:FOMC(Federal Open Market Committee)は米国連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利等を決定する会合。
FRBの政策スタンスや将来見通しを示すため、為替・金利・株式に大きな影響を与える。
Q2:ドル円相場における「金利差」がなぜ重要か?
A:米国と日本の金利差が拡大すると、トレーダーはより高利の通貨への投資を好む傾向があり、ドル買い/円売りが進みやすくなる。
逆に金利差縮小なら円高圧力が出やすい。
Q3:ドットチャート(Dot Plot)って何?どう見ればいい?
A:FOMCで発表される「ドットチャート」はFRBの複数のメンバーが予想する将来の政策金利水準を点で示したもの。
これによって市場が年内・来年の利下げ・利上げの可能性を読み解く。
Q4:発表時に逆張りが危ない理由は?
A:発表直後は市場のボラティリティが高いため、思わぬ値動きが発生する。
また、多くのトレーダーがポジションを持ち替えるタイミングになるため、スリッページや急変が起こりやすい。
Q5:なぜ私のFXブログでは「私見」が重要なのか?
A:経済指標や声明文は多くのメディアでほぼ同じ情報が出るが、個人の経験やポジション判断を含めることで、読者にリアルな判断材料を提供できる。
差別化にもなる。
Q6:FOMCの発表が為替以外に与える影響は?
A:債券利回り・株式市場・金利先物・国債市場など。特に米長期金利が動くと、為替にも二次的な影響。
リスク資産のセンチメントも変化する。
Q7:「利下げがいつか」はなぜ予想が難しいのか?
A:インフレ動向、雇用統計、サプライチェーンや国際情勢など変数が多く、FRBメンバーの見方も異なる。
新しいデータが出るたびに見通しが変化する。
Q8:トレードをする上で特に注目すべきチャート指標は?
A:サポート・レジスタンスライン、移動平均線(特に50日線・100日線)、ピボットポイント、ボリンジャーバンドやATRなどのボラティリティ指標。
Q9:9月18日FOMCと前回FOMCとの違いは?
A:(もし前回が利下げ見込み/据え置き等であったなら)発言内容・声明のトーン・ドットチャートの見通しの変化・インフレ/雇用データとの乖離がどうだったかなどで比較可能。
過去の発表との違いを押さえることが分析の鍵。
Q10:私のような個人トレーダーが活用できる情報源は何か?
A:FRB公式発表文・経済指標データ(BLS, CPI, PCEなど)/マーケット前日予想レポート/トレーダー同士のチャット・SNS情報/チャートプラットフォーム(TradingView等)。ただし、情報の信頼性に注意。
【総括】2025年9月FOMC後のドル円相場の見通しと注意点
- 2025年9月18日深夜のFOMCでは、政策金利・ドットチャート・FRBの見通しが市場の想定とどう違ったかが最重要ポイント。
- ドル円は発表直後、大きく動き、サポート・レジスタンスラインを試す展開に。金利差の動きが価格に強く影響。
- 経済指標(インフレ・雇用・PCEなど)の最新データが利下げ見通しを左右。FRBの発言トーンに注意。
- 私のトレード経験から、逆張りのリスクとストップロス設定の重要性を再認識。資金管理が結果を分ける。
- 今後の見通しレンジとチャート上で注目すべきラインを押さえておけば、急変へ対応しやすい。
今回のFOMC発表では、声明文・ドットチャート・FRBメンバーの発言が市場予想とどこまで一致していたかが鍵でした。
ドル円は発表直後に大きな値動きを見せ、金利差の変化が即座に反応として表れました。
私自身、発表直後の逆張りで痛い損切りを経験したことで、「想定外の動き」を前提とした戦略とリスク管理の大切さを改めて感じています。
中長期的には、インフレ・雇用データの動向とFRBの見通しが為替を左右するため、それらを注視しつつ、チャートの注目ラインを定めておくことが、相場の荒れた局面でも対応力を持つための鍵だと思います。
眠れない夜は続きますが、この「荒波」を乗りこなした時の成長こそがFXの醍醐味。
共に頑張りましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今回のFOMC速報が、あなたのトレードの一助になれば幸いです。

また大きな動きがあれば随時更新していきますので、ぜひ、また見に来てください。
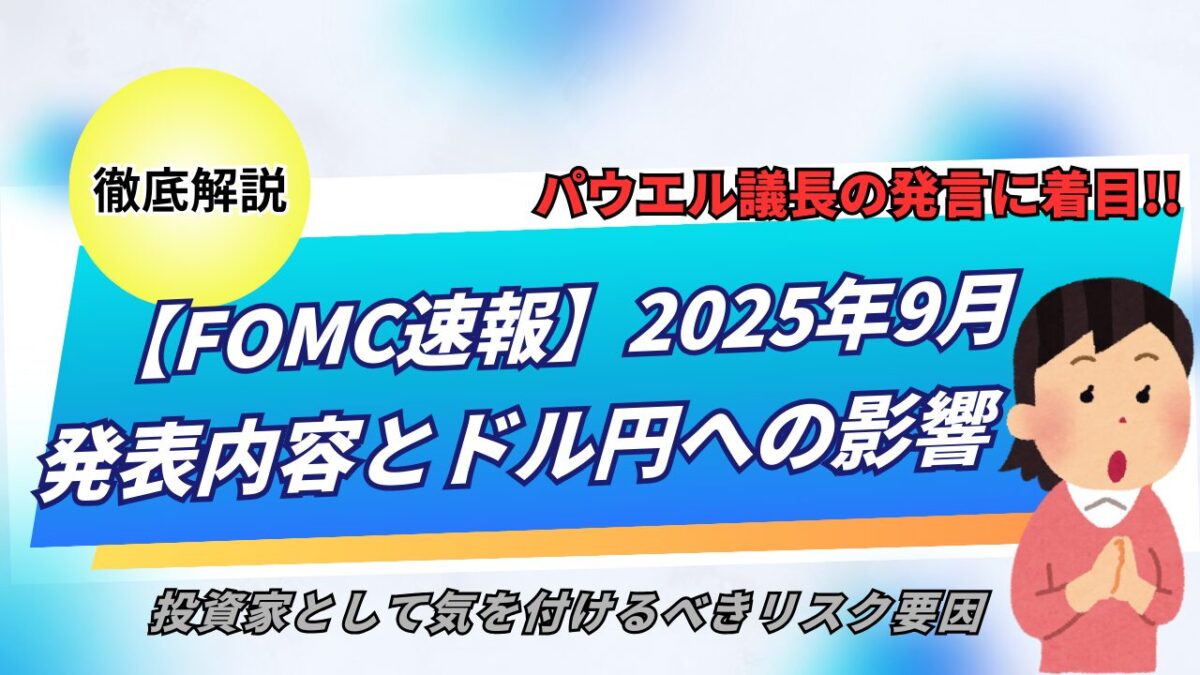




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン

