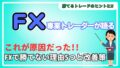2025年9月19日(金)のFXトレードを振り返ります。
本日は、日銀の金融政策決定会合が注目イベントとなり、ドル円は朝147.90付近から始まり、発表直後には147.20付近まで急落。
その後、植田総裁の会見をきっかけに148.28付近まで一気に円安が進行するなど、値動きの激しい一日でした。
私はこの「据え置き」を予想していたため、政策金利発表前に逆指値ロングを仕込みましたが、結果的に含み損を抱える展開に。
ただ、会見内容次第で流れが変わると判断し、ホールド戦略を選択。その後は少額ながらも利確に成功し、最終的な収支は微益でした。
この記事では、当日のドル円の値動き分析から、私の具体的なエントリー・決済ポイント、反省点、そして来週に向けた視点まで、実体験に基づいたリアルな戦略と結果をお届けします。
トレード後に見返してみても、値動きが大きかっただけに、「あと一歩で大きく取れたのに」と思う場面も多く、記録としても学びとしても残す価値がある一日だったと感じています。
- 本日の為替市況とドル円レートの動き
- 本日のトレード戦略と事前予測
- 収支結果とトレード詳細
- 反省点と私見 — “惜しかった”要因分析
- 来週に向けての戦略と注目の経済指標
- 本日のFX相場に関連する質問と回答集
- Q1:日銀会合で「据え置き」が発表された後、なぜドル円は147.20付近まで下落したのか?
- Q2:植田総裁の会見で、どの発言が最もドル高・円安を促したか?
- Q3:会見後、ドル円が148.28付近まで上昇したタイミングの背景は何か?
- Q4:昼間に含み損60pipsを抱えた時点でどのような対策が考えられたか?
- Q5:夜間にかけてドル円が147.80〜148.00のレンジで推移した理由は?
- Q6:豪ドル円・ユーロドルではどのような動きがあったか?
- Q7:政策金利発表前に逆指値ロングを仕掛けた戦略は合理的だったか?
- Q8:22日以降の経済指標で特に注意すべきものは?
- Q9:この日のトレードで最も大きな誤りは何だったか?
- Q10:利益2,558円という結果について、今後どう活かせるか?
- 2025年9月19日の相場と私の戦略まとめ
本日の為替市況とドル円レートの動き
本日は日銀会合というビッグイベントを控え、朝から為替市場もやや警戒ムード。
ドル円は147.90付近で静かなスタートを切りましたが、政策金利発表をきっかけに相場は一変しました。
特に据え置きのニュースを受けた直後の急落、その後の植田総裁の会見による急反発など、一日を通して大きく揺れる展開に。
ここでは、時間帯ごとのドル円の流れを追いながら、動きの背景を整理してみます。
朝~昼の相場スタート:147.90付近の様子見
東京時間の朝、ドル円は147.90付近で始まり、市場参加者の警戒感が強く表れていた。
大きな指標発表もまだで、テクニカルには前日の終値近辺を維持しながら、上下どちらかへ動き出すのを待つ展開だと感じた。
私もこの時間帯はポジションを抑えて、無理なエントリーを避け、戦線を整えることに集中していた。
為替チャートを見ると、直近サポート近辺に買いが入りにくい動きだったため、一旦レンジの上限・下限を確認する動きが強かったと思う。
特にロンドンやアメリカ市場が動き出す前の東京・アジア時間は流動性が低く、スリッページや滑りが生じやすいため、私はこの時間のエントリーは必ず手動で確認を取るようにしている。
日銀会合・据え置き発表のニュースがレートに与えた影響
正午過ぎ、日本銀行が政策金利を0.50%で据え置くと正式発表。
市場の大方の予想通りであったが、その直後にドル円は147.20付近まで急落した。
この「予想通り」の据え置きも、予想の一部であり“方向感を探る材料”として機能していたため、材料出尽くし感からの売りが優勢になったのだと私には映った。
私はこの下落自体は予測していたのですが、発表の瞬間に一度レートが上に跳ねたため、発表前に仕込んでいた新規逆指値ロングが約定してしまい、その結果として含み損を抱えることになりました。
けれども、この下落が会見での発言次第では巻き返せると考えていたので、焦らず静観する選択をした。

あなたなら、この急落局面でどう判断しますか?
焦って損切りしますか、それともホールドしますか?
この発表の瞬間こそが、その後の戦略の分岐点だった。
植田総裁会見の発言で円安が進んだ局面分析
午後の植田総裁の会見では、「データを見て判断する」「景気の見通しや物価推移に不確実性がある」という慎重な文言が混じっていたが、それが逆に市場に“今すぐの追加緩和変更はない”という安心感を与えたようだ。
市場はこの安心感を利用し、ドル買い・円売りを進めた。
このフェーズでドル円が一気に148.28付近まで跳ね上がったのは、会見中盤からの発言で“景気底堅さ”や“インフレ見通しの回復可能性”をにじませる部分があったからだと考えている。
私のポジションではこの上昇を捉えられたのがラッキーなところ。
だが、上がりきった後、反動が来るリスクも常に頭の片隅にあったので、利確のタイミングを慎重に見極めた。
夕方以降~夜間の動きと終値付近のレンジ推移
植田総裁の会見後、夕方から夜にかけては相場の勢いが落ち着き、レンジに収束する動きが目立った。
ドル円のレンジはおおよそ147.80〜148.00と狭くなり、この時間帯は大きなニュースも出ず、参加者がポジション調整や翌日の市場動向を見据えたポジショニングにシフトした印象。
私はこの時間帯、含み益が出ていたポジションを少しずつ微益で手放すなど、安全側に寄せる操作を行った。
利益を伸ばしたい気持ちもあったが、過去の失敗からも、“明日の動きが見えない夜”は無理にリスクを取るよりも、小さな利確を重ねるほうが心が安定するからだ。
結局このレンジ内の揺れもあって、利益と損失を行ったり来たりの展開になった。
本日のトレード戦略と事前予測
日銀イベントのある日は、「動くかどうか」よりも「どう動くか」を読むのが難しいですが、私は今回は据え置きと予想し、あえて発表前に仕掛けを入れました。
特に注意したのは、事前ポジションの取り方と、その後の初動への備えです。
ここでは、私がどのように相場観を持ち、どのタイミングで注文を設定したか、実際の思考と準備を交えてお伝えします。
政策金利発表前に私が据え置きを予想した理由
私が政策金利を据え置くと予想した根拠は複数ある。
まず、日本の直近の物価や賃金の動きが、利上げに踏み切るにはまだ力不足と見る向きが多かったこと。
加えて、世界的な金利環境の不確実性もあり、日銀としては慎重な姿勢を崩さないだろうと考えていた。
また、市場のコンセンサスやアナリストの予測を複数チェックし、“据え置き”という見方が主流であったことも重視した。
だからこそ、会見での言動が円安要因となる可能性に賭けて、発表前の逆指値ロングという戦略を採用した。
もちろんこの予測にはリスクがあったが、「大きく動かない可能性を織り込んだ上での戦略」であった。
新規逆指値ロング注文の設定ポイントとリスク管理
私は政策金利発表前に、現在のレートから約15pips上に逆指値ロングを入れた。
この位置設定には、「発表後の初動で会見内容次第では円安方向へブレイクする可能性が最も高いと予想されるゾーン」を念頭に置いた。
つまり、発表後すぐの反応を捉えにいくトリガーとするための設定だった。
ただリスク管理も疎かにはしなかった。
あらかじめ「このラインを割ったら損切りも視野に入れる」と決めていたことで、実際に含み損が膨らんでも慌てずに対応できました。
また、発表直後のスリッページや滑り込み注文が想定外の方向に動いた場合を想定して、エントリー後に逆指値を調整する余地を残していたのも戦略の一部だ。
含み損を背負った経過:昼から60pipsのマイナスをどう判断したか
政策発表後、初動で逆指値ロングがヒットしたものの、その直後に相場が一転し、私は60pipsほどの含み損を抱えることになった。
この瞬間、心拍数が上がり、「誤った仕掛けだったかもしれない」という不安が渦巻いた。
しかし私は、「植田総裁の会見は過去に円安方向へのサプライズを生んだことが多い」という自分の経験を信じて、すぐには損切りを選ばなかった。
その後、会見中の発言で上昇圧が強まる場面を確認できたため、徐々に含み損を圧縮。
ホールドを選んだ判断が功を奏し、最終的には微益で決済することができた。
もちろんこの過程ではメンタルが揺れたし、ポジションを「どこで見切るか」を何度も迷った瞬間があった。
だが、この経験は私にとっても良い教訓になったと感じる。
収支結果とトレード詳細
正直、今日はもう少し取れた気もしますが、結果だけ見れば「微益で終えられた」という意味では満足しています。
ドル円を中心に、豪ドル円・ユーロドルも短期トレードで入ったものの、勝ちと負けを繰り返すような落ち着かない展開に。
ここでは、通貨ペア別の戦略とその結果、取引タイミング、エントリー・決済の理由について詳しく記録しておきます。
取引通貨ペア別:ドル円・豪ドル円・ユーロドルの動きと私の取引戦略
この日はメインでドル円を監視していましたが、相場のボラが大きくなった時間帯を狙って、豪ドル円とユーロドルにも短期でエントリーしました。
特に植田総裁の会見をきっかけに全体的な円売りムードが出た時間帯では、クロス円の通貨ペアが一斉に動いた印象です。
- ドル円
イベント前の逆指値ロングが早々に含み損になったものの、会見後の上昇でプラ転。
小幅ながらも利確。全体の主戦場でした。 - 豪ドル円
反発の動きに乗って買いエントリーを狙いましたが、押し目が浅く、エントリー後の戻りが弱くて結局微益で撤退。
流れに勢いがなかったのが読み違いでした。 - ユーロドル
ドル全体の強弱を測るためのインジケーター的な立ち位置で見ていましたが、NY時間前後に軽く売りで入って10pips程度の利幅が取れました。
このように、メインのドル円は戦略通りだったものの、クロス円系やユーロドルにおいては“タイミング重視”の瞬発型エントリーでした。
エントリー時点のシナリオ構築と、それを崩された時の撤退判断が重要だったと感じています。
利確・損切りの判断タイミング:植田会見後の微プラス決済とその後の “取り切れなかった” ケース
政策発表後に逆指値が執行され、含み損を60pipsほど抱えた時点では、正直言って損切りも一瞬考えました。
しかし、会見内容次第では流れが変わると思い、植田総裁の発言をリアルタイムで追いながら様子見。
思った通り、円安方向へ戻す動きが出てきたため、ある程度戻ったタイミングで微益で決済を選びました。
ただ、結果的にそこが“浅利確”だったのは反省点です。
その後の伸びで148.28付近まで行ったことを考えれば、もう10〜15pipsは取れたはず。
でも、含み損を一時的にでも60pips背負っていたことで、「利があるうちに逃げたい」という気持ちが勝ってしまいました。
また、夜のレンジ時間帯では、数回のスキャルピングでコツコツ取ったり、反対に持ってかれたりと“取り切れなかった”場面も多く、特に利幅を引っ張る自信が持てなかったのが悔やまれます。
今日は、自分なりに冷静に判断して、リスク管理を優先して動いた日ということで、納得はしてますが、「もっと上手く立ち回れたかも」と感じる局面もありました。
最終結果:利益2,558円/総取引回数・勝率・平均pipsなど

最終的な収支は+2,558円。
大きな勝ちではありませんが、含み損を背負いながらも冷静に対処できた点、自分なりの戦略が通用した点は評価しています。
- 総取引回数:25回
- 勝率:56%(14勝11敗)
- 使用通貨ペア:ドル円/豪ドル円/ユーロドル
この日は相場の動き自体は非常に魅力的でしたが、序盤の逆指値ポジションの扱いで全体がやや受け身になったことが、収支の伸びに影響したと感じています。
あと2〜3トレード積極的に攻められていれば、1万円近くまで持っていけたかもしれませんが、無理に取りにいかなかった点はポジティブに受け止めたいです。

トレアイを見たところ、9月19日に少しでも勝てたトレーダーは、全体の3割くらいだったようです。
反省点と私見 — “惜しかった”要因分析
収支としてはプラスだったとはいえ、今日の相場の“動きの幅”を考えれば、もう少し取れていた場面もありました。
特に悔やまれるのは、初動で逆指値が狩られそうになったあの瞬間の判断と、その後の注文設定の距離感。
自分の中ではある程度の根拠があったものの、あと少し工夫していれば…という場面も多かったです。
ここでは、そのあたりの“反省”と“次につながる気づき”をまとめます。
ホールド vs 手仕舞いの判断で迷った瞬間
60pipsの含み損を背負っていた昼過ぎ、PCを見ながら「このまま戻らなかったらどうするか」を真剣に考えていました。
こういう状況下では、「今切っておけば損失はこれだけで済む」という“安心を買いたくなる気持ち”と、「いや、反発の可能性もある」という希望的観測が頭の中でぶつかります。
今回私がホールドを選んだ決め手は、「値動きの原因がテクニカルではなくイベント要因だったこと」でした。
会見という次の材料が控えている中で、相場がまだ方向を決めかねているように見えたんです。
結果的には上手くいきましたが、正直なところ、この判断は完璧とは言えず、自信満々だったというより、“経験的にそうなる可能性が高い”という肌感覚でした。
何度やってもこの判断は悩みます。
植田総裁会見の予測精度とその信頼度の振れ幅
今回は会見によって円安が進む展開をある程度想定していましたが、実際に動いてみるまでは確信は持てませんでした。
特に植田総裁の会見は、内容自体は慎重でも、市場が予想以上に勝手に好感するケースことが多く、ある種“読み筋のブレ”が出やすい材料だと感じています。
過去の傾向では、「明確に利上げを否定しない」=円安という流れがよくあり、今回もそれに準じる展開でした。
ただし、このパターンはいつまでも通用するものではないと思っているので、次回以降も過信は禁物だと感じています。
相場は同じように見えても、受け止め方は日ごとに変わる。
それを忘れないようにしたいですね。

植田総裁の会見、あなたならどのタイミングでポジションを取りますか?
注文設定の距離感(15pips離し等)が良かったか/改善したいか
今回の逆指値ロング注文は、レートから約15pips上に設定しました。
これは、急騰に乗り遅れず、かつダマシを避ける“程よい距離”を狙ったものでした。
が、結果論ではありますが、今回の私のように「初動で一瞬だけ飛んでからすぐ戻る」展開では、まさにその“15pips”に引っかかる形になってしまった。
次回以降は、同じく急変が予想されるイベント時でも、前回の反省を活かして、エントリー距離をもう少し広げて20〜25pipsに設定するか、あるいは“成行で飛び乗らず様子を見る”選択肢も持っておきたいと考えています。
事前の準備と、当日の値動きの噛み合わせがピタッと来るとは限らないので、複数パターンを用意しておくのが今後の課題ですね。
来週に向けての戦略と注目の経済指標
イベントを終えて一息ついた感もありますが、来週22日以降も重要な経済指標が多数控えています。
私は昨日の記事でも一部紹介していますが、来週は特に米国のCPIや雇用統計、日本の国内経済指標も相まって、再び大きな動きが期待できる場面が続くと見ています。
ここでは、今後のスケジュールと、私が注目している指標、それに対してどんなトレード準備をしていくつもりかをお話しします。
9月22日以降の重要指標スケジュール(前回紹介済みと重複しないもの)
前回の記事では主要指標の一覧を紹介しましたが、ここでは注目度は高いが見落とされがちな指標に絞ってピックアップします。
これらも相場の流れを変えるきっかけになり得ます。
- 9月24日(火)
米・リッチモンド連銀製造業指数 - 9月25日(水)
豪・月次CPI、ドイツIFO景況感指数 - 9月26日(木)
米・四半期GDP、失業保険申請件数 - 9月27日(金)
米・PCEデフレーター(FRBが注目)
特に月末に向かうにつれて、米国のインフレ関連データと景気指標が重なっており、ドル買い・売りのトレンド形成につながる可能性があります。
加えて、リスクイベントの間隙を縫って出る中堅指標でも、最近は値動きが出やすくなっている印象です。
これらもカレンダーにチェックしておくと安心です。
次の政策発表/要人発言で注意すべきポイント
今後の注目は、日銀に加えてFRB(米連邦準備制度)関係者の発言。
特に米国では、「年内利下げの有無」や「長期金利の水準」が焦点となっており、FOMCメンバーの一言がドル円の動向を大きく動かすリスクがあります。
注意すべきポイントは以下の通りです:
- 「ターミナルレート(最終金利水準)」への見通しが出る発言。
- 「労働市場の強弱」に対する見解。
- 「インフレ鈍化 or 高止まり」の判断基準に関する発言。
これらの内容が市場に対してタカ派・ハト派どちらに取られるかで、ドル円は簡単に1円近く動きます。
最近では、“ハト派に見えるタカ派”や“中立に見えてネガティブ”といった微妙なニュアンスが重要になるため、ニュースの見出しだけでなく、全文読解や発言前後の地合いチェックが欠かせません。
私が来週試したいトレード戦略の仮説
来週は指標が多く、また週の中盤〜後半にかけてボラティリティが高まりやすい構成です。
そこで私は、「初動をあえて捨てて、二波目を狙う戦略」を試してみたいと考えています。
理由は、今回のようにイベント直後の動きに乗ったことで逆行・含み損になるリスクを実感したからです。
今後は:
- 指標発表後の5〜10分は静観。
- 高値・安値を一度付けた後の「押し・戻し」を狙う。
- ストップはタイトに、リワード比を意識する。
という流れで、“乗り遅れても良いから精度を上げる”スタンスに寄せたいです。
また、エントリーの精度向上のために、指標当日はテクニカルよりも相場のボラ感・板の反応を重視して、裁量での判断も取り入れる予定です。
試行錯誤しながら、自分のスタイルに合った立ち回り方を見つけていきたいですね。

来週もトライ&エラーの連続になりそうですが、それこそが相場の面白さ。
自分なりの答えを探していきます。
本日のFX相場に関連する質問と回答集
FXトレードを日々行っていると、相場の値動きだけでなく「なぜそう動いたのか」「次はどう備えるべきか」といった疑問が尽きません。
ここでは2025年9月19日(金)の相場状況に関連して、実際に私自身や他のトレーダー仲間の間で話題になった「よくある質問」を、Q&A形式でまとめました。
相場の背景や政策判断に関する話だけでなく、翌週以降の経済指標や市場の注目点など、実践的なヒントになるものを厳選しています。
本文では触れていない視点も盛り込んでいるので、ぜひあわせて参考にしてみてください。
Q1:日銀会合で「据え置き」が発表された後、なぜドル円は147.20付近まで下落したのか?
A:市場は政策金利据え置きそのものよりも、その後の会見での文言・見通しへのヒントを探していた。
発表直後は“予想通り”と反応しやすく、材料不足感からドル売り・円買いが先走った。
その後、植田総裁の会見による円安サインが出て戻した。
Q2:植田総裁の会見で、どの発言が最もドル高・円安を促したか?
A:会見途中での「将来の政策変更の可能性」や「物価見通しの持続可能性への言及」が、円安方向への期待を高めた。
市場はこうした文言を“変更余地あり”とみて反応することが多いと私は感じている。
Q3:会見後、ドル円が148.28付近まで上昇したタイミングの背景は何か?
A:会見中の発言内容が“円安期待”を強めたことと、業者・投機筋がロングポジションを増やしたことが主因。
テクニカル的にも147.50〜148.00の抵抗帯を突破する動きがあったため、そのブレイクを利用した買いが加速したと思われる。
Q4:昼間に含み損60pipsを抱えた時点でどのような対策が考えられたか?
A:損切り設定を近めに置く/部分決済をする/逆指値注文の修正など。
私は“ホールドして勝負する”判断をしたが、その判断にはリスクが伴うので“もし逆方向にブレイクしたら”という前提でストップを意識していた。
Q5:夜間にかけてドル円が147.80〜148.00のレンジで推移した理由は?
A:為替市場参加者の間で「本日のサプライズ材料は出尽くした」という空気があったため。
さらに、アメリカ側・日本側ともに重要指標の発表がこの時間帯では少なく、ポジション調整や利益確定が優勢になったと考えられる。
Q6:豪ドル円・ユーロドルではどのような動きがあったか?
A:豪ドル円は日本円以外の通貨でのドル高・円安トレンドの影響を受けやすく、ドル円の動きに連動して上下しやすかった。
ユーロドルは米ドル側の利回り期待などが重しになり、ドル高圧力が強かったため、私は短期の押し目買いを狙ったが反応が鈍かった。
Q7:政策金利発表前に逆指値ロングを仕掛けた戦略は合理的だったか?
A:合理性はある。
なぜなら“据え置き”が“織り込み済み”と市場が判断していたので、会見内容に円安材料があれば利益になる見込みがあったから。
ただ、初動で上に飛ぶ可能性もあって含み損を抱えるリスクは承知していた。
Q8:22日以降の経済指標で特に注意すべきものは?
A:米国関連での雇用統計や消費者物価指数(CPI)、日本では機械受注や鉱工業生産など。
特に米CPIや米雇用統計はドル買い材料とみられやすいため、ドル円等で大きな動きを引き起こす可能性が高い。
Q9:この日のトレードで最も大きな誤りは何だったか?
A:誤りというほどではないが、逆指値ロングの注文設定を「初動で上に飛んだ」時点で即逃げる判断を取れなかったこと。
あと、損失許容度の見積もりが甘かったと感じている。
Q10:利益2,558円という結果について、今後どう活かせるか?
A:まずは“勝ち続けることよりも、負けを限定できること”の大切さを再認識。
感情に流されずにホールドする判断、判断ミスの見つけ方、注文設定の改善などを次回に反映したい。
小さくても利益が出た日は次の戦略設計に自信を持てる。
2025年9月19日の相場と私の戦略まとめ
- 昼間はドル円147.90付近からスタートし、日銀の据え置き発表で147.20付近まで下落。
- 植田総裁会見中に円安期待が強まり、148.28付近まで上昇。
- 夜~翌朝にかけては147.80~148.00付近でレンジ推移で終わる展開。
- 私は政策金利据え置きを予想し、発表前に新規逆指値ロングを設定(約15pips離し)する戦略を取った。
- 昼に約60pipsの含み損を抱えたが、植田会見で円安になる可能性が高いと判断しホールド → 微プラスで利確。
- 全体として値動きは良かったが、利確のタイミングや逆指値設定など、あと少しで改善できる余地あり。
今日のトレードは、朝のレート動きから日銀の据え置き発表、植田総裁の会見と、一連のニュースがドル円に対して明瞭な反応を引き起こした一日でした。
私は政策据え置きを予想していたため、リスクをとって逆指値ロングを早めに入れてみたところ、含み損を抱える展開もありましたが、会見による円安期待を信じてホールドした判断は正解だったと言えます。
利益は大きくないものの、負けなかったという“結果”を得られたこと、値動きの方向性をうまく捉えられたことは自分の戦略の一部が有効だった証拠です。
ただ、注文の設定、利確・損切りのタイミングはもっと磨くべきだと感じました。
来週以降、特に22日以降の経済指標をウォッチしながら、同じような材料が出たときにスムーズに動ける準備をしておきたいです。
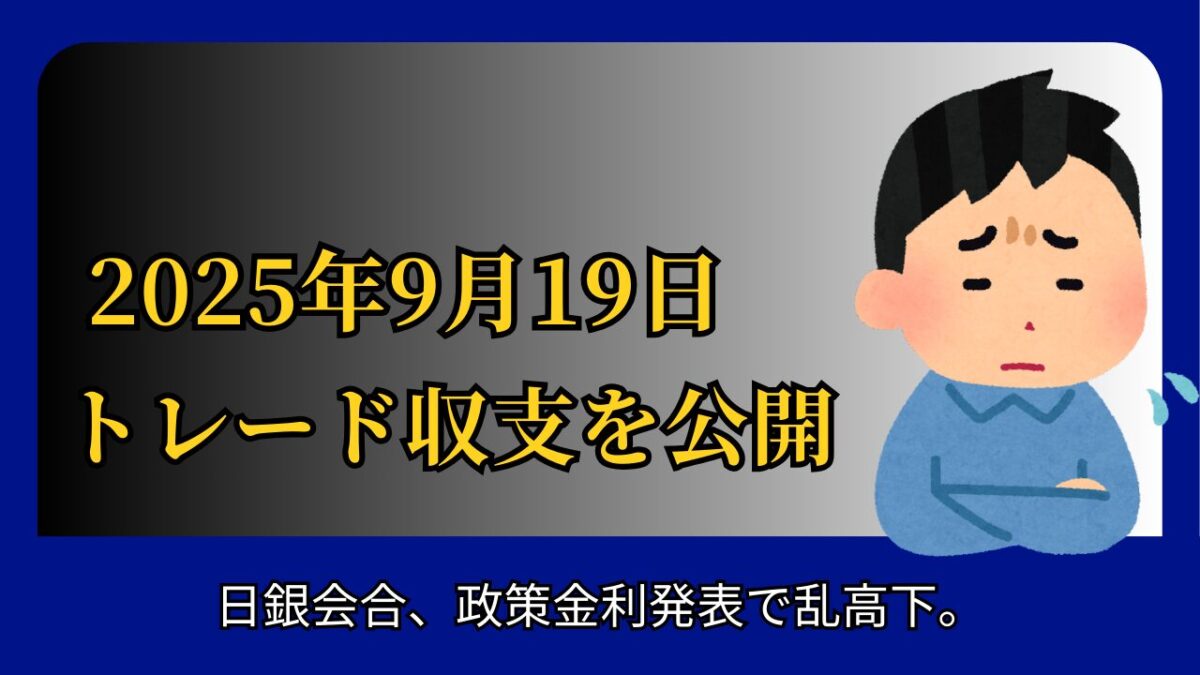




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン