2025年9月23日は、日本の祝日で東京市場が休場、重要指標もなく全体的に静かな1日となりました。
ドル円相場は朝から147.70付近でスタートし、日中から夜にかけては147.50~147.90のレンジ内を推移。
夜のパウエルFRB議長の会見でも相場に大きな動きはなく、結果的には「材料難の横ばい相場」だったと言えるでしょう。
そんななか、私も無理なトレードは避けつつ、ドル円でスキャルピングを4回ほど実施しましたが、収支は−3,006円という結果に。
今回は、値動きが悪い中での立ち回り方や、実際に行ったトレードの反省点・学びを中心に、振り返りと検証をしていきます。
2025年9月23日のドル円相場動向と背景分析
9月23日のドル円は、祝日ということもあり東京時間から大きな動きは見られず、147.50〜147.90の狭い範囲でのレンジ相場が続きました。
市場参加者も少なく、ボラティリティが極端に低い1日でした。
ここでは、相場がこうなった背景や、レンジが続く中でどういった点に注目すべきだったかを整理していきます。
朝〜日中のドル円レンジ展開(147.50~147.90)
2025年9月23日の朝、ドル円は147.70付近からスタート。
その後、東京時間を通して目立った動きはなく、147.50〜147.90の狭いレンジで推移しました。
この日の東京市場は祝日による休場。
さらに主要な経済指標もなく、値動きを支える材料に乏しかったため、売買が交錯する水準でもみ合う展開に終始しました。
出来高も明らかに薄く、アルゴリズムによる細かい値動きが目立った印象です。
私自身もこの時間帯に数回チャートを確認しましたが、方向感がなさすぎて、積極的なエントリーには至らず。
朝からの段階で「今日は動かないかも」と警戒していた方が多かったのではないでしょうか。

東京休場?OK、今日はロンドン時間まで様子見でいいな。
夜のパウエル記者会見と相場反応(ほぼ変化なし)
この日は米国時間にパウエルFRB議長の会見がありましたが、市場の反応はほぼ無風でした。
発言内容自体も目新しい情報はなく、金利に関しても「データ次第」のスタンスを繰り返すにとどまり、市場は織り込み済みの内容と判断。
発言中もドル円は147.60〜147.80付近で小幅に上下しただけで、目立ったブレイクもありませんでした。
実際のチャートを見ても、ローソク足がほとんどヒゲだけで構成されており、方向感のなさが際立っていました。
個人的にも、「何かしら動くかも」と思って一応チェックしていましたが、ポジションを取るに値する動きではなく、エントリーは見送りました。
翌朝にかけての下落〜調整(147.46付近まで安値更新)
NY時間後半から翌朝にかけて、ドル円はジリジリと下落し、最終的に147.46付近まで安値を更新しました。
急落というよりも「ジワ下げ」で、流動性の低い中でストップを巻き込みながら調整が進んだ形です。
ここまでほとんど動きのなかった1日のなかで、ようやく値幅が出たのがこの時間帯でした。
ただし、この下落も限定的で、翌朝には再び147.70付近まで戻しており、「あまり意味のない調整だったな」という印象です。
実際にトレードをしていた人でも、この時間帯はポジションを取っていなかったケースが多いかもしれません。
祝日・指標薄のなかでのレンジの重さ
全体を通して感じたのは、「とにかく動きが鈍い1日だった」という点に尽きます。
東京市場は祝日で休場、米国も重要指標なし。
唯一注目されたパウエル発言もサプライズに乏しく、投機的な注文も入りにくい環境でした。
そのため、トレンドを狙うにも、スキャルで抜くにも非常に難しい相場だったと言えるでしょう。
私自身も「今日は無理しない方がいい」と感じつつも、4回だけスキャルで入ってみましたが、やはり相場の重さにストレスが溜まり、結果としてマイナス収支に終わりました。
こういう日は、無理に手を出さず休むのが正解だったと反省しています
当日の私のFXトレード記録と収支結果
あまり期待せずに、動きのない相場に気づきつつも、「少しだけでも取れれば」と思い、ドル円でスキャルピングを4回行いました。
その結果は−3,006円。
ここでは、取引ごとのエントリー根拠やタイミング、結果、そして自分の感情や判断のブレなど、具体的に振り返っていきます。
取引通貨・時間足・トレード回数(ドル円スキャル4回)
本日の取引はすべてドル円で行いました。
使用した時間足は 5分足〜15分足中心の短期足で、いわゆるスキャルピング寄りのトレードです。
全体的に値動きが乏しく、「ここしかない」と思えるようなチャンスは1〜2回程度。
その中で4回だけエントリーを行いましたが、やはりタイミングを絞りきれなかった印象が強いです。
本来であれば、こういう日はノートレでも良かったのですが、「何かできることはないか」と少し探りを入れてしまったのが、良くも悪くも収支に表れた形です。

シナリオ外なら“見送り”が基本。手を出した時点で少し崩れてる。
勝敗履歴・利益・損失の内訳
以下は本日のトレード結果の内訳です(記録より抜粋):
- 1勝:+960円
- 3敗:−1,200円、−1,030円、−1,736円
合計収支:−3,006円
1勝3敗という結果でしたが、損失の金額がやや大きめなのが今回のポイント。
特に1回目の負けで損切りが遅れたことが響き、残り2回の小さな損失で収支が重くなりました。
一方、唯一の勝ちトレードは、すぐに逃げた判断がうまくいったケースで、レンジ相場においては特に、「素早い撤退」が重要だと改めて感じました。
トレードごとの簡単な振り返り(成功例・失敗例)
それぞれのトレードについて簡単に振り返ります:
1回目(勝ち)
147.65からの反発を拾って+960円。
→ 朝のサポート付近でエントリー。ローソク足の反転が明確で、比較的良いタイミングだった。利確も早めで良判断。
2回目(負け)
上昇途中を追いかけて−1,200円。
→ 値動きが緩慢なのに「伸びるかも」と期待して入ってしまった。
典型的な逆張り損。
3回目(負け)
パウエル発言中に飛び乗って−1,030円。
→ ボラに期待したが結局動かず。
発言内容が事前予想どおりで、エントリー自体が無意味だった。
4回目(負け)
深夜の下落に逆張りして−1,736円。
→ 安値付近で無理にロング。
結果として一番やってはいけない場所でエントリーしてしまった。
反省点: 感情でエントリーしたわけではないが、「何かしないと」という焦りに近い感覚が数回の無駄打ちに繋がってしまいました。
最終収支:−3,006円

本日の最終収支は−3,006円。
金額自体はそこまで大きくはないものの、内容としては「やらなくていいトレードをやってしまった日」だったと強く反省しています。
特に、値動きが鈍い中で無理にチャンスを探しにいった結果、タイミングがズレてエントリー精度が落ちていました。
こういう日は「潔くノートレ」を選ぶメンタルが必要だと痛感。
また、祝日・指標なし・薄商いと条件が揃っていたにもかかわらず、「もしかしたら動くかも」という甘い見通しで構えていたことも良くなかったと思います。
値動きが悪い日は楽しくない。
これは今日のような相場を経験すると、身に染みて実感します。
相場に合わせて「休む技術」も、引き続き磨いていきたいと思います。
収支悪化の原因考察と改善策
動きのない相場に気づきつつも、欲に負けてしまい、「少しだけでも取れれば」と思い、ドル円でスキャルピングを4回行いました。
その結果は−3,006円。
ここでは、取引ごとのエントリー根拠やタイミング、結果、そして自分の感情や判断のブレなど、具体的に振り返っていきます。
値動きが悪い日はなぜトレードが苦しくなるか
値動きが乏しいレンジ相場では、トレーダーの待つ力が試される場面が増えます。
上下どちらにもブレイクする気配がなく、ローソク足は小さく、出来高も薄い。
この状況では、「そろそろ動くかもしれない」という期待と焦りが入り混じり、ついエントリーしてしまう人も少なくありません。
私自身も、今日のように動きが少ない相場では、「何かやらなければ」と焦る気持ちに駆られがちです。
しかし、レンジ相場では動かないことが最善の選択である時間帯が多く、それを受け入れることがなかなか難しいと感じます。
値動きが乏しいと、エントリーチャンスが少ない分、無理に入って損切りに遭い、さらにそれを取り返そうとして連敗する。
この悪循環は、どれだけ経験を積んだトレーダーでも陥りやすい典型的なパターンです。

レンジで無理撃ちしてからの、連敗→イライラ→大損。
あるある過ぎて泣ける。
エントリー判断の甘さ・根拠不足の問題点
今回のトレードを振り返ると、特に目立ったのがエントリー根拠の甘さです。
例えば「前の安値に近いからロング」「直近高値を少し超えたからブレイク狙いでロング」など、一見それらしく見えて、裏付けが不十分な判断が多かった。
特に値動きのない相場では、普段なら使わないような根拠でエントリーしてしまうことがあり、「エントリーありき」で理由をあとづけしてしまうケースもあります。
テクニカル分析が効きにくい相場であったとしても、最低限のルールやシナリオの確認は不可欠。
その基本を軽視してしまったことが、今回の損失の主な要因だったと感じています。
メンタルの影響と感情的トレードを避ける方法
値動きがない相場では、チャートを見続けることで余計な感情が生まれる傾向があります。
「このまま何もできなかったら、今日がムダになるかも。」
「他のトレーダーはきっと稼いでる。自分も何かしなきゃ。」
こういった心理が働くと、ルールではなく“感情”がトリガーになるエントリーが増えます。
私も今回、パウエル発言時に「何か起こるかも」と思って入りましたが、振り返ってみると完全に“期待ベース”であり、実際の値動きや根拠を無視したトレードでした。
こうした感情的なエントリーを防ぐには:
- トレード前に「入る条件」を紙に書いておく。
- 条件が揃わなければ、ノートレでもOKとするマインドを持つ。
- 一定時間チャートを見て“違和感”を感じたら一旦離れる。
など、意識的に「間を空ける」習慣が効果的です。
メンタル管理もトレードスキルの一部と捉える必要があります。
翌日以降に活かす改善ポイント
今回のような「やらなくてよかった日」のトレードでも、改善点は必ず見つかります。
・相場が動かない日は、最初から「参加しない選択肢」を持つこと。
「今日はレンジになりそう」と思った時点で、最低限の確認だけしてPCを閉じる勇気を。
・エントリー前に根拠を3つ以上書き出すクセをつける。
曖昧な根拠のまま入らない。
自分に「なぜ今エントリーするのか?」を問い直す。
・自分のトレードスタイルに合わない相場を見極める力を養う。
例えば、スキャルパーでも「方向感がない&出来高もない」相場では休む判断が大事。
・無理に「日々の収支を作ろう」としない。
トレードは長期で見るもの。
勝つ日もあれば負ける日もあると、割り切る姿勢が必要。
このような改善点を、次の日からすぐに意識することで、同じミスを繰り返す確率を大きく下げられます。
トレードは「反省し、修正し、また挑戦する」ことの繰り返し。
淡々と、しかし確実にレベルアップしていきたいですね。

改善点を“見える化”することで、次の一手が変わってくる。
経験から得た私見とトレーダーとしての学び
負けトレードには、必ず原因があります。
今回は、エントリーの根拠が曖昧だったことや、無理にトレードを成立させようとした「焦り」が敗因となりました。
ここでは、自分のトレードを冷静に見つめ直し、どこに改善の余地があったのかを掘り下げていきます。
ギャップを見逃さない「違和感」の捉え方
相場において、「なんかおかしい」と感じる小さな違和感には、実は大きな意味があることがよくあります。
ローソク足の形、インジケーターとの乖離、動きの鈍さやタイミングのズレ…。
こうした違和感は、単なるノイズに見える一方で、ダイバージェンスやトレンド転換の前触れであることも少なくありません。
私自身、「ブレイクしたのに勢いがない」「高値を更新しているのにインジケーターが伸びていない」など、小さなサインを無視してエントリーして痛い目を見たことが何度もあります。
違和感は“経験値の裏返し”です。
パターンとして言語化できない領域だからこそ、チャートを見続けることでしか磨けません。
「この動き、いつもと違うかも」と思ったときは、あえて見送りの判断をする勇気も必要です。
ルール・チェックリストの大切さを再確認
トレードは判断の連続です。そしてその判断をブレさせないために欠かせないのが「ルール化」と「チェックリスト化」です。
特にレンジ相場や薄商いの相場では、裁量が入りやすくなるため、事前に作ったルールが唯一の“安全装置”になります。
たとえば私のチェック項目は以下のようなものです:
- 上位足のトレンド認識はできているか。
- ダイバージェンスが明確に出ているか。
- 他のインジケーターとの一致があるか。
- ローソク足の反転サインが出ているか。
- 損切り・利確のラインは明確か。
こうしたチェックリストを、エントリー前に1つずつ声に出して確認するだけで、無駄なエントリーをかなり減らすことができます。
トレードルールを形だけにせず、「実行する仕組み」にまで落とし込むことが勝率の向上につながります。
資金管理とリスク設定の優先順位
勝率や手法よりも重要なのが、資金管理とリスクコントロールの徹底です。
たとえ優れたトレード手法を持っていても、1回の大きな損失で資金を失ってしまえば、次のチャンスを掴むことはできません。
私は1トレードごとの損失許容額を「1〜1.5%以内」に設定しています。
今日のように動きが悪い日は、リスク量をさらに抑えて、「ノートレードでもいい」という選択肢を持つことで、メンタルの安定にもつながっています。
特に初心者や連敗中のトレーダーは、「損失を取り返したい」という心理からリスクを増やしがちです。

この一発で取り返す…が、一番やっちゃダメな思考。
ですが、そういう時こそ「資金を守るトレード」に切り替える判断力が試されます。
勝つことよりも、まずは資金を減らさないこと。
その意識が、結果として勝率やトータル成績の改善にも直結します。
継続した検証・改善を習慣化するコツ
トレードで結果を出している人の多くは、例外なく「検証と記録」を習慣化しています。
勝ったトレードだけでなく、負けたトレードこそ掘り下げて分析することが、再現性のあるスキルへと変わっていく第一歩です。
私が意識しているポイントは以下の通り:
- 毎日の収支とエントリー理由、感情を記録する。
- スクリーンショット付きで反省点を残す。
- 「なぜ勝てたか」「なぜ負けたか」を言語化する。
- 同じパターンでの勝敗を分類して傾向を可視化する。
また、週末には過去のトレードを見返して、「もし再エントリーするとしたらどこか?」をシミュレーションします。
これは地味ですが、判断力と相場観を磨く非常に効果的な訓練です。
検証は一度きりでは意味がなく、継続してこそ価値が出てきます。
習慣化のコツは「記録のフォーマットを固定すること」と、「完璧に書こうとしないこと」です。
3行でもいいので、とにかく継続する。
それが上達の一番の近道です。
今後の見通しと戦略プラン
値幅が出にくい相場では、「エントリーしないこと」も立派な判断です。
しかし、私自身も過去にそういった場面で無理なトレードを繰り返し、痛い目を見てきました。
今回はその典型的なパターンが再発した形です。
この章では、動かない相場に対してどう向き合うべきかを整理します。
相場環境がレンジ優勢ならどう立ち回るか
レンジ相場が優勢な日は、トレンドフォロー型の戦略が機能しにくくなります。
特に、本日のように祝日・指標なし・出来高低下という三拍子が揃った日は、ブレイク狙いの飛び乗りや、中途半端なエントリーは機能しづらいです。
レンジでの基本戦略は、上下のバンド際で逆張りを行い、中間では様子見を徹底すること。
私の場合は、15分足や5分足でサポートラインとレジスタンスラインを明確に引き、そのゾーンに近づいたときだけエントリーを検討します。
また、値幅が狭い=利益も小さいため、無理にトレード回数を増やすと手数料やスプレッド負けにもなりやすいです。
レンジ優勢の環境では、「稼ぐ」よりも「減らさない」ことに重きを置き、無理にエントリーせず、ルール外の場面では“見送る勇気”が一番のスキルになります。
パウエル会見など材料時の注意点
重要人物の発言や会見は、相場に大きなインパクトを与えることがありますが、必ずしも“すぐ動く”とは限らないのが難しいところです。
本日のパウエルFRB議長の発言もそうでしたが、「注目されていた割に動かない」というケースは珍しくありません。
その背景には、
- 市場がすでに織り込んでいた。
- 内容が想定内で驚きがなかった。
- 他の要因(祝日やNY市場休場など)で流動性が低かった。
など、テクニカル以外の“空気感”が影響している場合が多いです。
私自身も、過去に「FOMCで絶対動くだろう」と構えていたのにノイズだけで損切り、という経験を何度もしています。
材料時はボラティリティが急激に変わる可能性があるため、
- 発言内容の確認まではエントリーを控える。
- 指標前はポジションを持たない or 小さくする。
- 出来高と反応の“温度差”を見る。
といったルールを徹底することが、感情に振り回されないためのカギになります。
自分ならこんなトレードを狙いたい(設定例)
値動きが渋い中でも「もし自分が狙うとしたら?」という視点で、具体的なトレード設定例を考えておくことは大切です。
たとえば今日のような狭いレンジ相場なら、以下のようなシナリオが現実的でした。
設定例:ドル円(147.50~147.90のレンジ内スキャル)
- 【時間足】5分 or 15分足
- 【エントリーポイント】
上限(147.85〜147.90)到達時の反転サインでショート。
下限(147.50〜147.55)到達時の反発サインでロング。 - 【根拠】
明確なレンジ帯が継続中、抜けの勢いがなく騙しも多いため逆張り有利。
MACDやRSIの乖離縮小が確認できたタイミングで入る。 - 【損切り】
明確なラインを5pipsほど抜けたらカット。 - 【利確】
中間ライン(147.70〜75)で部分決済、またはサイドへ引きつけ直し。
こういった「シナリオが明確な場面だけ入る」という姿勢を徹底することで、感情的なミストレードを減らすことができます。
来週への備えと注目ポイント
来週は米経済指標が複数予定されており、特にPCEデフレーター、ISM製造業指数、雇用統計関連のデータなどは為替相場に大きく影響する可能性があります。
加えて、パウエル議長の発言やFOMCメンバーのコメントが再び注目される可能性もあり、市場の金利観測がどう動くかを見極めることが重要です。
【来週の備えとして意識しておきたいこと】
- 日足・4時間足ベースで方向感が出る兆候があるか?
- 現状のレンジを上抜け・下抜けするようなパワーが出てくるか?
- 材料イベント前後での“だまし”に注意。
- 指標の内容ではなく“市場がどう反応するか”を重視。
また、個人的には「今週が静かすぎたぶん、来週は動く可能性が高い」と見ています。
こういう静かな週は、むしろ体力を温存しておくことも一つの戦略。
相場が動き出した時に、迷いなく入れる準備をしておくことが、来週の収支を大きく左右するかもしれません。
まとめと振り返りチェックリスト
最後に、本日のトレードを簡潔にまとめ、次に活かすための「自分用チェックリスト」を作成しておきましょう。
どんな小さな気づきも見逃さず、日々の振り返りを継続することが、長い目で見て大きな成長につながります。
今日の教訓・改善点まとめ
今日は明確なトレンドが出ないまま、狭いレンジで上下に振られる“方向感のない日”でした。
結果として、無理にエントリーした場面があったり、ポジションを保有しても「自信が持てない状態」での取引が多かったです。
収支は−3,006円と大きな損ではないものの、内容的には反省点が多い1日でした。
以下、今日のトレードから得た教訓と改善すべきポイントを整理しておきます。
【本日の教訓・改善点】
- 値動きが弱い日は“やらない勇気”が最も重要。
- エントリー根拠が薄い時は見送る判断を徹底するべき。
- レンジ相場での逆張り戦略にもっと一貫性が必要。
- 材料イベント(パウエル発言)に過剰な期待をしない。
- 感情的な「取り返そうとするエントリー」は絶対NG。
- 「トレードの質」を振り返るクセを毎日継続すべき。
今日の収支はマイナスでしたが、こうして1日をしっかり振り返ることで、次につなげる学びは十分に得られたと思っています。
明日以降に使える振り返りチェックリスト
毎日のトレードで成長していくためには、単に結果を記録するだけでは不十分です。
「なぜ勝てたか/なぜ負けたか」を言語化し、再現性のある行動に落とし込むことが何より大切です。
私自身、勝っても負けても毎晩以下のチェックリストを使って振り返っています。
この習慣が、自分のブレを小さくし、トレードの軸を安定させてくれています。
【トレード振り返りチェックリスト】
- 相場環境の把握は正確だったか?
(トレンド or レンジを見誤っていないか) - エントリーの根拠は明確だったか?
(RSI・MACD・ローソク足・ライン等で裏付けできたか) - エントリーのタイミングは適切だったか?
(早すぎ or 遅すぎになっていないか) - 損切り・利確ラインは事前に設定していたか?
(ルール通りの対応ができたか) - メンタルの影響はなかったか?
(焦り、取り返したい欲、過信など) - トレード内容を言葉で説明できるか?
(第三者に理由を説明できる=根拠があるということ) - 次に同じ場面が来たらどうするか?
(再現性のある行動に落とし込めているか)
このように振り返ることで、単なる“勝ち負け”から脱却し、「成長するトレード」に変えていくことができます。

勝っても振り返らないと、慢心が静かに忍び寄るんだよね…。
毎日コツコツやるのは地味ですが、それが最も確実な上達への道です。
FXトレードに関するよくある質問【2025年9月23日の相場を踏まえて】
Q1:なぜパウエル会見があっても相場はほぼ動かなかったのか?
A:既に市場には予想織り込み済みで、強いサプライズがなければ動意薄になりやすい。
今回も「タカ派/ハト派の新情報」が乏しく、買い/売りの注文の均衡が続いたと考える。
Q2:祝日・指標薄で値動きが悪い日は、トレードすべきか?
A:リスクが高まるので、トレード回数を絞るかノートレードにする判断も有効。
特にスキャルピングはノイズに打たれやすい。
Q3:レンジ幅(147.50~147.90)で狭い相場はスキャル戦略で稼げる?
A:レンジ内で小さな上下を狙うスキャルは可能性あるが、スプレッド・手数料と逆張りリスクを加味すると実利は限定的になる。
Q4:−3,006円の損失を次回に活かすなら何を最優先すべきか?
A:まずは「ダメなトレードの共通点」を抽出すること。
エントリー根拠が弱かった、相場の流れに逆らった、感情的だった、etc. そこを改善する。
Q5:4回のスキャル取引で損失になったが、回数が多いほど良い?
A:取引回数を増やすより、精度を上げる方が重要。勝率・リスクリワードが伴わなければ“ギャンブル”になってしまう。
Q6:私見だが、「違和感」をチャートで捉えるにはどうすればいい?
A:価格とインジケーターのズレ、反応の鈍さ、ローソク足の勢いの欠如などを「違和感」として意識化。
それを無視せずメモして振り返ることで感覚が研ぎ澄まされる。
Q7:パウエル発言時に逆張りを仕掛けたらどうなる?
A:発言内容が市場予想とズレていれば方向性が出るが、ズレなければ混乱した動き・だましが出やすい。
発言直後は手を出さずに様子見する戦略も有効。
Q8:祝日で東京市場休場の影響は海外勢の参入か?
A:国内参加者が少ないため、欧米勢の流動性やポジション調整が目立ちやすくなる。
ただ、指標や材料が少ないと動きは限定されがち。
Q9:レンジ相場を突破するためのヒントは?
A:出来高急増、価格の引きつけ、前回高値・安値のブレイク、ダイバージェンスの発生などを複数根拠で確認できれば突破の可能性が高まる。
Q10:トレードログ(コピペ)を添付する際の注意点は?
A:時間・損益・通貨ペア・エントリー理由を抜けなく記載すること。
ログ公開は客観性を伝える武器だが、誤記や見落としがないよう正確性を優先する。
本日のトレード総括と学び|収支・反省・改善ポイントの整理
- 9月23日はドル円が147.50〜147.90の狭いレンジで推移、パウエル会見でも目立った動きなし。
- 私のトレード:ドル円スキャル4回、最終収支−3,006円。
- 値動きの乏しさと判断力の甘さが損失の主な要因。
- メンタル管理と根拠強化が今後の改善ポイント。
- 継続的な振り返りとルール見直しで精度を上げていく。
本日の相場は、祝日で東京市場休場という特殊環境もあって、ドル円は147.50〜147.90の狭いレンジで推移し、夜のパウエル記者会見でも市場には大きなインパクトを与えませんでした。
その中で私が行ったスキャルピング4回のトレードは、最終的に−3,006円という結果に終わりました。
勝てなかった主な理由は、そもそもの値動きの乏しさを過小評価したこと、根拠が弱いエントリーをしてしまったこと、そして感情に流されたトレード判断です。
今後は、「違和感」を見逃さない視点、明確なトレードルール、資金管理、そして何より継続的に検証・改善する習慣を中心軸に据えることが不可欠だと改めて実感しました。
次回からは、今回の反省点を必ず改善し、より安定したトレードへと昇華させていきたいと思います。
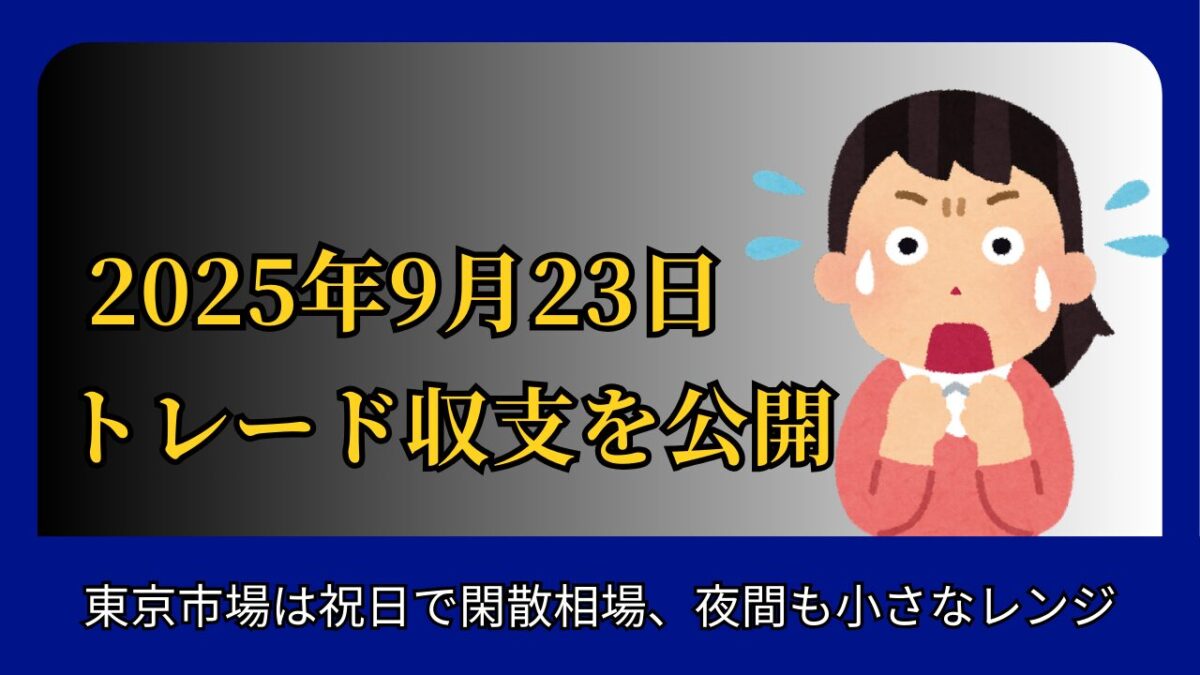




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン

