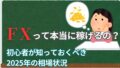2025年9月25日のドル円相場は、朝方148.80円付近で始まり、一時的に148.60円まで下落。
その後は夜までレンジ相場が続きましたが、21時30分の米経済指標発表をきっかけに一気に上昇し、149.93円付近まで到達しました。
この急変動に私も参加し、短時間での値幅を狙ったトレードを展開しました。
結果としては、前半で逆張りショートがうまく機能し利益を確保できた一方、最後のトレードで判断ミスが重なり、大きめの損切りを出してしまいました。
この記事では、9月25日のドル円の相場動向、私自身のトレード履歴と収支、勝因と反省点を整理しながら、次に活かすための改善点をまとめています。
同じような相場環境で迷う方や、指標発表前後の立ち回りに課題を感じている方の参考になれば嬉しいです。
ドル円の相場動向とその背景
2025年9月25日のドル円は、前半は静かなレンジ相場、後半は激しい値動きという、メリハリのある1日でした。
特に注目すべきは、21時30分の米経済指標発表をきっかけとした急騰局面。
朝から夜までの流れを時系列で振り返りつつ、その背景にある要因を自分なりに読み解いていきます。
朝~昼のレンジ推移と要因
2025年9月25日のドル円相場は、朝方148.80円付近でオープンしました。
その後、一時的に148.60円近辺まで下落しましたが、それ以上は崩れることなく、午前から午後にかけては再び148.80円前後でのレンジに落ち着きました。
この時間帯は特に重要な経済指標や要人発言もなく、材料難の状態が続いていたため、動きが鈍くなるのもある意味では自然な流れだったと思います。
東京市場では実需や仲値絡みのフローが中心で、積極的に方向感を出すようなトレーダーも少なかった印象です。
個人的にも、朝からチャートは開いていましたが、値動きに方向感がまったく見られず、エントリーするほどの根拠も見つからなかったため、自然と「今日は静観する時間帯かな」と判断しました。
ボラティリティが小さい中で無理に入っても、損大利小になりやすいと過去に痛感しているので、こういう“動かない時間”を見送ることも大事だと改めて感じました。

入れそうな根拠が見つからず自然に様子見へ。
21:30 米指標後の急上昇とそのメカニズム
相場が一変したのは、やはり21時30分に発表されたアメリカの経済指標でした。
それまで148.80円前後で膠着していたドル円は、一気に買いが優勢となり、わずか10~15分で149.90円近辺まで急上昇する展開に。
背景としては、発表された米指標が予想を大きく上回る「サプライズ結果」だったことが大きいです。
内容次第では米利上げ観測が強まるとマーケットは織り込んでいた可能性があり、それがドル買い圧力に直結しました。
また、同時刻に他のクロス円も上昇していたため、円売りの流れも手伝ったと見られます。
私自身もこの時間帯にモニターに張り付いており、瞬間的なボラティリティの高まりに反応して参戦。
初動は逆張りショートでしたが、急騰前の直前の戻りで一旦利確でき、うまく値幅を取れました。
ただ、思った以上にチャート上の勢いが強く、その後の“押し目買い”の流れには乗れず、様子見に切り替える場面も多かったです。
このように、ファンダメンタルズとテクニカルが一気に重なった局面では「自分の想定を超える動きが来る前提」で準備しておくべきだと実感しました。
22時以降のレンジ定着の流れ
21:30の急騰のあとは、そのまま149.90円前後での高値圏レンジに移行しました。
ここからは、チャート的にも明確な上値ブレイクは出ず、149.70~149.90円の間でのもみ合いが深夜まで続く形に。
22時以降は欧州勢の動きが徐々に収束し、NY勢の利確やポジション調整が入る時間帯でもあるため、大きな新規のトレンドは発生しにくくなります。
加えて、指標による初動でポジションを取りきったトレーダーも多かったことで、値動きが一服した可能性があります。
私もこの時間帯で再エントリーを検討していましたが、値動きのスピードが落ち着いたことで、「抜け待ちのレンジ」と判断。
ただ、最後に1回だけRSIの高止まりを見てショートを打ったのですが、これが逆に捕まる結果となり、損切りを余儀なくされました。
このミスの要因は、「動きが落ち着いた=そろそろ反転するだろう」という希望的観測が強すぎたことです。

「そろそろ反転」はただの願望に過ぎなかった。
レンジ内での逆張り自体は悪くない戦略ですが、勢いがまだ残っている可能性をもっと慎重に評価すべきでした。
私のトレード記録と収支分析
この日は昼間に大きな動きがなかったため、私は基本的に様子見スタンスで過ごしました。
ただ、21時30分を境に相場が一変し、短期的なボラティリティが一気に高まったことで、集中してトレードに参加。
ここではその詳細なトレード内容と、最終的な収支を振り返ります。
昼間は様子見:エントリー回避の判断
9月25日の昼間のドル円は、市場参加者も静観気味で、完全に“手が出しにくい相場”でした。
朝に一瞬148.60付近まで落ちたものの、そこからは148.80付近を挟んだ小さなレンジに収まり、方向感のない状態が続きました。
このような場面で、私は「トレードしない」という選択を取りました。
経験上、動かない相場に無理に入ると、スプレッド負けや“根拠の薄いエントリー”になりやすいからです。
もちろん、短期スキャルであれば小さな波を狙う戦略もあります。
ただ、ボラティリティが低く、テクニカル的にも明確なシグナルが出ていない状況で無理に入っても、トータルで見れば勝率もリスクリワードも下がる可能性が高い。
この日は「様子見」と割り切れたこと自体が、ある意味で良い判断だったと振り返っています。
待てる力もトレードスキルの一つだと、改めて実感しました。
21:30~23:00の参戦履歴と勝敗
大きく動き出したのは21時30分の米指標発表後。
ここから相場の雰囲気が一変し、ドル円は急激に149円台後半まで上昇しました。
このタイミングで私は、以下の3回のトレードを実施しました:
・21:35 ショート(逆張り)→ 利確
RSIが過熱気味、かつ直前の急伸が行き過ぎに見えたため短期ショートをエントリー。
数pipsで利確。
・21:50 ショート→ 同値撤退
高値を更新しつつも勢いが鈍化していたため、再度ショート。
ただ、方向が明確でなくなり、一旦撤退。
・22:30 ショート→ 損切り(-3,800円程度)
レンジ上限付近からの反転を狙ってショートしたものの、勢いは落ちず、ストップにかかって終了。
結果的には最初の2回で若干の利益を得られたものの、最後のショートで損切りが入り、トータルでは+2,974円という収支に落ち着きました。
各トレードの損益・ロジック比較
今回の3トレードを振り返ると、損益だけでなく“エントリー根拠の質”が勝敗を分けたことがよく分かります。
| トレード時間 | エントリー方向 | 根拠の明確さ | 結果 | 振り返り |
|---|---|---|---|---|
| 21:35 | ショート | RSI+急伸の反動 | 勝ち | チャートパターンと指標反応を的確に判断できた |
| 21:50 | ショート | 弱めの根拠 | 引き分け | 流れが止まりそうだったが、判断に迷いがあった |
| 22:30 | ショート | 希望的観測 | 負け | RSI高止まりを過信し、トレンド転換を誤読 |
ここで重要なのは、「根拠があいまいなエントリーほど負けに繋がりやすい」というシンプルな事実。
逆に、テクニカルとファンダメンタルズが一致している場面では、比較的スムーズに利確まで持っていけました。
私の今後の課題としては、「根拠が揃っていない場面ではエントリーしない勇気」をもう一段階引き上げることです。
勝因の整理
一部のトレードでは、読みがハマった部分もありました。
とくに指標直後の逆張りショートがうまく決まった場面は、自分の中でも良い判断ができたと感じています。
ここでは、収支をプラスに押し上げた「勝因」に焦点を当てて、どんな根拠が有効だったのかを掘り下げていきます。
初動の逆張りショートが奏功した理由
21:30の米指標発表後、ドル円は一気に149円台後半まで吹き上げましたが、私が最初に取ったポジションはあえての逆張りショートでした。
この選択は一見リスクが高いように思えますが、結果的に小幅ながらも利確につながりました。
この判断が奏功した要因は3つあります。
- RSIが90近くまで上昇していた(短期足)。
- 1分足・5分足ともに長い上ヒゲが出ていた。
- 急伸後の“買いの息切れ感”が明らかだった。
経験則上、「経済指標直後の急騰・急落の初動には一度反動が来る」ことが多いため、今回はその“呼吸”を読み取って短期逆張りにチャレンジしました。
もちろん、逆張りが失敗するケースも多いのですが、リスクリワードを1:2以上に設定し、あらかじめ「ダメならすぐ撤退」のメンタルで臨んでいたことが功を奏しました。
今回はその判断がうまくハマった形です。
リスク管理とエントリー精度の良かった部分
今回のトレードで自分なりに「うまくいった」と感じているのは、ポジションサイズの調整と、エントリーの間合いの取り方です。
まず、21:30以降の高ボラ局面では、あえて通常のロットよりも1段階下げてエントリーしました。
これは「値幅は出るけど、反転も早い」と見ていたためで、値幅に任せて無理に枚数を増やすのではなく、あくまで冷静にリスクコントロールした形です。
また、エントリーのタイミングも、ローソク足の実体・ヒゲ・出来高の変化をしっかり観察したうえで、焦って飛びつくことなく、「一度引き付けてから入る」意識を徹底しました。
ボラの大きい相場こそ、“入らない勇気”と“慎重な呼吸”が大切だと、改めて実感できるトレードになりました。
利益確定部分で正しい判断をできた場面
利確の判断というのは、実は損切りよりも難しい場面が多いと感じています。
今回のトレードでも、最初の逆張りショートはもっと伸ばせたかもしれませんが、あえて早めに手仕舞ったことで結果的にトータル収支は安定しました。
私が利確したのは、急騰のあとに一度大きく陰線が出て「やや息切れ感」が見えた場面。
逆張りだったので、粘れば反発される可能性も高く、「欲を出すよりも反転前に逃げる」という判断を優先しました。
もう一つ、利確のポイントで役立ったのは、1分足のボリンジャーバンドとMACDの同時転換でした。
逆張りにおいて、テクニカル指標の「合致」は確信度を高めてくれます。
この場面での利確判断は、結果的に相場の流れに飲まれずに冷静でいられたことが大きかったと振り返っています。
利確は、タイミングだけでなく「自分の中で決めたルールを守れたか」も大事ですね。
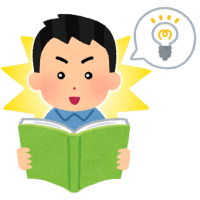
逆張りでは特に利確タイミングが命。
反省点と判断ミスの要因
勝因があれば、もちろん反省点もあります。
特に、最後に入った逆張りショートでは、判断の甘さと楽観的なエントリーが重なり、大きめの損切りを出すことになりました。
ここでは、「なぜあの判断をしてしまったのか」を冷静に見直し、次につなげる視点で振り返ります。
最後の逆張りショートでのRSI判断ミス
22時30分頃、ドル円は149.85円付近まで上昇し、私は「RSIが高止まりしている=そろそろ反転が来る」と判断して、ショートで入ってしまいました。
これが、今回のトレードで最大のミスだったと思います。
確かに、RSIは80を超えていたものの、相場全体の流れとしては「高値圏での強い持ち合い」に近く、過熱というよりは勢いを保ったままの、いわゆる“高止まり”状態でした。
RSIを単体で過信してしまい、ほかの指標(たとえばMACDやローソク足の勢い)との組み合わせ確認を怠ったのは完全な油断です。
また、指標直後のボラの大きさに慣れてしまっていて、「そろそろ落ちるだろう」という思い込みが生まれたことも影響しました。
冷静に見れば、あの場面で逆張りショートは、非常に“賭け”に近かったと言わざるを得ません。
損切り判断が後手に回った理由
損切り設定自体はエントリー時に入れていましたが、いざ価格がその付近に近づいてくると、どうしても「まだ粘れるんじゃないか」という気持ちが強くなってしまい、最初のストップを少しだけ上にずらすという悪手を取ってしまいました。
この判断が命取りでした。
結果として、その少しのズレが損失拡大につながり、当初想定していたリスク幅を超えてしまったのです。
後から振り返ると、「もう一回落ちるかも」という希望的観測に支配されていて、完全に感情>ルールの状態でした。
これがまさに、相場で負ける典型パターンの一つです。
経験者であっても、相場のスピードやノイズに飲まれると、損切り判断がズレてしまう瞬間があります。
今回の件を通して改めて、「損切りは潔く、ルールは守る」という原則の重みを痛感しました。

初期ルールを破るとメンタルも崩れる。
メンタル・欲が入った瞬間とその背景
今回のトレードでもっとも悔しかったのは、最後のショートエントリーの背景に、明らかなメンタルの乱れである“取り返したい気持ち”が混じっていたことです。
前半で小さな利確ができていたにもかかわらず、最終的に「もっと伸ばしたい」「一発で大きく獲りたい」という気持ちが芽生えてしまい、結果的にポジション判断が雑になりました。
特に、高値圏で逆張りをしたのは、RSIだけでなく「さすがに上げすぎだろう」という感覚的な判断。
つまり、自分の中で冷静なシナリオ構築ではなく、“感情”がシナリオを作っていた状態でした。
こういったメンタルのブレは、トレードルーティンの見直しや、エントリー前の“自問自答プロセス”の強化で対策できると感じています。
「このエントリーは本当にロジックに基づいているか?」と毎回自分に問うことを、次回からのルールに明記しておく予定です。
改善策と次への方針
失敗は改善のきっかけでもあります。
今回の判断ミスや利確のタイミング、ロット管理の甘さなどを踏まえ、具体的な改善策を整理しておきます。
今後同じような相場が来たときに、より機械的でブレのない判断ができるように、今のうちに方針を固めておきたいと思います。
逆張りエントリー条件の厳格化
今回の大きな反省点のひとつが「逆張り判断の甘さ」でした。
特に最後のエントリーは、テクニカルの根拠が弱いにもかかわらず、“そろそろ落ちそう”という感覚だけで入ってしまった部分が否めません。
今後は、逆張りで入る際のエントリー条件をより厳格にルール化します。
現時点で考えている条件は以下のとおりです:
- RSI単体ではなく、MACDクロス+BBタッチ+ローソク足の形が揃っていること。
- 1分足と5分足でのオーバーシュート傾向が確認できること。
- 経済指標直後は“1回目の反転”に限定し、それ以降は様子見優先。
このように、逆張りを“勘に頼る手法”から“精度で勝負する戦術”に変えていくことが、私にとっては大きな成長ポイントです。
逆張りは確かにリスクが高いですが、条件次第では有効な武器になります。
利確/トレーリングのルール再構築
今回のトレードでは、利確タイミングはそこまで悪くはなかったものの、「もう少し伸ばせたな」という場面で手仕舞ってしまった感がありました。
逆に、引っ張りすぎて損切りにかかる場面もあり、利益と損失のバランスをもっと最適化できる余地があると感じました。
そこで、以下のようなルールの見直しを検討中です:
- トレーリングストップの導入(10pips以上利益が出た時点で移動)。
- 利確ターゲットは固定ではなく、直近高値/安値ライン+価格の反応を見て判断。
- 利益がある程度伸びたら、半分利確+半分トレーリングの戦略を併用する。
要するに「利確=出口戦略」にもっと柔軟性を持たせ、機械的ではなく“再現性のある裁量”として構築していく方向です。
これにより、利益の取りこぼしも減らし、ストレスの少ない利確ができるようになると考えています。
ポジション設計・ロット管理の見直し
収支自体はプラスで終われましたが、最後の損切りでは「もう少しロットを抑えていれば、心理的ダメージは軽かったかもしれない」と思う場面がありました。
特にボラが大きい日や、指標後の荒れた相場では、普段と同じロットではなく相場の変動率に応じたポジション調整が必要だと痛感しました。

ロット設計ひとつでメンタルは大きく変わる。
今後は次のような運用ルールを検討しています:
- ボラティリティが高いとき(ATR大・指標前後)は1段階ロットを落とす。
- 想定する損切り幅をベースに、1回のトレードでの損失リスクを資金の1.5%以内に収める。
- エントリー前に「このロットで負けたときに感情が乱れないか?」を自問する。
ポジションサイズの設計は、トレードの“土台”とも言える重要部分。
これを誤ると、どれだけ正しい方向に入っても、精神面で揺らぎが出てしまいます。
“勝ち方”だけでなく、“負け方”の設計も含めて見直すことで、より安定したトレードに近づけると考えています。
まとめと今後の戦略
今日のようなメリハリのある相場では、待つ時間と攻める時間の使い分けが重要です。
ここでは、1日のトレードから得られた学びを総括し、今後の戦略と心構えを簡潔にまとめておきます。
本日の学びの要点
本日のトレードを通じて改めて感じたのは、「ルール厳守の重要性」と「感情管理の難しさ」です。
特に逆張りエントリーの際には、感覚で入るのではなく、複数のテクニカル指標を組み合わせて精度を上げる必要性を痛感しました。
また、トレード量を控えめにし、チャンスが来たときだけ集中して参戦するスタイルが自分には合っていると実感。
損切りも遅れがちだったため、損失を最小限に抑えるためのロット管理の見直しは必須課題です。
総じて「冷静な判断」と「再現性のあるルール作り」が勝ち続けるための鍵だと、改めて認識しました。
翌日以降のドル円注目ラインと狙い方
翌日以降のドル円相場では、まず149.90円付近の上値抵抗ラインに注目しています。
ここをしっかり抜けられるかどうかが、今後の短期トレンドを左右するポイントになるでしょう。
下値では148.60〜148.80円のサポートゾーンが意識されやすく、このレンジでの反発を狙った押し目買い戦略が考えられます。
トレードスタイルとしては、強い経済指標や要人発言などで一時的にボラティリティが高まる局面を狙い、反転シグナルが複数確認できたところでエントリーするのが安全かつ効率的です。
もちろん損切りは必須で、リスク管理を徹底しつつ、トレンドの継続をしっかり見極めて臨みたいと考えています。
9月25日トレードのポイントと疑問解消Q&A
ここでは、2025年9月25日のドル円相場や私のトレード内容に関して、多くの方が気になるポイントをピックアップしてQ&A形式で解説します。
当日の経済指標の影響や相場の動き、トレード戦略に関する疑問を中心に、できるだけ分かりやすく回答しています。
ぜひ参考にして、皆さんのトレード改善に役立ててください。
Q1:21:30の米指標は何で相場が動いたの?
A:雇用統計・ISMなどの主要指標が予想を上回る内容になった可能性があります。
そのサプライズ性がドル買いを強めたと考えられます。
Q2:朝の 148.80 → 148.60 円下落の要因は?
A:市場参加者の調整売り、前日の米指標の余波、流動性の薄さなどが重なった可能性があります。
Q3:なぜ昼間はエントリーを控えた?
A:レンジが狭く動意に乏しかったため、根拠が弱いトレードを避けてリスクを抑える判断をしました。
Q4:最初の逆張りショートで勝てた理由は?
A:抵抗帯とテクニカル反転のシグナルが重なった局面を狙ったからです。
複数の判断根拠を持っていた点が功を奏しました。
Q5:最後の逆張りショートで致命的なミスは?
A:RSI の過熱判断を過信し、相場の勢いの強さを見誤った点です。
また逆行耐性を超えるロットを取ってしまった面もあります。
Q6:利確のタイミングで改善できた点は?
A:部分利確やトレーリングストップの併用をもっと早く入れられたかもしれません。
急変動後に利益を伸ばし過ぎた点が反省です。
Q7:ポジションサイズ(ロット設定)に問題は?
A:最後の逆張り時にロットをやや大きく取りすぎた印象があります。
勝てていた余勢判断が過信につながりました。
Q8:収支 2,974 円は妥当な成果?
A:金額として大きくはないですが、リスクを抑えつつプラスで終えた点を評価すべきです。
中身の質で判断するべき日でした。
Q9:今後同じような相場で狙うべき時間帯は?
A:21:30 の指標発表前後は引き続き注目。
発表直後の急変動を捉える戦略を準備する価値ありです。
Q10:今回学べるメンタル面での教訓は?
A:利益局面での欲、損失局面での追いかけ癖を戒めること。
指標直後など感情が揺れやすい時間帯では、基準を平常以上に引き締めるべきです。
2025年9月25日トレード振り返りの総まとめ
- ドル円は朝~昼レンジ後、21:30で急上昇 → 夜間レンジへ。
- 昼間は様子見、21:30以降に集中参戦。
- 初動ショートで利益を取れたが、最後に逆張りで判断ミス。
- RSI 過信、損切り遅れ、ロット過大が反省点。
- 次回に向けて、エントリー基準強化・利確戦略拡充・ロット管理見直し。
今回のトレードは、比較的動きの少ない時間帯を安全に見送り、波が立ち始めた時間帯に集中投資した戦略が部分的には機能しました。
しかし、最後の逆張りショートでの判断ミスが、せっかくの利益を削る形となってしまいました。
RSI の過熱判断を甘く見たこと、勢いを過小評価したこと、そしてロット設定の甘さが主な敗因です。
そこから得た教訓を次に生かすべく、逆張り判断を複数指標で裏付ける、利確戦略を多層化する、ロット管理を保守的にする、といった改善方針を確立したいと思います。
今回の収支 2,974 円は小さな成果ですが、内容を正しく見直すことで“質のある勝ち癖”へとつなげていきたいです。
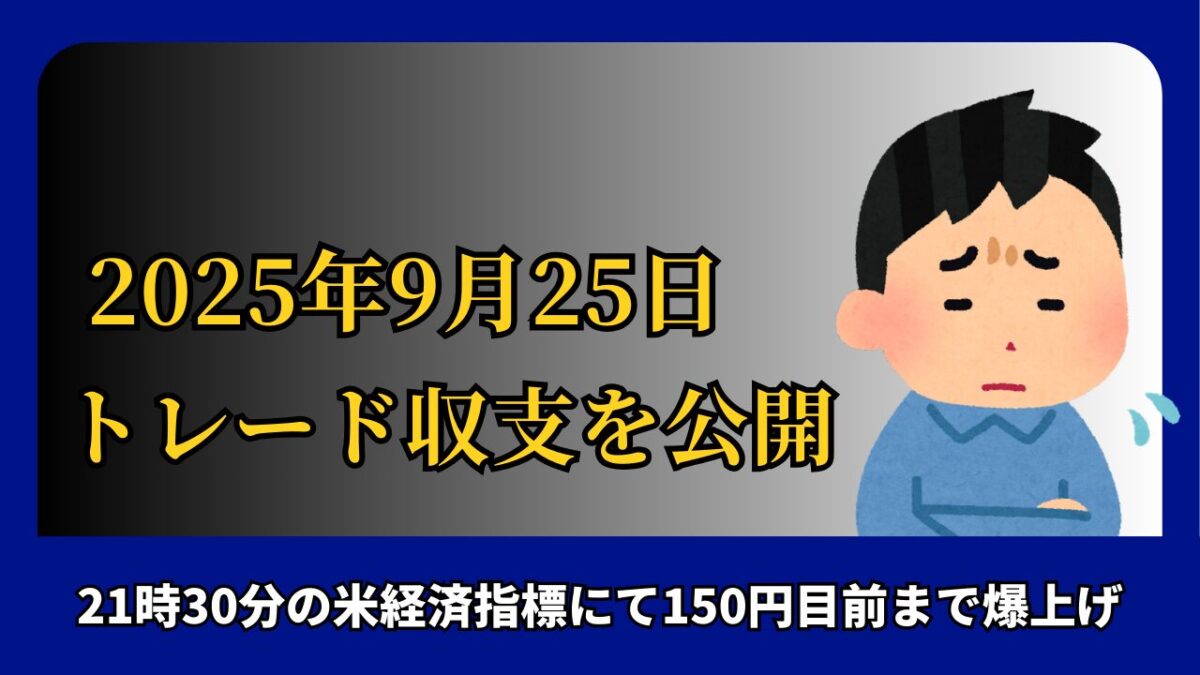




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン