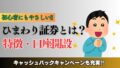2025年10月10日のFXトレードを振り返ります。
この日はドル円のみでの取引でした。朝は153円付近から始まり、しばらくして153.27円付近まで上昇。
その後は少しずつ下げていき、夜中にはトランプ元大統領による中国への100%関税発言もあり、大きく動く1日となりました。
結論から言うと、今日の収支は‑224円。
大きく勝ったわけでも負けたわけでもないですが、相場の流れや自分の対応には反省点もいくつかあります。
今回もトレード結果をもとに、チャートの動きやエントリータイミング、戦略の良し悪しをしっかり振り返っていこうと思います。
また、153円付近がひとつの天井になったかもしれないという印象もあり、週明け月曜の窓開けも気になるところ。
この記事では、当日の値動きやトレードの内容、今後に向けた視点まで、できるだけわかりやすく整理してみました。
少しでも何かの参考になれば嬉しいです。
トレード結果と全体の振り返り
10月10日のFXトレードは、ドル円1本に絞ってエントリーしていました。
値動きとしては、朝の上昇から夜にかけての下落、そして終盤の急落という流れ。
トレード自体は控えめな内容で、収支は‑224円でしたが、レートの変動が大きかっただけに、いろいろと学びも多かった1日です。
ここでは、当日の相場全体の流れと、自分のトレードの結果について簡単に振り返っていきます。
10月10日のドル円相場の流れと特徴
この日のドル円は、朝の東京時間にかけて153円付近でスタートしました。
やや強めの買いが入り、一時は153.27円まで上昇する場面も。
ただ、その後は徐々に頭が重くなり、ロンドン時間にかけてはジリジリと売りが優勢に。
決定的だったのは、NY時間後半に入ってから。
トランプ元大統領による「中国製品に100%の関税をかけるべきだ」との発言が伝わると、一気にリスクオフムードが強まり、ドル円は急落。
深夜0時前後には151.50円付近まで落ち込む展開に。
その後は多少戻す動きも見られましたが、相場全体としては上値が重く、151円台後半から152円付近でのもみ合いが続き、引け間際には再び下落。
6時前には151.14円付近まで落ちて終了しました。
上下で約2円以上の値幅がある、かなり動きのあった1日だったと思います。

記録しておきたい日になりました。
当日のトレード収支と損益要因

この日はドル円のみを対象に数回のトレードを行いましたが、最終的な収支は−224円。
大きな損失ではありませんが、プラスで終わるチャンスもあっただけに、内容としてはやや悔しい結果になりました。
主な要因としては、朝の上昇局面での押し目買いが早すぎて、天井を掴んでしまったこと。
それに加えて、下落局面での戻り売りも中途半端な位置でのエントリーになってしまい、利確が甘く、利益を伸ばせませんでした。
また、トランプ氏の発言が出た瞬間はノーポジだったものの、その後の急反発に反応して飛びついたところがあり、結果として逆行を食らう場面もありました。
これが地味に響いています。
勝ちパターン/負けパターン別の振り返り
勝ちパターンとしては、東京時間に152.80円台で拾った押し目買いが、153円台前半まで伸びた局面です。
ただし、すぐに利確せずに粘ったため、その後の反落で伸ばしきれなかったのが課題。
利確ポイントをもっと意識すべきでした。
負けパターンは、やはりNY時間の急落前後での判断ミス。
反発を狙って入ったロングポジションが伸びず、損切りラインにかかって終了したのが一番痛かったです。
加えて、ロンドン時間帯の中途半端な戻り売りも、トレンド転換の見極めが甘く、利が乗らないうちに建値付近で撤退という感じでした。
こうやって振り返ると、エントリーよりも決済と粘りすぎの調整が課題かなと思います。
ついビビって、小さく取って、小さく負ける、いわゆる「チキントレード」になってしまっていたので、次はしっかりルールを守っていきたいですね。
時間帯別チャート分析と戦略検証
値動きの激しかった10月10日ですが、時間帯ごとにチャートを見ていくと、それぞれ違った特徴があったのが印象的でした。
東京時間、ロンドン時間、そしてNY時間後半と、それぞれのタイミングでトレード戦略の組み方も変わってきます。
ここでは、相場の時間帯別の動きと、自分がどんな戦略を立てていたかを振り返ってみます。
東京/ロンドン時間帯でのドル円の動き
朝の東京時間は、比較的おだやかな上昇からスタートしました。
153円を少し超えるあたりまで上値を試す展開で、153.27円あたりがこの日一番の高値になりました。
ここまでは押し目買いを狙うトレーダーも多かったと思いますし、実際に私もその流れに乗ろうとエントリーしていました。
ただ、ロンドン勢が入ってくる時間帯になると、雰囲気が少し変わりました。
ジリジリと売りが入りはじめ、値が伸びにくい状態に。
ここで「高値更新は難しそうだな」と感じたんですが、押し目だと判断してポジションを持っていたこともあり、判断が遅れました。
このあたりのタイミングで早めにポジションを解消していれば微益で終われたのに、利確を引っ張りすぎて結局下げに巻き込まれるという、よくあるパターンでした。
東京時間の穏やかな上昇とロンドン時間の売り転換、このギャップをもう少し意識しておくべきでしたね。
NY時間(終盤)で起きたトランプ関税発言のインパクト
相場が一気に崩れたのは、やはりNY時間の終盤です。
日付が変わる直前、トランプ元大統領が中国に対して「100%の関税を課すべきだ」と発言したというニュースが流れ、ドル円は一気に急落。
直前まで152.40円付近で安定していたのが、151.50円あたりまでズドンと下げてきたので、一気に緊張感が高まりました。
私はこのタイミングではポジションを持っていなかったので直接の被害はなかったですが、その後の反発を狙ってエントリーしたことで軽く踏まれました。
値動きが荒くなると「チャンス」と思ってしまうのですが、今回のような発言系ニュースでは一方向に振れすぎることが多く、反発狙いの逆張りは危険だと改めて実感しました。
ニュース直後は静観、これが基本ですね。
引け間際の急落タイミングと対応策
一日を通して振れ幅が大きかった10月10日ですが、最後の最後、引け間際の動きがまた激しかったです。
深夜3時~5時台までは151.60~152円付近で落ち着いていたのに、6時直前になってから一気に151.14円付近まで下落しました。

引け前の乱高下、あなたならどうする?
このタイミングはポジションを持っていなかったのでトレードとしては何もできていないんですが、チャートを見ていて「これは動きすぎだろ…」と感じました。
おそらく短期筋の仕掛けや、週末ポジション調整の影響もあったのではないかと思います。
もしこの動きに巻き込まれていたら、おそらく損切りか含み損で精神的にキツくなっていたと思うので、むしろ「ノーポジで見ていた自分を褒めてあげよう」とすら感じました。
引け間際はスプレッドも広がるし、流動性も落ちて不安定になる時間帯。
トレードを控える、もしくは逆指値をしっかり置いておくというのは、やはり大事なルールだと改めて確認できました。
戦略・手法の振り返りと改善点
トレードの良し悪しは、結局のところエントリーと決済、そして損切りや資金管理の判断にかかってきます。
今回は大きく負けたわけではないけれど、結果としてマイナスだったのは、どこかに改善できるポイントがあったということ。
ここでは、自分なりの戦略や判断をどう見直すか、冷静に整理してみました。
エントリーと決済タイミングの精度検証
10月10日のエントリーは、方向性の初動を見てすぐに入ったものが多かったです。
例えば朝の上昇局面では、「これは上に行くだろう」と判断して早めにエントリー。
ただ、結果としてはその後の伸びが弱く、利確タイミングを逃して利益を削ってしまいました。
逆に、NY時間の下落を見てから入ったショートは、勢いに乗れずに建値付近で撤退。
どうも「動き始めに乗る」という意識が強すぎて、値動きの勢いやタイミングを見極める前に入ってしまうクセが出ていました。
決済についても、伸びているのに粘りすぎて戻される、伸びないのに期待して放置する、という典型的な「迷い」が出ていた感じです。
特に反発のタイミングを見極める冷静さが足りなかったなと反省しています。
損切り・利確設定の振り返り
この日はあまり大きなロットではなかったこともあって、損切り設定はやや緩めにしていました。
ただ、それが裏目に出てしまい、ちょっとした逆行で耐えてしまった場面もありました。
結果として、−224円という小さなマイナスで済みましたが、これは運が良かっただけかもしれません。
逆行したときの「まあ戻るだろう」という甘えが、今後もっと大きな損失につながるリスクにもなるので、やはり事前に決めた損切りラインはしっかり守る必要があります。
利確も似たような感じで、欲張ってしまう場面がありました。
+10pipsぐらいで一度利確できたのに「もう少し伸びそう」と思って放置したら反転、結果建値に戻って終了。
何回も同じことをやっているので、ここは自分ルールの徹底が課題ですね。
リスク管理/資金管理の見直し
今回のように少額トレードをしていると、つい「多少逆行しても大丈夫」と思ってしまいがちですが、これが一番危ない考え方だと感じました。
ロットが小さいからといってルールを緩めるのは、資金管理の観点では完全にNGです。
特に今回のように不安定な相場では、ちょっとしたニュースや発言で一気に動きます。
リスクを最小限に抑えるには、エントリー前の想定損失を具体的に数字で把握し、1回のトレードで資金全体の○%以上はリスクに晒さない、という管理が必要だと実感しました。
また、週末に近づくほどボラが増えることもあるので、「週末の持ち越しは原則しない」というルールも改めて徹底しようと思います。

甘い資金管理、気づいたときには遅い。
翌日以降に向けた展望と注目ポイント
相場は1日で完結するものではなく、流れはその先にもつながっていきます。
10月10日の動きから見えてきたのは、153円付近の上値の重さと、深夜にかけての下落圧力。
それに加えて、月曜の窓開けがどの程度のギャップになるのかも気になるところ。
ここでは、週明けに向けて意識しておきたいポイントや、今後の戦略について少し考えてみました。
月曜の窓開けリスクと対応方針
今週のように金曜終盤で大きな下落があった場合、週明け月曜日の「窓開け」がどうなるかは毎回気になるところです。
特に今回はトランプ発言という突発的なニュースが絡んでいるので、その影響が週明けまで引きずるかもしれません。
こういったケースでは、週明けのオープン直後に変にポジションを持つと、スプレッドが広がったタイミングで滑ったり、意図しない損失が出たりすることがあります。
特にロットを張っていたら、そのダメージは大きいです。
なので、月曜は基本的に様子見スタートで、窓の方向とその後の動きをしっかり見てから入るつもりです。
窓埋め狙いは王道ですが、最近は「埋めずに走る」パターンも増えているので、あまり決め打ちはせず、慎重にいきます。

“月曜窓”どう動く?待つ勇気が鍵!
153円近辺が“天井”になった可能性は?
10月10日の高値が153.27円付近だったことを考えると、現時点では「153円が重たい」という印象が強くなっています。
過去にもこのあたりでは何度か売りが入っていて、ちょっとしたレジスタンスゾーンになっている感じです。
この日も一度は153円を超えましたが、そこから素直に上抜けしていかずに押し戻されたというのは、やっぱり売り勢力の存在感を感じさせます。
短期的には153円前後が天井となって、上値を抑える展開が続くかもしれません。
ただ、地政学リスクや要人発言など外部要因であっさりブレイクすることもあるので、「153円=絶対の壁」と思い込まないようには注意が必要ですね。
次にこの水準を試しにいくときは、突破力があるかどうかをしっかり見極めたいです。
今後のドル円見通しと戦略仮説
現状のドル円は、やや方向感に欠ける状態に見えます。
短期的には下落トレンドのようにも見えるし、中長期で見ると上昇トレンドがまだ生きているようにも感じます。
つまり、どちらにも動きやすい「レンジ」または「調整フェーズ」に入っているというのが正直な印象です。
今後の戦略としては、無理にトレンドフォローを狙うよりも、重要な価格帯での反発や反転ポイントを狙う「逆張り+確認型」のスタイルが合っている気がします。
特に152円と151円のキリ番は意識されやすいので、この辺りでのサポレジの切り替えを見ながら、慎重にエントリーしていきたいところです。
ファンダ要素も不安定な状況なので、テクニカルだけで判断せず、要人発言や地政学ニュースにも常にアンテナを張っておくのが大事ですね。
10月10日の為替相場の動きや背景に関するQ&A集
10月10日のドル円相場は値動きも大きく、トレードの難易度も高めな一日でした。
この記事では、その日のできごとや相場の背景について、FX初心者から中級者の方が「こういうこと気になるかもな」と思った疑問をピックアップして、Q&A形式で整理してみました。
経済指標の未発表や要人発言など、少しイレギュラーな要素もあったので、同じような局面での参考になると嬉しいです。
Q1:なぜ10月10日は米国の指標発表がなかったのですか?
A:この日は米国政府の閉鎖(シャットダウン)により、連邦機関の多くが機能停止しており、本来予定されていた経済指標が発表されなかったためです。
閉鎖中は雇用統計やCPIなどの公式統計が出されず、市場は代替データや発言に頼る展開になりました。
Q2:トランプ氏の中国への100%関税発言は市場にどう影響を与えましたか?
A:この発言はリスク回避志向を刺激し、ドル円は一気に下落しました。
特に151.50円近辺まで押すほどのインパクトを与え、終盤の相場の流れを大きく変えました。
Q3:153円近辺を上限(天井)と見る根拠は何でしょうか?
A:朝始値近辺から153円前後まで上昇した後、反転下降したこと、さらにその後の下落の勢いを考えると、心理的な抵抗水準または売りが集中するゾーンであった可能性があります。
ただし、過去の高値ラインや移動平均線、水準訂正などのチャート指標と照らし合わせて確認するのが確実です。
Q4:損益がたった‑224円という小さな金額になった原因は?
A:取引ロット数が小さい、ストップ幅/利確幅が控えめ、または多くのポジションが微益・微損で終わった可能性があります。
また、利食い遅れや逆行に振られた際の含み戻し対応などが要因になっていたかもしれません。
Q5:引け間際の急落(151.14円付近まで)をどう捉えるべきですか?
A:当日引け前は流動性低下/ショートカバーやニュース発言による急変動リスクが高まる時間帯です。
このような急落には、ポジションを持ち越さない戦略や逆張り対応を控えるルールが有効になります。
Q6:月曜日の窓開けリスクをどう警戒すればいい?
A:週末を挟むと材料が溜まりやすく、窓を開けて始まる可能性があります。
対策としては、週明け前にシナリオを複数用意し、指値・逆指値オーダーを先にセットしておくのが有効です。
Q7:ドル円以外の通貨でトレードしなかったのはなぜ?
A:当日はドル円相場の動きに集中したかった、あるいは他通貨ペアで動きが明瞭でないと判断した可能性があります。
また、流動性やスプレッド面でドル円が最も扱いやすかったという判断もあり得ます。
Q8:当日のボラティリティ指標(ATRなど)はどうでしたか?
A:正確なATR値はチャートソフト等で確認する必要がありますが、153円 → 151円台への大幅なレンジを考えると、通常よりかなり大きな値幅があった日と見られます。
ボラティリティが高い日は、ストップや利確幅を柔軟に設計する必要があります。
Q9:取引量や出来高の傾向はどう見られましたか?
A:終盤の急落やトランプ発言直後など、重要ニュースのタイミングでは出来高が膨らむ傾向があります。
逆に閑散時間帯(深夜帯など)は薄い流動性でスリッページに注意が必要です。
Q10:今後似たような展開を狙うにはどんなアプローチが有効ですか?
A:短期レンジ内での逆張り・ブレイクアウト戦略、あるいはニュースリスクを見越した事前仕込み(但しリスク大)などの戦略が考えられます。
また、重要発言前後はポジションを小さめにして対応力を高めるのもひとつの手です。
10月10日FXトレードの総括と反省点のまとめ
- 朝は153円近辺からスタートし、一時153.27円付近まで上昇。
- その後徐々にレートを下げ、深夜のトランプ関税発言で151.50円近辺まで急落。
- 一時152.18円まで反発後、151.60円~152.00円あたりでレンジ推移。
- 引け前には151.14円近辺まで急落して一日を終える。
- 当日のトレード通貨はドル円のみ、収支は‑224円。
- 指標発表は米国政府機関閉鎖の影響で中止・延期。
- 153円近辺が上値抵抗ラインとして意識された可能性あり。
- 月曜の窓開けリスクを警戒すべき展開。
10月10日は、ドル円相場の振れ幅が大きく、特に深夜のトランプ関税発言が強いインパクトを与えた一日でした。
朝の153円台から下落モードに転じ、最終的には151円台前半へと急落。私自身のトレードは‑224円という結果に終わりました。
振り返ると、エントリー・決済の精度、損切り設定、相場急変への対応力といった部分に課題が多く見つかりました。
特に終盤の急変動ではポジションを持ち越さない心構えや逆張り制限が必要だったと感じます。
今後は、153円近辺を天井水準の候補として頭に入れつつ、週明けの窓開けリスクも想定したシナリオを事前整理しておくことが重要だと思います。
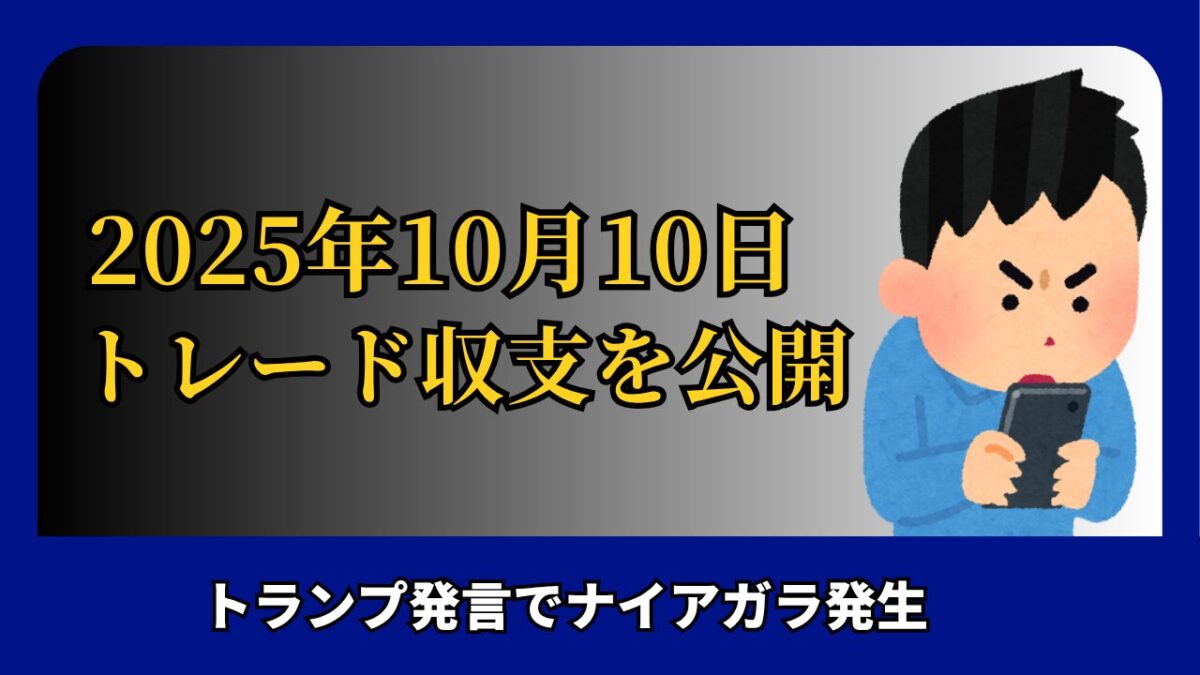




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン