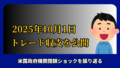10月14日のFXトレードは、結論から言うと−16,479円のマイナス収支で終わりました。
朝のドル円上昇から午後の反落、そして夜の再浮上と、そこそこ動いた一日ではありましたが、うまく波に乗り切れずに反省の多いトレードとなりました。
特に不慣れなユーロドルとポンド円での無理なエントリーが足を引っ張り、ドル円でのプラス分を帳消しにしてしまったのが痛かったです。
とはいえ、相場環境としては学びの多い一日でもあり、値動きや背景材料をしっかり整理することで、次に活かせるヒントも見つけられました。
この記事では、10月14日の収支詳細やトレード内容を振り返るとともに、ドル円を中心とした為替相場の動き、米国指標の発表中止や要人発言の影響など、当日の相場背景を丁寧にまとめていきます。
自分の振り返りも兼ねて、できるだけリアルな内容をお届けできればと思います。
- 2025年10月14日トレード収支と概要
- 10月14日のドル円レート推移と動きのポイント
- 相場背景/材料分析
- 各通貨ペア別の戦略・反省点
- 今日の学び & 次回への戦略
- 10月14日トレードで気になる疑問をスッキリ解決!
- Q1:なぜ 10月14日には主要な米国指標の発表がなかったのか?
- Q2:パウエル議長の発言があってもドル円に大きな動きがなかったのはなぜ?
- Q3:15時から 151.60円付近まで下落した場面で何が売り圧力につながったのか?
- Q4:9時台の上昇で152.60円付近まで達した背景は?
- Q5:なぜドル円は深夜~朝方にかけて151.60~151.80円のレンジに収まったのか?
- Q6:米金利見通しの変化は当日のドル円にどのように影響したか?
- Q7:日本側の要人発言や政策観測は当日の値動きに影響したか?
- Q8:ユーロドル・ポンド円を扱ったがなぜうまくいかなかったのか?
- Q9:この日の収支-スか?
- Q10:10月14日の動きを踏まえて、今後ドル円で意識すべき水準はどこか?
- 今日の取引から学ぶ重要ポイントまとめ
2025年10月14日トレード収支と概要
この日のFXトレードは、1日を通して見ても、「うまくいかなかった日」でした。
収支は−16,479円。
メインで触ったドル円は比較的読みやすい動きをしていたのに対して、つい手を出してしまったユーロドルとポンド円でミスが続き、トータルではマイナスに。
本来ならドル円に絞ってじっくりやるべきだったのに、ちょっと「取り返したい」気持ちが出てしまったり、慣れてない通貨ペアでチャレンジしたくなったり…。
そういう小さな判断ミスが積み重なって、結果に表れてしまった感じです。
とはいえ、何が良くて何が悪かったのかを冷静に振り返っておくことは、次に同じ失敗を繰り返さないためにも大切だと思っています。
ここでは、当日の収支の内訳や使った通貨ペアごとの結果、トレードの流れや反省点をまとめていきます。
当日の総収支と通貨ペア別トレード結果

この日の最終的な収支は、-16,479円。
途中までは小さなプラスで推移していたんですが、午後からのポジションが裏目に出て、徐々に苦しい展開に。
トレードの軸としてはドル円を中心にしていて、そちらでは多少うまく立ち回れた部分もあったんですが、残念ながらそれを打ち消すような結果に終わりました。
通貨ペアごとの内訳は以下の通りです:
- ドル円:+5,200円くらい
(利確多め、小ロットでコツコツ) - ユーロドル:−7,800円くらい
(逆張り狙いが失敗) - ポンド円:−13,000円くらい
(ボラの大きさに翻弄され損切りが遅れた)
ポンド円に関しては、正直慣れてないのに値動きだけで「チャンスかも」と飛び込んだのが大きな反省点です。
ボラがある分、判断ミスが大きな損失につながってしまいました。
ユーロドルも普段より感覚が合わず、入っては微損、もしくは損切り、という悪循環に。
トータルで見ると、得意なドル円だけやっていれば「普通の日」くらいで済んだかもしれません。
欲張って広げすぎた結果のマイナスだったなと、つくづく実感してます。
ドル円メイン、ユーロドル・ポンド円のトレード比率
この日は、トレード全体の約7割以上がドル円。
残りがユーロドルとポンド円でした。
正直、朝からの動きを見て「今日の主役はドル円だな」と思っていたんですが、午後にかけてボラティリティが落ち着いてきたタイミングで、つい他の通貨ペアに目移りしてしまいました。
- ドル円:約70%
(慎重に回数多め) - ユーロドル:約20%
(少ないけど負けが重い) - ポンド円:約10%
(数回のトレードで大きめのマイナス)
ドル円は、朝の上昇〜午後の下落〜夕方の戻しまで、比較的読みやすい値動きだったこともあって、入りやすかったです。
ただ、値幅はそれほど出なかったので、小さな利確を積み重ねるスタイルに。
逆に、ユーロドルやポンド円に手を出したのは、完全に「動きがあるから」「取り返したいから」といった気持ちが先行してしまってました。
結果的に、そこが足を引っ張ってしまった形ですね。冷静さを欠いたトレードはやっぱりうまくいかない。
不慣れペアが収支を圧迫した状況(ユーロドル/ポンド円での失敗例)
今回の最大の反省ポイントは、間違いなく「ユーロドルとポンド円に手を出したこと」でした。
ユーロドルは、一見レンジに見えた動きが一気にブレイクして逆指しが連発。
エントリーの位置が中途半端だったせいで、損切りがどうしても遅れがちになってしまいました。
ポンド円に関しては、動きが激しいのはわかってたけど、タイミングが合えば大きく取れるという期待があって、ちょっと賭けに出た部分もあります。
でも結果的には上下に振られて、利確できずに損切りの連続。
「慣れてないのにチャレンジするな」というのは以前から自分に言い聞かせていたのに、相場が動いてるとつい忘れてしまう…。
今回もその悪い癖が出てしまいました。
こういう日は、「得意な通貨ペアだけ」「得意な時間帯だけ」「得意なパターンだけ」に絞ることが本当に大事だと痛感します。

今日の反省は次に生かす。焦らずコツコツ得意パターンで勝負しよう!!
使用した手法、時間帯、エントリー・決済スタイル
この日は、ほとんどが短期のデイトレード〜スキャルよりのトレードスタイルでした。
基本は5分足ベースで、価格帯やサポレジの反発を見て入るシンプルなプライスアクション中心の戦略です。
エントリーは以下のような時間帯が多かったです:
- 朝9時〜10時台(東京時間スタート)
- 14時〜16時台(欧州勢の入り始め)
- 21時〜23時台(NY時間)
東京時間は、152.20円からの上昇にうまく乗れて一部利確。
午後の下落でもショートを試しましたが、ポジションを粘りすぎて利益が伸びきらず。
夜の時間帯は方向感が乏しく、狭いレンジの中で無理に仕掛けたことで連敗につながりました。
とくに深夜帯は、完全にノートレでもよかったかもしれません。
決済スタイルは、一応「損小利大」を意識してましたが、負けが続くとどうしても利を伸ばすのが怖くなってしまって…。
利確が早くなり、損切りが遅れるという最悪のパターンに入りかけてた気がします。
10月14日のドル円レート推移と動きのポイント
10月14日のドル円相場は、朝から夜にかけて方向感のある値動きとレンジの切り替わりが印象的な一日でした。
東京時間には買いが優勢となり、152円台中盤まで上昇。
その後、午後にかけて下落し151円台後半まで押し戻されるなど、値幅としてはしっかりと動いた一日だったと思います。
注目されていた米経済指標が政府機関の閉鎖で発表されず、材料不足の中で、チャート主導のテクニカルな展開が目立ちました。
夜にはパウエル議長の発言もありましたが、内容に大きなサプライズはなく、深夜から朝方までは落ち着いたレンジ推移が続きました。
ここでは、時間帯ごとにドル円がどう動いたのか、実際の値動きを振り返りながら、自分のトレード目線から見た注目ポイントや学びも交えてまとめていきます。
朝152.20円付近からのスタート、その後9時台への上昇要因
朝の時点でドル円は152.20円付近からのスタート。
東京市場が始まるにつれて、じわじわと買いが入り、9時台には152.60円手前まで上昇していきました。
この時間帯は毎日同じように動くわけじゃないけど、東京時間の入りたては実需のフロー(輸入企業のドル買いなど)でドルが買われやすい傾向があります。
おそらくこの日もその影響があったんじゃないかと。
また、前日の海外市場でドルがやや強含んでいた流れを引き継いだという面もあって、9時過ぎからの買いは比較的素直な上昇でした。
自分もこのタイミングで短期ロングを仕掛けて、小幅だけど取れた場面がありました。
こういう「東京オープン後の流れに乗る」って、やっぱり鉄板ですね。過度に逆張りしないことが大事だなと再確認しました。
9時台~15時にかけて152.60 → 151.60円への下落、要因と背景
9時台の高値をつけた後は、午後にかけてじわじわと下落トレンド入り。
結局、15時前後には151.60円付近まで下がっていきました。
この下げの要因ははっきりしたニュースが出てたわけじゃないけど、目立った材料がなかったことが逆に売りやすさにつながったのかも。
加えて、ドル円が数日間高値圏にいたこともあって、利益確定の売りやショート勢の仕掛けも出てきたのかもしれません。

高値圏での利確売りとショート仕掛け、見逃さずに対応できたのは収穫。
ここは自分も「流れが変わったな」と感じて、何度かショートを試したんですが、やや早めに入りすぎてしまい利が伸ばせなかったです。
焦らず引きつけてエントリーしていれば、もっと取れた場面でしたね。
午後の時間帯は、欧州勢の参入も近くなることから動きが読みにくくなりがちです。
欲張らず、切るところはちゃんと切る判断力が求められる場面でした。
15時~18時の戻り、152.15円付近までの上昇理由
午後の安値をつけたあとは、15時以降から18時台にかけて再び上昇。
ドル円は再び152.15円付近まで戻しました。
これはよくある「戻り売りを試すタイミング」でもありますが、この日は思ったよりも素直に戻してきた印象。
欧州勢がドルを買い戻した可能性もありますし、日経平均の下げ止まり、米先物の安定など、リスク要因が落ち着いたのも影響したかもしれません。
この動きにはちょっと乗り遅れてしまい、エントリーのタイミングを測っている間に上がってしまったので、個人的には静観していた時間帯でした。
ただ、方向感があったので、こういう時間はチャートに張り付き続けておけばよかったなと後悔もあります。
「動く時間に動く通貨で勝負する」――言うのは簡単だけど、やっぱり実行するのは難しい。
深夜~翌朝にかけてのレンジ151.60~151.80円の攻防
夜の時間帯から深夜~朝方にかけては、151.60~151.80円の狭いレンジでの推移となりました。
まさに「動かない時間帯」。
この原因ははっきりしていて、まず材料が何も出なかったこと。
そして本来なら注目されるはずの米国経済指標が、政府機関閉鎖の影響で発表中止。
これによって市場に方向感がまったく出ず、手控えムードが広がった形です。
さらに、深夜1時過ぎにはパウエル議長の発言がありましたが、内容に目新しさがなかったこともあって、相場の反応はほぼゼロ。
動く材料がないと、短期勢も手を出さなくなり、こうした狭いレンジになりがちです。
ここで自分は軽くスキャルを試したんですが、手数が増えるだけで結果が出ず、むしろスプレッド負け。
完全に「やらなくてよかった時間帯」でした。
こういう場面こそ「見送り」も立派なトレードなんだと再認識しました。
相場背景/材料分析
この日は、テクニカルな動きが目立った一日でした。
というのも、本来注目されていたはずの米国経済指標が発表中止になったため、相場が「材料待ち」ではなく「チャートだけを頼りに動く」状況に。
そして、夜にはパウエルFRB議長の発言があったものの、こちらも想定内の内容だったことから、マーケットの反応は非常に限定的でした。
つまり10月14日は、「材料がない=動かない」ではなく、「材料がないからこそチャートに素直な動きになった」側面が強い日だったという印象です。
ここでは、当日の材料や指標関連、要人発言がどう為替市場に影響を与えたかを整理していきます。
発表予定だった指標の中止:なぜ米国政府機関閉鎖で発表されなかったか
本来であればこの日、いくつかの米国系経済指標の発表が予定されていました。
特に注目されていたのは小売売上高やNY連銀製造業景気指数など。
しかし、米政府機関の一部閉鎖の影響により、これらの指標はすべて発表延期に。
この影響で、ニューヨーク時間に入っても明確な材料が出ず、市場は「様子見モード」に。
特に機関投資家やヘッジファンドのような大口勢は、こういう不確実な状況では積極的に動きません。
その結果、夜間は方向感のないレンジ相場になってしまったわけです。
指標発表がないだけで、ここまで相場のボラティリティが変わるのかと、改めて経済指標の重要性を実感しました。
パウエル議長の発言と市場の反応(または反応できなかった理由)
この日の深夜、FRBのパウエル議長による講演がありました。
マーケットとしては「タカ派な発言があるかも」と警戒感もあったんですが、実際の内容はこれまでの路線をなぞるような内容でした。
具体的には、
- インフレ抑制への姿勢は継続
- 金利はデータ次第で動く可能性がある
- ソフトランディングを目指す
といった発言が目立ち、特に目新しさはなく、マーケットの反応もほぼゼロ。
ドル円は発言前後でやや上下する場面もありましたが、151.70円台で安定した動きに戻っていきました。
為替相場としては完全に「無風通過」だったと言えるでしょう。
こういう場面では「期待外れで反応薄」というパターンも多く、過度にポジションを取るよりは一歩引いて様子を見る姿勢が正解だったなと感じました。

市場は新しいサプライズを待っていたけど、今回は静かな展開に終わったね。
米金利見通し、連邦準備制度と市場期待の変化
10月14日時点では、FRB(米連邦準備制度)の金融政策に対する市場の期待は、かなり織り込みが進んでいる状況でした。
すでに年内の利上げはほぼ打ち止めという見方が広がっていて、市場参加者の関心は「いつ利下げが始まるのか」に移っています。
CME FedWatchによれば、この時点で2026年前半にかけて2回以上の利下げを織り込む動きも見られました。
ただし、FRBの姿勢としては「インフレが鈍化してきてはいるが、完全に安心できる水準ではない」というスタンス。
つまり、利下げに踏み切るにはまだ慎重というのが本音です。
このため、パウエル議長の発言も含め、何かよほどの材料がなければ、金利の方向性が短期的に大きく変わることはなさそうです。
こうした状況下では、「ドル高材料がやや鈍化している一方、ドル売りに転じるほどの弱気材料もない」という、方向感の乏しい地合いが続きやすくなります。
まさに10月14日の値動きは、その典型だったと感じました。
日本側の動き(輸出、日銀見通し、要人発言など、あれば)
日本側の材料は、この日もそこまで目立った新情報はありませんでしたが、為替に関連する構造的なテーマが相場の背景として意識されていたように思います。
たとえば、日銀による政策スタンスの変化期待については、10月中旬時点で一部市場関係者の間から「マイナス金利解除が年内にもあり得る」といった観測が再浮上していました。
もっとも、これは織り込み度も限定的で、明確な声明や発言があったわけではありません。
また、輸出企業による実需のドル売り(=円買い)が、午後からのドル円下落を後押しした可能性もありそうです。
特に152円を超える水準では、企業サイドからの売りが入りやすいとの見方も根強く、それが151円台への押し戻しにつながった面もあるでしょう。
要人発言については、この日は特に為替に直接影響を与えるような日銀関係者のコメントは見られませんでした。
全体として、日本側の動きは静かではありましたが、「為替介入水準として意識されるゾーン(152円台)」に差し掛かっていたこともあり、警戒感が相場の上値を抑える一因になったように感じます。
リスク要因・外部環境とのリンク(株式、債券金利、リスクオフなど)
為替相場は単独で動くことは少なく、株式市場や債券市場、リスクオフ要因とも密接に連動しています。
10月14日もその例外ではなく、為替だけ見ていると気付きにくい背景がいくつかありました。
まず、米国債利回り(長期金利)はこの日、やや落ち着いた動きをしており、ドル円の上昇を後押しする材料にはなりませんでした。
金利が上がらないと、ドルの買い材料としては弱くなるため、ドル円の上値が重くなるのも納得です。
また、米株市場(特にナスダックやS&P500)も、方向感に欠けるレンジ内での小動き。
これは投資家のリスク選好度が低下していたことを示していて、ドル買いにも円売りにもつながりにくい相場地合いだったと言えます。
さらに、地政学的リスクや中東情勢などの不安材料がくすぶっていたため、全体的に「積極的にリスクを取ろう」というムードではなく、リスクオフに傾きやすい土壌があったのも事実。
これら外部要因が複合的に絡み合い、「買いも売りも続かない」「動いてもすぐ反転する」という展開が生まれたのではないかと見ています。
各通貨ペア別の戦略・反省点
10月14日のトレードを振り返るうえで、通貨ペアごとの立ち回り方は大きな差が出ました。
得意なドル円ではある程度の成果を出せたものの、不慣れなユーロドルとポンド円では判断が甘く、収支を押し下げる結果に。
ここでは、各通貨ペアごとにどんな戦略をとったのか、実際のエントリーポイントやタイミング、そして反省すべき判断ミスについて、できるだけ具体的に振り返っていきます。
こうして戦略の良し悪しを分解することで、自分のクセや弱点にも気づきやすくなりますし、次につながる大事なステップだと思っています。
ドル円でうまく入れた場面・エントリーポイント分析
10月14日のドル円トレードで特にうまくいったのは、朝の9時台の上昇局面にうまく乗れたことでした。
東京市場のオープン直後、152.20円付近からじわじわと152.60円近くまで上がる流れを見て、「ここは素直に買いで入りやすい」と判断できたのが良かったです。
特に、チャートのサポートラインを確認しつつ、少し押し目を待ってからエントリーしたので、リスクを抑えつつ利益を伸ばせました。
このポイントは、多くのトレーダーが注目する時間帯でもあるため、動きが比較的読みやすかったのも勝因の一つ。
ただ、欲をかかずに早めに利確したのは、結果的に良かったと思っています。
ユーロドルでのミス・原因と対処策
一方、ユーロドルのトレードでは明らかにミスがありました。
慣れていないペアだけに、相場のクセや反応を読み違え、エントリータイミングを見誤ったことが最大の原因です。
具体的には、押し目買いのポイントだと思い込んで入ったところが、実は戻りの一時的な反発で、その後大きく逆方向に動いてしまったため、損切りが早くなりました。
対処策としては、まずユーロドルは値動きの癖がドル円と違うので、チャートのパターンやボラティリティをしっかり勉強し直す必要があります。
また、慣れない通貨ペアはポジションを控えめにし、損切りラインを厳しく設定するなど、リスク管理を徹底することが重要だと痛感しました。
ポンド円トレード振り返り、改善策
ポンド円についても、動きが荒い割には自分のエントリーが後手に回ってしまい、思ったほど利益が伸ばせませんでした。
特に、15時以降の下落局面でのショートは、入りどころが早すぎて損失を出してしまったのが大きな反省点です。
改善策としては、ポンド円の特徴である「急激な値動き」に慣れることが大切です。
例えば、指標発表や重要な要人発言の前後は、値幅が大きく跳ねることも多いため、そのリスクを考慮した上でエントリーする必要があります。
また、待つ勇気を持ち、動きが明確になるまで無理にポジションを取らないというメンタル面の強化も課題です。
ポンド円は短期勝負になりやすいので、特に慎重さが求められます。
ポジション管理・ロットサイズ配分の見直し
今回のトレード全体を通じて感じたのは、ポジション管理の重要性です。
特にユーロドルやポンド円のように不慣れな通貨ペアで、ロット数を同じにしてしまったことで損失が膨らみました。
次回以降は、得意なドル円に資金を集中しつつ、慣れていない通貨ペアはロットを抑えめにするなど、リスク分散のための配分を工夫したいと思います。
また、トレードの際は常に最大許容損失を意識し、負けが続いたら一旦取引を止めてリセットするルールを徹底していきます。
これにより、大きなドローダウンを防ぎ、安定的にトレードを続けられるはずです。
ポジションサイズの調整はメンタル管理にも直結するので、焦らず冷静に運用していきたいですね。

どの通貨を触るかより、どう向き合うかのほうが成績を左右する気がする。
今日の学び & 次回への戦略
マイナスで終わったトレードこそ、得られる気づきや学びは多いもの。
10月14日はまさに「いつもの自分じゃなかったな」と感じる一日で、収支以上に内容の粗さが目立った日でした。
ここでは、自分のトレード全体を通して「これは良かった」「ここは直すべき」といったポイントを整理しつつ、次回以降にどう活かすかを考えてみます。
勝ちも負けも冷静に受け止めて、少しずつ精度を上げていければと思っています。
こういう地味な振り返りの積み重ねが、結局は一番の成長につながると信じています。
成功要因を振り返って再現性のあるパターン
今回のトレードで成功したポイントは、やはり「冷静にチャートの流れを読み、無理のないタイミングでエントリーできたこと」だと思います。
特にドル円の朝9時台の上昇トレンドでは、勢いを見極めて押し目で拾えたことが勝因でした。
このパターンは再現性が高く、今後も「トレンドの初動を逃さずに入る」「押し目や戻りを待ってリスクを抑える」という基本に立ち返ることで、同じような利益を狙えそうです。
また、過度な欲張りを控え、適度な利益確定を心がけたことも結果を安定させる要因になりました。
焦らず丁寧にトレードする姿勢は、ぜひ継続していきたいですね。
失敗要因(煩雑になった通貨ペアへの挑戦、集中欠如など)
今回の失敗の最大の原因は、「慣れていないユーロドルやポンド円に無理に挑戦し、資金と意識が分散してしまったこと」です。
不慣れな通貨ペアは値動きのクセも違い、判断に迷う場面が多かったため、集中力が散漫になり、冷静なエントリーが難しくなりました。
特にポンド円の動きの荒さに対応しきれなかったのは、戦略不足と準備不足の表れです。
また、複数ペアを同時に追うことで情報処理が追いつかず、判断が遅れた結果、損失を重ねてしまった部分も反省点として挙げられます。
次回は得意ペアに絞るか、挑戦する場合も事前に戦略を明確にして取り組みたいです。
次回に向けた改善点・ルール強化ポイント
今回のトレードを踏まえ、まずは「通貨ペアの絞り込み」と「エントリー前の再確認ルール」を強化したいと思います。
具体的には、得意のドル円を中心に資金配分を集中させ、不慣れなペアはロットを極力抑え、チャートの動きをしっかり観察してからエントリーする方針です。
また、エントリー直前には「今日の相場背景」「指標発表の有無」「重要なサポート・レジスタンス」を再度チェックし、根拠のない無理なポジション取りを避けるようにします。
損切り設定もより厳格にし、負けを小さく抑えることを最優先に考えるルールを徹底します。こうしたルール強化が、次回の安定したトレードにつながると期待しています。
今日の収支を拡大するための戦略プラン
マイナス収支を出した今回の反省を活かし、収支を拡大するための戦略は「リスク管理の徹底」と「勝率の高いトレードに集中すること」です。
まず、ポジションサイズの適切な配分により、一回の損失が収支を大きく崩さないように調整します。
特に不慣れな通貨ペアでの過剰なエントリーは控え、得意なドル円に注力します。
次に、トレード前にその日の相場状況を丁寧に分析し、勝てるパターンだけを狙うこと。
無理なエントリーは避け、チャンスが来るまで待つ忍耐力を持つことが重要です。
さらに、メンタル面の管理も意識し、連敗時は冷静に損切りを徹底しつつ、一旦休憩を挟むルールも取り入れます。
これらを組み合わせることで、徐々にプラス収支を増やしていけるはずです。
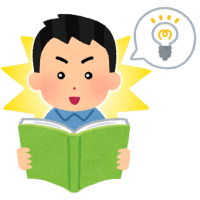
得意な土俵で勝負することが、最大のリスクヘッジになるんだな。
10月14日トレードで気になる疑問をスッキリ解決!
Q1:なぜ 10月14日には主要な米国指標の発表がなかったのか?
A:その日は米国で政府機関閉鎖が起こっており、多くの政府統計部門(例:労働省、商務省など)が機能停止状態となったため、通常予定されていた雇用統計や消費者物価などの指標発表が延期・中止されました。
Q2:パウエル議長の発言があってもドル円に大きな動きがなかったのはなぜ?
A:発言内容が市場の予想を超えるようなサプライズがなかったことと、指標材料が乏しかったため、マーケットに勢いを与えるきっかけにはならなかった可能性があります。
特に流動性が低い時間帯だったことも一因でしょう。
Q3:15時から 151.60円付近まで下落した場面で何が売り圧力につながったのか?
A:米金利低下期待の再燃やドル買い材料の鈍化、日本円買い戻しの圧力、リスクオフの動きなどが重なって、短期売りが加速した可能性があります。
また、レンジブレイクを狙ったトリガー売りも含まれたと想定されます。
Q4:9時台の上昇で152.60円付近まで達した背景は?
A:朝方のドル買い需要、前日の海外市場からの流れ、あるいは米債利回りの上昇や市場センチメントの改善(リスク許容度上昇)などが押し上げ要因となったと思われます。
Q5:なぜドル円は深夜~朝方にかけて151.60~151.80円のレンジに収まったのか?
A:材料難の時間帯で、参加者も手控えモードになったこと。
大口の動きも出にくく、値幅を出すには材料不足。加えて重要指標発表前の待機姿勢もレンジにつながったでしょう。
Q6:米金利見通しの変化は当日のドル円にどのように影響したか?
A:市場では、将来の利下げ期待や金利先高観が揺らぎつつある状況で、ドル買い材料とドル弱材料が交錯していたため、明確な方向感が出にくく、レンジ混戦になった可能性があります。
Q7:日本側の要人発言や政策観測は当日の値動きに影響したか?
A:記事に明記されていない限り影響は限定的だったと推察されますが、もしあれば、財務省や日銀関係者の「過度な円安への警戒」論調などが売り圧力を担った可能性があります。
Q8:ユーロドル・ポンド円を扱ったがなぜうまくいかなかったのか?
A:これら通貨ペアはドル円と比べて流動性やスプレッド、相場の方向性が複雑で、変動が読みにくいため、エントリー判断や損切りタイミングを誤りやすいという点が足を引っ張ったと考えられます。
Q9:この日の収支-スか?
A:この収支水準を出すには、通貨ペア、レバレッジ、取ったトレード回数、勝率・損益率のバランスが関係します。
もしポジションが大きすぎたり、損小利大の構成が崩れていた可能性があれば、安定性には改善余地があります。
Q10:10月14日の動きを踏まえて、今後ドル円で意識すべき水準はどこか?
A:この日はレンジ内での攻防が続いたため、151.60~152.60円が意識されるサポート・レジスタンス帯として引き継がれる可能性があります。
加えて、もしどちらか方向に抜ければ、153円近傍、または 151円割れを試す展開も視野に入れておくべきでしょう。
今日の取引から学ぶ重要ポイントまとめ
- 朝 152.20円付近からスタート → 9 時台上昇で 152.60円近辺到達。
- 9~15 時にかけて 151.60円付近まで下落、その後 18 時台にかけて再度 152.15円近辺まで戻る。
- 深夜~翌朝は 151.60~151.80円の狭いレンジで推移。
- 指標発表は米国機関閉鎖の影響で実質中止となり、材料不足の相場。
- パウエル議長の発言も目立ったトリガーにはならず。
- 主戦通貨はドル円、ユーロドル・ポンド円は不慣れゆえに足を引っ張る局面あり。
- 成功できたエントリー/戻しの読みと、失敗したペアでの対処を明確に振り返ることが重要。
- 次回は通貨ペアを絞る、リスク管理をより厳格にする、事前シナリオを複数持つこと。
10月14日は、為替材料が乏しい中でのレンジ展開が特徴的な一日でした。
朝方からのドル買い優勢で 152.60 円近くまで伸びたものの、午後にかけて利益確定や売りが成立し 151.60 円台まで押し戻され、夕方以降は再び戻す動きも出ました。
ただし、夜~翌朝にかけては大きなトレンドを作るには至らず、151.60~151.80 円あたりの狭いレンジに収まりました。
自分のトレードでは、ドル円での読みが的確にはまり、収益を取る場面がありましたが、ユーロドルやポンド円など不慣れな通貨ペアでのミスや判断遅れが収支を抑えた印象があります。
今回の収支-16,479 円は悪い成果ですので、トレードごとの精度やリスク管理をさらに詰めていきたいところです。
次回以降は、材料のある時間帯を重視しつつ、扱う通貨ペアを絞る、エントリーポイント・損切りルールを明確化する、そしてシナリオを複数立てておくことで、ぶれないトレードを目指したいと思います。
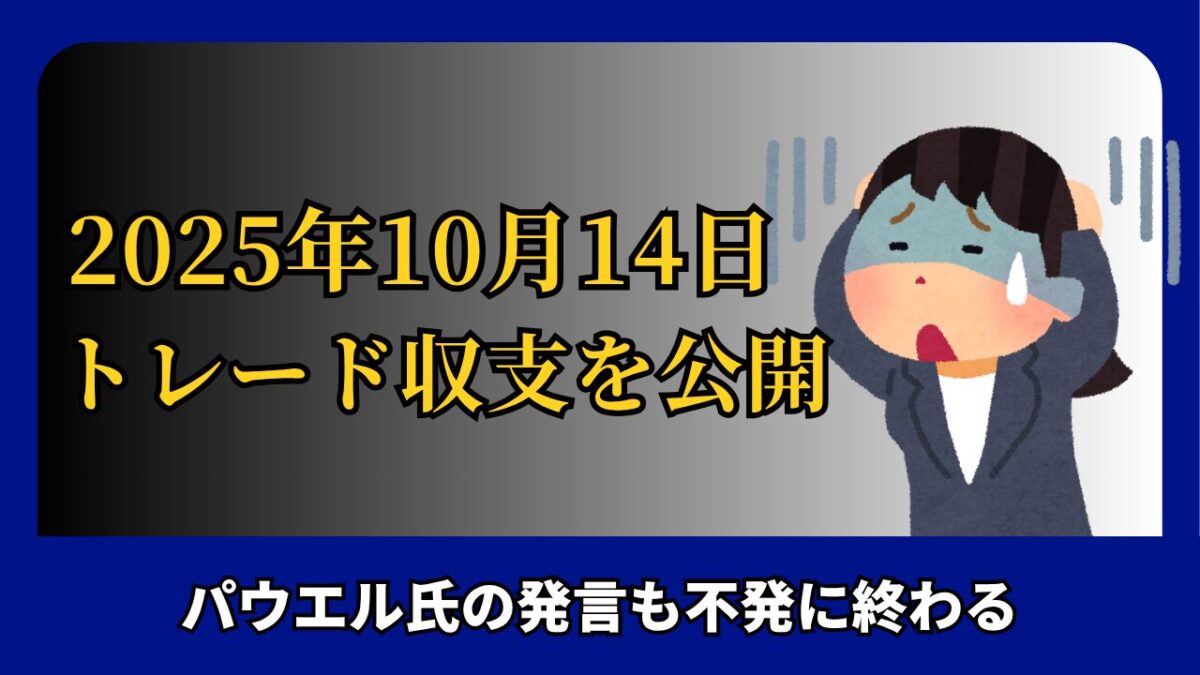




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン