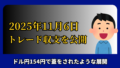朝から波乱のスタートでした。
株式市場がAI関連株の暴落で一気に崩れ、リスクオフムードが強まった11月5日。
ドル円は153.67円付近で始まったものの、10時台には152.96円まで急落。
その後はじわじわと切り返し、夜には154円台を回復するという、上下の激しい一日になりました。
そんな相場の中で、私はドル円と豪ドル円をメインにトレードしましたが、結果はマイナス9,783円。
焦りからチキン利確を繰り返し、損切り分を取り返すこともできず、まさに「歯車がかみ合わない一日」でした。
この記事では、11月5日のドル円相場の動きや経済指標、そして自分のトレードの振り返りを通じて、「焦り」がどれほど判断を狂わせるのかをリアルに記録しています。
同じように日々トレードに向き合う方の参考になればうれしいです。
- 11月5日のドル円レートと相場環境
- 経済指標・要人発言がトレードに及ぼした影響
- 本日の自分のトレード戦略とミスの要因
- 今日の反省点から学んだ3つの教訓
- 次回トレードへの改善アクションプラン
- 当日のドル円相場をより深く理解するための10の質問と回答
- Q1:11月5日のドル円レートが「朝153.67円→10時台152.96円」まで下落したのは何が原因ですか?
- Q2:22時台からドル円が再び上昇して午前1時台に154.35円付近まで上がったのはなぜですか?
- Q3:豪ドル円を少しだけ取引されたとのことですが、どんな意図でしたか?
- Q4:「チキン利確してしまった」とありますが、なぜ利確タイミングが早まったのでしょうか?
- Q5:収支が-9,783円となった中で「損切分も取り返せず」だった理由は?
- Q6:「154円半ばは今回の上昇トレンドの天井として意識されている」とありますが、その根拠は何でしょう?
- Q7:指標発表前にドル円が上昇した「漏れ情報」の噂とは?それは信頼できるのでしょうか?
- Q8:株式暴落が為替に与えた影響は具体的にどのようなものですか?
- Q9:今回のレンジ推移(13時~21時153.40〜153.75円)でトレードを控えるべきだったのでしょうか?
- Q10:次回以降、このような「焦り」が出ないようにするにはどうすればいいですか?
- まとめ|2025年11月5日のFXトレードで得た教訓と改善策
11月5日のドル円レートと相場環境
11月5日の相場は、まさに“朝から波乱”という言葉がぴったりの一日でした。
東京市場のオープンと同時に株式市場が急落し、AI関連株を中心に売りが殺到。
為替市場でもリスクオフの流れが強まり、ドル円は朝の153.67円付近から一気に152円台後半まで値を崩しました。
テクニカルよりもニュースが優先されるような、荒れた地合いです。
私はそんな中で「底を拾う」意識が強くなりすぎてしまいました。
下げの勢いを感じながらも、これまでの流れを信じて買い下がる戦略を取ったものの、動きは想定以上に激しく、精神的にも振り回される展開。
ここでは、11月5日のドル円レートの推移や株式市場の影響、そして当日の値動きがどんな環境の中で起きたのかを整理していきます。
朝のドル円153.67円付近スタートと10時台152.96円までの急落
11月5日の東京市場は、朝から波乱の幕開けでした。
ドル円は153.67円付近で取引をスタートしましたが、10時台にかけて急速に円高が進行し、一時152.96円付近まで下落しました。
背景には、株式市場の急落があります。
AI関連株を中心に投げ売りが広がり、リスク回避の動きが強まったことで、円買いが進行しました。
朝方は特にボラティリティが高く、テクニカルもほとんど機能しない「一方向の下げ」でした。
私はこの下げの中で、ドル円を段階的に買い下がる戦略を取りました。
しかし、値動きが荒い中でのポジション追加は精神的にも負担が大きく、「ここが底だろう」と思うたびにさらに下を掘る展開。
焦りと不安が混じり合う難しいスタートでした。
13時~21時153.40〜153.75円のレンジ推移と22時台以降の154円台上昇
昼以降は相場が一旦落ち着きを取り戻し、13時~21時あたりは153.40~153.75円付近のレンジで推移しました。
欧州勢の参入後もトレンドは明確に出ず、まさに「待ち時間」が続く展開。
この時間帯は小幅な値動きが続き、スキャルピング狙いで細かく取る戦略ならまだしも、トレンドフォロー型の私にはやや退屈な相場でした。
しかし22時台になると空気が一変します。
ADP雇用統計の発表前後からドル買いが強まり、154円台に乗せる展開。
最終的に午前1時台には154.35円付近まで上昇し、当日の最高値を記録しました。
その後は154円前後で推移し、相場全体としては底堅さを感じさせる動きでした。
株式暴落・AI株ショックからの為替反応と豪円も関与
この日の相場を語る上で欠かせないのが、朝の株式暴落。
AI株の急落がきっかけとなり、日経平均をはじめとする主要株価指数が一気に売られました。
その影響は為替市場にも波及し、ドル円・豪ドル円の両方で急落が発生しました。
特に豪ドル円は、リスク資産の代表格として敏感に反応し、序盤は大きく下げました。
私はドル円を主軸にしつつ、リスク分散として豪ドル円も少しだけエントリー。
結果的には方向感を掴みきれず、こちらでも利幅を伸ばせない展開となりました。
「株と為替はつながっている」と再認識させられた一日です。

朝の急落時に焦ってエントリーすると、方向感を掴みにくくなることが多いです。
冷静な判断が利益を左右します。
経済指標・要人発言がトレードに及ぼした影響
11月5日は、指標や発言の多い1日でした。
特に夜の米ADP雇用統計やISM非製造業景気指数、サービス業PMIの発表が相場の方向性を決める大きな材料に。
東京時間での株式暴落で荒れた後、ニューヨーク時間にかけては「ドル買いが戻るかどうか」に注目が集まりました。
指標前からドル円は上昇し始め、「結果が漏れたのでは」という噂も飛び交う中で、私もポジションを持つべきか迷いました。
ここでは、当日の主要指標の結果と市場反応、そしてトレーダー心理への影響を自分の体験を交えて振り返ります。
ADP雇用統計(予想3.8万人・結果4.2万人)と市場の反応
夜のメインイベントとなったのが、米ADP雇用統計。
予想3.8万人に対して結果は4.2万人とやや強い内容でした。
この結果を受けてドル円は上昇し、22時台から買いが加速しました。
一部では「結果が漏れていたのでは?」という噂もあり、実際に指標発表前からドル買いが進んでいました。
こうした“事前の動き”に惑わされると、早すぎるポジション取りをしてしまうリスクがあります。
私もこの上昇局面では「乗り遅れたくない」という気持ちが先行してしまい、焦りながらエントリーしてしまいました。
ISM非製造業景気指数(予想50.8・結果52.4)およびサービス業PMI(予想55.2・結果54.8)
ADPの後には、ISM非製造業景気指数とサービス業PMIが続きました。
どちらもほぼ市場予想に近い数字で、特に強弱を分けるほどのサプライズはなし。
しかし、数字の「安定感」が逆にドルの支えとなり、ドル円の上昇を後押ししました。
指標後の動きを見ると、相場全体が「強いドルを織り込みにいく」流れでした。
このあたりで私は一度ポジションを軽くしてしまったのですが、結果的にはその後に上昇が続き、利益を取り逃す形に。
焦って建て、焦って手仕舞う。
まさに今日のテーマそのものです。
指標前のドル円上昇と「漏れ情報」噂が招いたトレード心理のズレ
FXではよくある話ですが、「情報が漏れたのでは?」という噂が流れると、トレーダー心理が一気に傾きます。
当日も指標発表の1時間ほど前からドル円がじわじわ上昇を始め、SNSやチャットでも「ADP強いらしい」といった投稿が相次ぎました。
私もこの流れに惑わされ、通常ならエントリーポイントを明確に待つところを、つい“感覚トレード”に走ってしまいました。
結果的に中途半端な位置でのエントリーとなり、損切りラインも浅く設定しすぎてしまったことが、マイナスにつながりました。

噂やSNS情報で動くと、トレード判断がブレやすくなります。
公式発表前の動きには注意が必要です。
本日の自分のトレード戦略とミスの要因
この日は、相場の荒れ具合に反して自分の戦略は少し強引でした。
「押し目買いで取れるだろう」という固定観念のまま挑んでしまい、結果として流れに逆らうトレードになってしまいました。
焦りと過信が混ざり、冷静さを欠いた判断の連続。
特にドル円と豪ドル円のダブルエントリーが裏目に出て、思ったように利益を伸ばせませんでした。
ここでは、私がどんな根拠でポジションを取ったのか、そしてなぜその判断が間違っていたのかを整理し、次に活かすためのヒントをまとめます。
ドル円・豪ドル円を底値まで買い下がった戦略
11月5日は、朝の急落を見て「これは押し目買いのチャンスだ」と判断しました。
153円を割った水準は何度も意識されていたサポートゾーンだったため、私は152.9円台から段階的に買い下がる戦略を選択しました。
最初のうちは悪くなかったのですが、結果的には下げの勢いが予想よりも強く、追加エントリーのタイミングが早すぎました。
建値が中途半端に近くなり、リスクが広がってしまったのが反省点です。
また、豪ドル円にも少しエントリーしましたが、こちらは株式市場のリスクオフで想定外に下落。
クロス円全体が弱くなる中、豪ドル円はドル円以上に振れが大きく、結局こちらもわずかな利益で逃げてしまいました。
「焦らず、1つの通貨ペアに集中すべきだった」と感じました。
チキン利確による損切分の未回収と「歯車が噛み合わなかった」理由

底値で拾ったドル円は、一時的に含み益になりました。
しかし、そのあとに相場が伸びきる前に利確してしまい、結局損切り分を取り返せないまま。
典型的なチキン利確です。
なぜ焦ったのか。
それは「さっきまでの下げが怖かった」から。
急落を経験した直後というのは、どうしても“また下がるかもしれない”という不安が残ります。
この心理的なブレーキが強すぎて、せっかくの上昇波を最後まで握れませんでした。
トレード中の自分を振り返ると、冷静さよりも「早く取り返したい」という気持ちが前に出ていました。
相場のリズムと自分のリズムが完全に噛み合っていなかった日。
結果として-9,783円という損失を出し、「焦り」が一番の敵だと再確認しました。
「焦り」が招いたメンタルのズレと資金管理の甘さ
焦りはメンタルだけでなく、資金管理にも悪影響を与えます。
いつもならリスクを計算してポジションを立てるところを、この日は「早く入らなきゃ」と感情で動いてしまいました。
損切りラインを曖昧にしてしまい、ロットを少し増やしたのも失敗の一因。
自分では“少しの調整”のつもりでも、積み重ねると大きな違いになります。
メンタルの乱れはチャートに現れます。
そして一度崩れると、正しい判断がどんどんできなくなります。
焦ったままのトレードは本当に危険ですね。
この1日で、改めて「感情をコントロールする大切さ」を思い知りました。
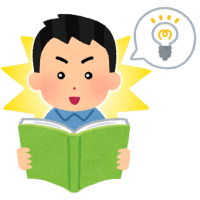
少しのロット増やしも、積み重なると大きな損失に。
感情でのポジション操作は避けるのが基本です。
今日の反省点から学んだ3つの教訓
一日を終えて、チャートを見返しながら真っ先に思ったのは「やっぱり焦りはトレードの敵だな」ということでした。
エントリーも利確も、焦るとすべてが雑になります。
11月5日のトレードはまさにその典型。勝てる相場ではあったのに、自分のメンタル次第で結果が逆転してしまいました。
この章では、今回のトレードから得た“3つの教訓”を整理します。
どれも難しいことではなく、日々の積み重ねで意識すれば変えられる内容ばかりです。
同じように焦りや迷いでミスをした経験がある方にも、共感してもらえると思います。
教訓①:十分な根拠がないままエントリーするな
相場が荒れているときほど、「ここが底だ」と決めつけたくなります。
しかし、それは根拠ではなく願望です。
今回のように株式市場が崩れている日は、テクニカルよりもファンダメンタルズ(市場全体の流れ)が勝ちます。
しっかりとトレンドの確認をしてからエントリーする。
この基本を守れなかったのが第一の反省です。

願望で入ったポジションは、損切りも遅れがちです。
冷静な分析を優先する習慣が重要です。
教訓②:利確・損切りの基準をあらかじめ決めておけ
一番悔しかったのは、利益を伸ばせなかったこと。
「まだ上がる」と思って握るならいいのですが、「下がるのが怖いから逃げる」という理由で利確しても意味がありません。
感情ではなく、数字で判断する。
利確・損切りラインを明確にしておけば、焦ってもブレません。
これはすぐにでも改善できるポイントだと思います。
教訓③:相場環境があまりにも非日常ならばポジションを抑えめに
AI株暴落やADPリーク疑惑など、11月5日は“特別な日”でした。
こういう日に無理に普段通りのトレードをしようとすると、ほぼ間違いなくリズムが狂います。
「今日は荒れているからロットを落とす」「もしくは見送る」
その判断ができるかどうかで結果が大きく変わる。
自分にとって、これが一番大きな学びになりました。
次回トレードへの改善アクションプラン
反省で終わらせるだけでは意味がありません。
大事なのは「どう直すか」。
11月5日の失敗を冷静に見つめ直すと、改善できる点がいくつも見えてきました。
メンタルの持ち方、ロットの調整、指標時の対応など、次に同じ状況が来たときにどう動くかを明確にしておくことが大切です。
この章では、私自身がこれから意識していく“実践的な改善ポイント”を整理しました。
焦りや過信に振り回されないための、具体的な行動ステップをまとめています。
ポジションサイズとリスク許容度を見直す
次回からは、相場状況に応じてロット数を調整するルールを設けます。
急落局面ではまず様子見を入れ、落ち着いてから入る。
そして、ロットを上げるのは「勝ちパターン」が明確に出たときだけ。
資金を守る意識を最優先にします。
経済指標発表時・要人発言時の動きを事前にシミュレーション
今回のように、ADPやISMなどの発表が複数重なる日は、事前に「もし結果が良かったら」「悪かったら」の動きを想定しておくべきでした。
実際に書き出しておくことで、発表後に焦らず行動できるはずです。
「どう動くか」よりも、「動いた後どうするか」を準備しておくことが重要。
精神状態(焦り・過信・疲れ)を可視化して、セルフチェックを実施
トレードノートにチャートだけでなく、そのときの気分や体調も記録しておくようにします。
焦っているとき、眠いとき、体調が悪いときはトレードの質が確実に落ちる。
数日分の記録を見返すだけでも、自分の癖や弱点が見えてくるものです。
感情をデータ化して、再現性のあるトレードを目指したいと思います。

感情や体調もデータ化すれば、再現性のあるトレード戦略の構築につながります。
当日のドル円相場をより深く理解するための10の質問と回答
ここでは振り返りとして、11月5日の相場を客観的に整理しておきます。
当日の為替市場は、株式の急落や指標発表などさまざまな要素が絡み合った一日でした。
以下では、相場背景・指標の反応・要人発言などを中心に、11月5日の為替相場をより深く理解するための10のQ&Aを紹介します。
Q1:11月5日のドル円レートが「朝153.67円→10時台152.96円」まで下落したのは何が原因ですか?
A1:この日は朝から株式市場でAI株を起点とした暴落が起き、リスクオフの動きが一気に進行しました。
その波及で安全資産の円買いが強まり、ドル円が朝高から急落しました。
加えて、指標発表が迫っていたため「一旦調整」の売りが出やすかったです。
Q2:22時台からドル円が再び上昇して午前1時台に154.35円付近まで上がったのはなぜですか?
A2:指標発表後にドル買いが優勢になったことと、相場参加者が152円台で拾っていた買いを徐々に利確・押し目買いに切り替えた流れがあるためです。
また、154円半ばが上昇トレンドの天井として意識されており、そこまでの戻りが出やすい環境でもありました。
Q3:豪ドル円を少しだけ取引されたとのことですが、どんな意図でしたか?
A3:ドル円メインで参加する中、リスクオフ・リスクオンの振れも出そうだったため、通貨分散を意図して豪ドル円も少量エントリーしました。
結果として主通貨に比べて利益機会を活かせず「焦ってしまった」感が反省点として残りました。
Q4:「チキン利確してしまった」とありますが、なぜ利確タイミングが早まったのでしょうか?
A4:急落後の安値買いという展開だったため「欲張らずに一旦利益を確保しよう」という思いが先行し、利確基準を明確に決めず流れに身を任せてしまいました。
焦りが背景にあり、「底値を拾ったから必ず上がる」という過信も影響していました。
Q5:収支が-9,783円となった中で「損切分も取り返せず」だった理由は?
A5:損切りが発生した後、ポジション的にもメンタル的にも冷静さを欠き、次の押し目をしっかり待てずに再度買いに入ったことでリスクが増え、回復のタイミングを逃しました。
加えて、レンジ相場となった13時~21時の時間帯で明確なトレンドを取れなかったのも回復を妨げた要因でした。
Q6:「154円半ばは今回の上昇トレンドの天井として意識されている」とありますが、その根拠は何でしょう?
A6:市場参加者の多くが154円半ばを上値のレジスタンス(抵抗帯)と認識しており、過去の上昇局面で同水準で反落した実績があります。
そのため「この付近まで上がれば一旦売られる可能性がある」と意識され、結果的に22時台以降の上昇でも154.35円あたりで戻り売りが出やすい状況になりました。
Q7:指標発表前にドル円が上昇した「漏れ情報」の噂とは?それは信頼できるのでしょうか?
A7:当日、指標発表前に「ADP雇用統計の結果が一部リークされたのでは」という市場の噂があり、これがドル買いを誘った可能性があります。
しかし、公式には確認されておらず、あくまで「噂レベル」です。
こうした情報に反応して動くと、思わぬ位置でポジションを取るリスクが高まるため注意が必要です。
Q8:株式暴落が為替に与えた影響は具体的にどのようなものですか?
A8:当日、AI関連株を中心に株式が急落しました。
これによりリスク回避の動きが加速し、円買い・ドル売りが進行しました。
特に朝のドル円急落は、株式市場の不安が為替にも波及した典型的な例です。
FXを取る際には株式の動きにも目を配ることが重要だと改めて感じました。
Q9:今回のレンジ推移(13時~21時153.40〜153.75円)でトレードを控えるべきだったのでしょうか?
A9:レンジ相場はトレンドが明確でないため、利幅を取りにくく、損失につながる可能性が高まります。
この時間帯では「大きく動く期待」が低くなっており、本来ならばポジションを控えるか、利益確定・損切りルールを厳守すべきでした。
私自身、この点を軽視してしまいました。
Q10:次回以降、このような「焦り」が出ないようにするにはどうすればいいですか?
A10:まずは取引前に「エントリー・利確・損切り」の基準を紙に書き出しておくことが有効です。
そして、相場が異常に変動している時(今回の株式暴落など)は、ポジションサイズを減らして参加する、もしくは休むというルールを設けるのが良いでしょう。
また、トレード後に必ず振り返りをして「焦っていたかどうか」を自分で点検することも習慣化したいと思います。
まとめ|2025年11月5日のFXトレードで得た教訓と改善策
- ドル円は朝153.67円付近スタート→10時台152.96円まで急落→13時〜21時153.40〜153.75円レンジ→22時台以降から上昇し、午前1時台に154.35円付近で当日最高値。
- 株式市場でAI株が引き金となる暴落発生、リスクオフで円買いが強まった。
- 指標ではADP雇用統計・ISM非製造業景気指数・サービス業PMIが発表され、ドル円に影響を与えた。
- 自分のトレードはドル円・豪ドル円を底値買い下がりする戦略だったが、チキン利確・メンタルの焦り・損切分取り返せずで反省点多数。
- 学んだ教訓:根拠のないエントリーを避ける、利確・損切り基準を明確にする、メンタル管理を徹底する。
- 次回の改善アクション:ポジションサイズを見直す、指標発表・異常相場時は控えめに、焦りチェックを習慣化。
本日のトレードを振り返ると、相場の流れ・経済指標・株式市場との連動という“3つの要素”を理解していたつもりでしたが、焦りと過信が混ざり合って、冷静さを欠いたエントリー・利確・損切り判断になってしまいました。
特に、底値買い下がろうという戦略が「取れそう」という気持ちに変わり、チキン利確という自らの癖を発動させてしまったのが痛かったです。
次回は今日の反省を活かして、ルールを守るトレード、精神を整えたトレードを徹底していきたいと思います。
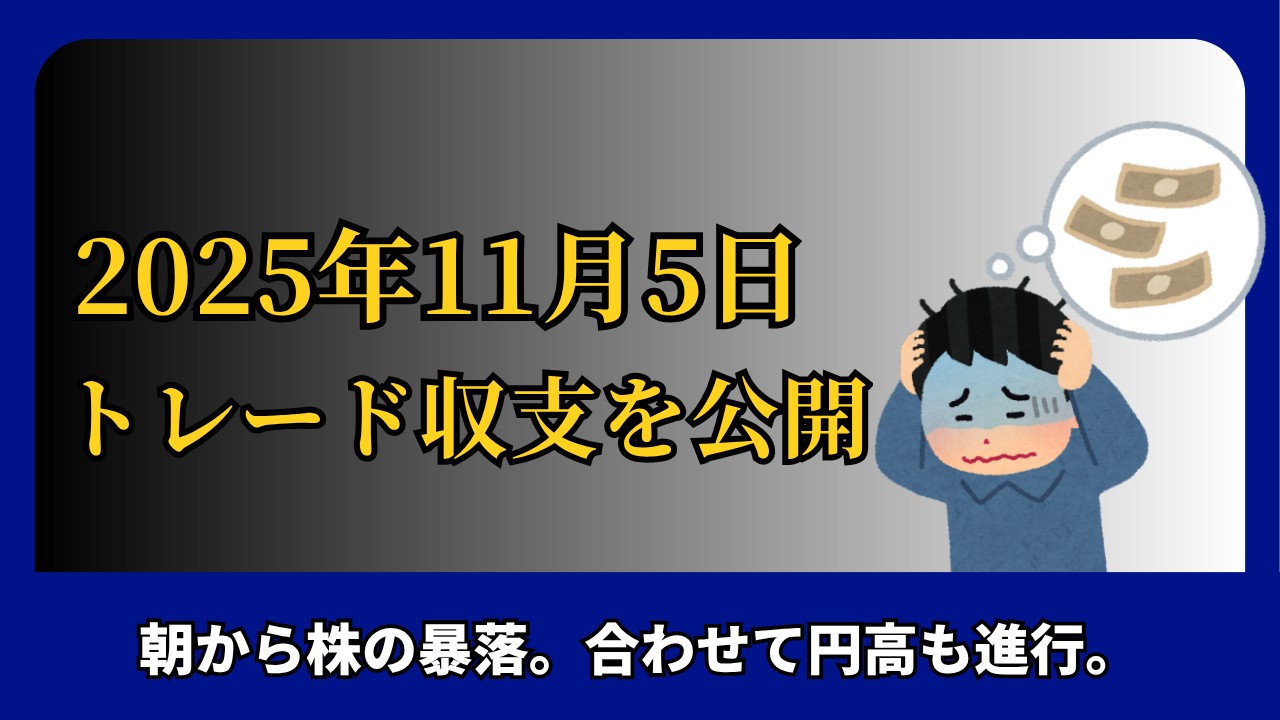




 ひまわり証券
ひまわり証券
 外為オンライン
外為オンライン